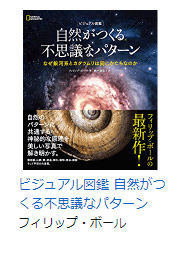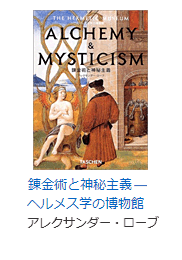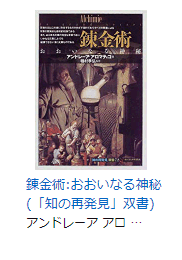No.A7X_hc_hermes
作成 1998.2
「ヘルメス思想」の謎

■■第1章:ヘルメス・トリスメギストス
■三重に偉大なヘルメス
ヘルメス・トリスメギストスとは、「三重に偉大なヘルメス」の意味であり、そしてヘルメスとは、いうまでもなくギリシア神話に登場する、オリンポス12神の一柱である。ギリシア神話では、ヘルメスは死者の魂の導き手として、生と死の境を自由に行き来できる使者であり、商業と学問の神であった。
また、エジプトの守護神トートと習合して、ヘルメス・トートとも呼ばれる。トートも同じく冥府の神であり書物の神であった。さらにヘルメスは、ローマ神話の神でトートと同じような役割を果たしていたメルクリウス(マーキュリー)とも同一視されている。


ギリシア神話に登場するヘルメス神
※ 錬金術の象徴である「ヘルメスの杖」を
持っている(右は拡大した画像である)
このように、ヘルメス・トリスメギストスは、古代の3人の神として人類の前に登場しているのである。「三重に偉大な」とは、そうした意味をも含んでいるのである。
だが、秘教の伝承によれば、この「三重に偉大な」という表現には別の理由があり、ヘルメスは実際に存在した人間で、3回転生して活躍した偉大な賢者だったとされている。
はじめはアダムの孫として天文学の研究に携わり、ピラミッドを建造した賢者として生まれ、次はノアの大洪水後のバビロニアにおいて、自然科学・哲学・医学・数学の賢者で、ギリシアの哲学者ピタゴラスの師として生まれた。そして最後の生まれ変わりのときは、モーセと同じ時代のエジプトにおいて都市計画に携わり、化学・医学・哲学の賢者だったという。
また、ヘルメスは、生涯に3万6525冊の本を書いたとされ、宇宙の森羅万象を究めて、人類に医学・化学・哲学・法律・芸術・数学・占星術・音楽・魔術などのあらゆる知識をもたらしたといわれている。紀元後2世紀のアレクサンドリアの学者クレメンスは、その膨大な量の本のエッセンスは最終的に42冊の本にまとめられたとしているが、これらの書物は、一般に「ヘルメス文書」と総称されている。
ヘルメス文書という名称は、これらの文書が、主に導師ヘルメス・トリスメギストス、が、弟子に教えを授けるという形式で書かれていることに由来する。これらの文書のほとんどはギリシア語で書かれ、おおむね紀元前3世紀から紀元後3世紀に至る600年間に、エジプトで製作されたと考えられている。
もちろん、ここでいう「製作された」とは、あくまでも「写本の形で編纂された」という意味であり、その内容のすべてが、この600年の間に一から創りだされたという意味ではない。そこに盛り込まれた叡智がどれほどの過去にまで遡りうるものかは、いまだに判然としていないのである。
現在、一般にヘルメス文書の名で呼ばれているものとしては、『コルプス・ヘルメニクム』や『アスクレピオス』、『ポイマンドレース』などがあるが、その中でも精髄というべき最重要の書物こそ『エメラルド・タブレット』であるのだ。
■錬金術の奥義書『エメラルド・タブレット』の行方
ヘルメスの死後、『エメラルド・タブレット』は彼の死体とともに埋葬されたが、その正確な場所は失われてしまう。そして、それから2000年を経て、このタブレットは再び歴史に姿を現した。なんと、ヘルメスの死体は、エジプトのギザの大ピラミッドの中に安置されており、タブレットはその手中にしっかり握られていたというのである。これを発見したのは、この地を征服したアレクサンドロス大王であったという。
とはいうものの、むろん、以上は単なる伝承であり、その信憑性を云々することはできなかった。タブレットの原文も失われ、長い間、この碑板の内容は、10世紀に製作されたアラビア語訳、およびそれに基づく12世紀のラテン語訳によって知られるのみだったのである。
そのため、この伝承のみならず、タブレットの内容自体が後世の創作だ、とまでいわれることもあった。たとえば17世紀の著名なオカルティスト、アタナシウス・キルヒャーまでもが、このタブレットは「ライムンドゥス・ルルス以前には存在しなかった」と述べ、暗にルルスの創作であることをほのめかしている。
だが、1828年、エジプトのテーベにおいて、紀元4世紀の魔術師の墓から大量のパピルス文書「ライデン・パピルス」が発掘され、驚くべきことに、この文書の中に、『エメラルド・タブレット』の最古の写しが含まれていたのである。
つまり、仮に先の伝承の全てが事実ではないにしても、そこには幾分かの真実の断片が含まれていること、そして何よりも、『エメラルド・タブレット』の起源自体が相当に古いものであることが確認されたのだ。
■大ピラミッドを建造したのは「ヘルメス=エノク」だった!?
ヘルメスの死体は、エジプトのギザの大ピラミッドの中に安置されており、タブレットはその手中にしっかり握られていた──。これだけでも驚くべき話だが、
さらに驚くべきことに、そもそも大ピラミッドを築いたのはヘルメス本人だったという伝承も残されており、それを裏づける資料もある。

エジプトのギザの大ピラミッド
例えば、14世紀エジプトの歴史家アル・マクリージーの『群国誌』の一節である。
「最初のヘルメスは、預言者で王で賢人であるということから〈3つの顔を持つ者〉と呼ばれ、これはヘブライ人がエノクと呼ぶ人物で、またの名はイドリスである。彼は星を読んで洪水の到来を預言した。また、ピラミッドを建造させて、宝物や学問的な著作をはじめ、散逸しないように守っていた品々をことごとく隠して、保管をはかった」
なんと、大洪水の前にピラミッドを建造させたのが「最初のヘルメス」であり、この人物はまたエノクとも、イドリスとも呼ばれていたというのだ。この他にも、アラブ人歴史家アル・マキールやイブン・バトゥータも、ヘルメスをエノクと呼んで紹介している。
◆
『旧約聖書』にも登場するエノクは、ノアの洪水以前に生きた超人種族の一員であり、あらゆる秘教の元締めとされている人物だ。生きながら天に昇ったというエピソードを持ち、彼が天使との会話に用いた言語「エノク語」は、至高の力と叡智をもたらす呪文ともなる。また、イドリスはアラブの伝承に登場する「太古の賢人」である。
そして驚くことに、アラブ人にとって、大ピラミッドが大洪水以前の建造物であることは、なかば常識であったといっても過言ではないようなのだ。
9世紀後半、アブ・バルキは、こう述べている。
「大洪水の直前、多くの賢人は天変地異を予言した。彼らは地上の生物や文明の叡智が失われることを憂慮し、エジプトの大地に石造りの塔を建設した」
アブ・バルキとほぼ同時代のアラブ人マウスティーは、著書『黄金の牧場と宝石の山』のなかで、大ピラミッドについて、もっと詳しく述べている。
「大洪水以前のエジプト王サウリドは、巨大なピラミッドを建設した。彼は、大洪水が起こる300年も前、大地がねじ曲がる夢を見たからだ。……ピラミッドには金銀財宝はもとより、数学や天文学をはじめとする科学の知識が詰められた」
ここでいうエジプト王「サウリド」とはイドリスと同一人物で、いうまでもなくヘルメスの別名である。混乱を防ぐため、ここで一応、整理しておこう。「ヘルメス=エノク=イドリス=サウリド」である──。
◆
このほかにも、アラブ人の歴史家ワトワティ、マクリーミ、ソラール、アルディミスギらなど、一様に大ピラミッドを建設したのはエノク(=ヘルメス)であると著書に書き記している。
なかでも、最も有名なのは、歴史家にして旅行家のイブン・バトゥータである。14世紀、彼はアラブ世界のみならず、エジプトからアジア、なんと中国にまでやってきている。イブン・バトゥータが記した『旅行記』には、こうある。
「エノクが大ピラミッドを建設した目的は、大洪水から貴重な宝物と『知識の書』を守るためだった……」
この『知識の書』とは、『エメラルド・タブレット』のことを指している可能性が高い。
ところで、余談になるが、あの秘密結社フリーメイソンの一部には、『エメラルド・タブレット』は、彼らの伝説的な始祖ヒラム・アビフが製作したとの伝承が伝わっている。すなわち、ヒラム・アビフもまた、ヘルメスであったらしいのである。ヒラム・アビフはソロモン王の第一神殿を建立した石工の棟梁とされているが、フリーメイソン自体、大ピラミッドの建造に関わった古代の建築者/秘儀伝承者集団に起源を持つという。
■■第2章:錬金術の謎 ~人間の変成を目指す「神秘錬金術」~
■錬金術と「賢者の石」
西欧神秘主義において、ヘルメスは特別な存在である。とくに錬金術においては、まさに始祖ともいうべき存在である。そのため、「錬金術」は「ヘルメスの術」とも呼ばれている。
錬金術とヘルメス文書は、切っても切れない関係にある。あえていうなら、この両者は表裏一体であり、一方が欠ければ、もう一方も成立しない。すなわちヘルメス文書が「文字に記された叡智」であるならば、ヘルメスの術すなわち錬金術は、「文字に記されざる叡智」である。自らの手と肉体と精神を総動員して実践することによってのみ、初めて知解しうる叡智である。
一般に錬金術の目的とは、文字通り「黄金」を製造することにあったとされている。実際、14世紀のフランスで『象形寓意図の書』を著したニコラ・フラメルという著名な錬金術師は、1000回以上の錬金術の実験を重ねたのち、1382年に水銀をほぼ同量の金に変えることに成功したと言われている。
錬金術をこうした「無限の富を生み出す秘法」としてみれば、確かに人間の欲望を直接刺激するマジックとして映るだろう。
なお、厳密に言えば、錬金術の“最終目標”は黄金を作ることではなく、「賢者の石」を手にすることであった。「賢者の石」とは、卑金属を金に変える究極の物質である。
「賢者の石」さえあれば、どんなものでも金にできると考えられてきた。その意味で、金よりも重要な物質といえる。錬金術師は「賢者の石」を「錬金薬(エリクシール)」と呼びならわしてきた。が、しかし、歴史上、誰ひとりとして、「賢者の石」を精製できた者はいない。それはそうである。卑金属を金に変える物質などありえないからだ。核変換でもしない限り、金以外の元素から金を作ることはできないのだ。
そう考えると、「錬金術など、化学的な知識のなかった時代の人々の幻想にすぎない。化学変化の実験によって、いろいろな化合物が見つかり、化学の発展に寄与はしたが、肝心の『賢者の石』を精製することはできなかった。結局、錬金術など、単なるオカルトのお遊びにしかすぎない──」という評価が幅をきかせることになる。
しかし、本当にそうであろうか? 錬金術は単なる世俗的な富を求める人々の道楽にすぎなかったのだろうか? 錬金術文献には、「われらの黄金は世俗の黄金にあらず」、「汝ら自身をして生ける〈賢者の石〉に変成せしめよ」などの言葉が散見される。どうやら、錬金術師のいう黄金を文字どおりの意味に解すると、道を誤ることになるとおぼしいのだ。
果たして、錬金術の真の目的は何だったのか?
■錬金術を精神的な修行と解釈したユング
20世紀最高の知的巨人のひとりである、分析心理学の泰斗カール・グスタフ・ユングは、中世・ルネサンス期に製作された、数多くの錬金術図像に着目した。

カール・グスタフ・ユング
錬金術の文献では、言葉では語りえぬ叡智を、一部の選ばれた者にのみ正しく伝えるため、一見したところではまったく意味のわからない象徴的な図像が多用されている。ところが、心理学者として多くの精神病患者と接していたユングは、彼らの夢の中に、錬金術図像に描かれたものと同一のイメージが、たくさん出現することに気づいたのである。すなわち、精神病患者の夢と錬金術は、共通の言語を持っていたのだ。
ユングはこの発見に基づいて、錬金術師たちは自らそれと知らないうちに、象徴言語を用いて自らの無意識を探究し、これを図像化する試みを行っていたと結論した。すなわち彼らの残した図像は、人間の無意識の領土の地図にほかならないのだ、と。
ユングによれば、錬金術師たちの行っていた黄金錬成(大いなる作業)とは、とりもなおさず、個々の錬金術師自身が、知らず知らずのうちに行っていた「個性化」と呼ばれる、精神的陶冶の作業過程である。そして、個性化によって得られる「黄金」とは、作業の結果として得られる完成された「精神」であり、洋の東西を問わず、神秘体験に共通して見られる意識の変容状態を意味しているという。
単なる詐術、あるいは無知と迷信から生まれた未熟な化学という、それまでの錬金術理解に比較して、この術を精神的な一種の「修行法」と見なすユングの研究は、まさに画期的なものであった。20世紀以降の包括的な錬金術理解への道程は、まさしく彼によってその第一歩を踏みだすことが可能になった、といっても過言ではないだろう。
■錬金術の作業が象徴する哲学的意味
19世紀の神秘主義の大家エリファス・レヴィによれば「大いなる作業=錬金術とは、なによりもまず、人間の彼自身による創造、すなわち己れの能力および将来に対して行うあますごとなき征服」だという。

エリファス・レヴィ
錬金術は全てのものに神=宇宙精神が内在すると教える。つまり、この大宇宙の根本原理は、無限の形態を通じて顕現するのだ。宇宙原理は私たちの物質的宇宙のあらゆるものに“種子”として潜んでいるのである。とすれば、術によってこの種子を育て、その本質的で完全な姿へと変容させることも十分に可能だ。卑金属に潜む種子に働きかけて、“哲学者の金”に育て上げることもできるはずなのである。
これがよく知られている錬金術の原理だ。だから、術の根本は、“大いなる作業”なのである。すなわち、文字通りの実験作業なのである。
「卑金属」とは、この世の様々な欲望と煩悩、正しい人間存在の発展を妨げるもの一切であった。「賢者の石」とは、神秘的変成によって姿を変えた人間であった。人間は錬金作業の素材そのものであり、鉛から黄金への変化は、人間が高次の理想に向かって意識を高めること、誰もが自分の内部に持っている祖型を実現させることであった。自然界の何ものにも冒されない「黄金」は、“完璧なるもの”“不死性”のシンボルであり、宇宙精神そのものを象徴していた。
このように、実際の物質的黄金ではなく、人間の精神の変成(純化)を目指した本来の錬金術を「神秘錬金術」と呼ぶ。
■アラビアの最も偉大な錬金術師ゲベルの言葉
アラビアの最も偉大な錬金術師ゲベルによれば、真正の術者は化学についての正しい知識をもっているだけでなく、意志堅固で、根気強く、忍耐力に富み、温和で、敬虔で、誠実で、晴れやかな表情をたたえ、快活な心をもっていなくてはならないのだ。
「作業を行う者は自分の仕事と同じ高みに立たなければならない。すなわち、自分が物質に期待するのと同じ過程を、自分自身の内において実現しなければならない」
低次の金属を高次の黄金に変えていくという物質変容の過程は、獣性をもって生まれてきた人間が霊性に目覚めていく魂の精鍛・錬磨の過程と同一である。とすれば、錬金術を行おうとする者は、それだけの心構えを要求されるのは当然だ。
だから、ゲベルによれば、「権力や富に食欲な人間、うぬぼれの強い人間、優柔不断な人間、そして全ての心悪しき人間には、錬金術の秘密が明かされることは決してない」のである。
中世およびルネサンスの王侯貴族の中には、錬金術に傾倒した人々が多くいたが、彼らの工房は実験と祈りの場でもあったのだ。
■東洋の錬金術
以上見てきたように、錬金術の真の目的は「人工の黄金」をつくりだすことではなかったといえよう。黄金を生み出す術というのは、錬金術のほんの側面を表しているにすぎず、その本質は、人間の精神と肉体の練成法を示したものであり、人間をより高次の存在にまで高めることを目的としていたといえるのだ。
事実、錬金術に用いられていた術語は比喩的な意味を持ち、神秘思想に精通した錬金術師たちが目指したのは物質的黄金の探求ではなく、魂の浄化であり、精神を徐々に変容させることにあったのである。
当然、このような「神秘錬金術」の思想は東洋にも古くから存在していた。
中国の錬金術師たちは、彼らの流儀の錬金術によって得られた錬金術的金「丹金」(西洋錬金術のいう「哲学者の金」)は、生命を無限に伸ばすと考えていた。錬金術の変成のプロセスによってつくられた黄金は、より高度な生命力をもっており、人はそれによって不死を達成することができると考えていた。
インドの錬金術はハタ・ヨーガの一部だが、その最高の達成を「殺された水銀」と呼ぶ。この賢者の石に比すべき物質も、水銀を黄金に変える力のほかに、さまざまな力をもっているとされた。たとえば、それを薬として飲むことによって、術者は中空を飛行することや、不可視になることができると考えられた。そして、若さを無限に延長すること、ついには“生きながら解放されたもの”になることも可能だと考えられた。つまり、超人化だ。
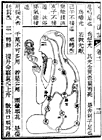
仙道書に書かれた修行法
(小周天と大周天)
■真の錬金術は「自己」の完成を目指す技術である
中国でもインドでも、錬金術師たちは賢者の石や哲学者の金によって、自らを純化して神に近づくこと~人間の神性回復~を目指したのである。錬金術についての莫大な研究を残したユングの言葉を借りれば、錬金術師たちは「意識を変容して神のような状態になること、究極的な個体へと変わるための鍵」を賢者の石に求めたわけだ。
このように、錬金術の核心部分には“本質的なもの”への回帰を願う超人思想~意識変容の術があったと考えることができるのである。
優れた錬金術師たちが「真の目的は錬金術師自身の変質であり、より高い崇高な意識状態に達することである」といっているのは、まさにこのことなのである。
■■第3章:「アーサー王伝説」に隠された錬金術の修行階梯
■15世紀に集大成された騎士物語「アーサー王伝説」
ヨーロッパにおける神秘学の精髄をもっとも端的に表した伝説といえば、「アーサー王伝説」をおいてほかにはない。そこに語られている数々の試練や聖杯、聖剣などのアイテムには、どれにも明確な意味が与えられ、心ある者がこの物語をひもとけば、知らず知らずに錬金術の奥義をマスターし、覚醒を遂げることができるのである。
そうした密義を満載したアーサー王の原伝承は、かなり古くから民衆の間に語り継がれていたと考えられるが、文学としてまとまるのはジェフリー・オブ・モンマスの『ブリタニア列王記』に採録される13世紀頃までで、このときにほぼ現在のかたちとなり、15世紀トーマス・マロニーによって集大成された。
アーサー王とは、5~6世紀頃にイギリスに実在したとされる伝説の人物で、様々な部族国家を再統合し、サクソン族の侵入を阻止した英雄とされているが、物語はこうした史実に基づく王とは別に進行する。
そこに描かれる騎士物語は、ケルト神話、特にウェールズ地方の物語をべースに、キリスト教によって埋没させられた古代神の失われた面影、キリスト教神秘主義、魔術、奇跡、そして、人間社会と異界とをつなぐ妖精たちや魔怪、様々な錬金術の呪術を駆使する魔法使いらがふんだんに登場することで、ヨーロッパの闇の精神思想史の様相を呈している。
その中心的なテーマとなっているのが、中世に花開いた神秘学や神学、哲学などの重層的な意味づけだった。
■「聖剣」と「聖杯」の融合が意味するもの
アーサー王物語の骨子は、王自身の受胎と誕生、結婚と、それを取り囲む円卓の騎士たちの様々な試練(修道の階梯)や、魔術師で予言者でもあるマーリンの秘儀を通じて最終的にたどり着くであろう至高の境地の獲得なのである。
その具体的な到達点が聖剣と聖杯(ケルトの大釜神話が原型)との融合である。すなわち「聖剣」は男性原理を表し、キリストの血を受け、最後の晩餐にも使われたとされる「聖杯」は子宮である女性原理を表している。
この融合により、錬金術の奥義「アルス・マグナ」に到達した騎士(修道者)は、この世のすべての束縛から解放され、心身ともに純化され、覚醒を遂げ、神と比肩する存在に昇華することで自己救済を完了させる。これこそが、黄金の生成(魂の覚醒)の持つ真の意味なのである。

「聖杯」は「アーサー王伝説」の中で、
騎士たちが探し求める「聖遺物」である。
「聖杯」はヨーロッパ精神史の隠れた
核であるといわれている。
ちなみに「アーサー王伝説」でこの聖杯の探究を成功させるのは、ガラハッドを頂点とするパルジファル、ボウルズの3人で、これはそのまま3つの悟りの階梯を表現している。物語では、真実の聖杯(真理を体得することで得た覚醒の境地)に到達したガラハッドの魂は、聖なるものを見つめたために激しく震え、目的を達した喜びのなかで昇天し、神に比肩する存在にまで昇華される。そして、後に残されたパルジファルは瞑想と信仰の隠者となり、ボウルズはアーサー王のもとへ帰還していくのだった。
「アーサー王伝説」とはまさに、騎士物語に仮託して、錬金術の修道階梯を明らかにした教導書といえるだろう。
■■第4章:ヘルメス思想の全体像
■宇宙の創造(流出)と螺旋運動による回帰(進化)
ここで、簡単にヘルメス思想の全体像を紹介しておきたい。
ヘルメス思想においては、本来は霊的な存在であるはずの人間が物質界に下降し、そこで認識を得て再び神界に復帰する、という往還運動をとりわけ重視する。それはつまり、ヘルメス思想における進化とは、まっすぐでやみくもな直線運動ではなく、ときに後退とも見える運動を経ながら、より高次の存在をめざしていく螺旋運動にほかならないことを意味している。
ヘルメスの持ち物である「ヘルメスの杖(カドゥケウス)」にも、そのことは、はっきりと示されていよう。人間の霊的進化の経路を表象するあの杖には、中央の軸の周囲に、上昇と下降を示す2匹の螺旋状の蛇が示されている。これは錬金術の過程を象徴的に表したもので、進化はそのように行われるのである。
また、ヘルメスによれば、「目に見える世界が形づくられる前に、その雛型がつくられた。この雛型は『原型』と呼ばれ、創造の過程が始まるずっと以前に『最高の精神』の中にあった」のである。その原型を眺めているうちに、“最高の精神”はある考えに魅せられてしまった。そこで太古の空間に洞窟を掘り、“原型的な”鋳型の中に球の形をつくったのだ。そして、これが“宇宙”の始まりなのである。
わかりやすく言いかえれば、“神は天上界の原像をもとにして、その模造を地上の物資界に流出せしめた”ということだ。とすれば、この下降運動を、下位の物質を手がかりにして、再び天上的なものへと到達するための上昇運動に変成することも可能なはずである。『エメラルド・タブレット』によれば、“上なるものは下なるものに一致し、下なるものは上なるものに対応する”からだ。
その上昇運動の実現を目指すのが錬金術の究極の目的であり、その鍵を握るのが「賢者の石」なのである。つまり、錬金術の究極的に目指すものは“模造”であるこの世界を、人間存在そのものとともに“最高の精神”の高みにまで引き上げることなのだ。

螺旋状にからみ合う蛇は「ヘルメスの杖」
のシンボルであり、上昇と下降という
ヘルメス学の中心概念を表す。
■創造主と被造物は本質的に同一物
ヘルメス思想においては、人間と神は本質的に同一なのであるから、そのことを「認識(グノーシス)」しさえすれば、人間を神のレベルにまで高めることができると説く。「神化、これこそがグノーシスを有する人々のための善き終極である」のだ。
逆にいえば、本来は神的な存在である人間が物資界に下降し、また再び神のレベルに上昇するという「運動」自体に計り知れない価値があるとし、これを評価する。すなわち下降や堕落に積極的な意義を見出す。これは正統キリスト教にはありえない思想である。
キリスト教においては、教義の絶対性を強調するため、神はあらゆるものに隔絶して存在する絶対者として規定されている。したがって神は、自分自身とは無関係なところで、絶対無から宇宙を創造し、人間は本質的に死すべきものであり、生まれながらに原罪を背負い、死後は裁きにあうと説く。キリスト教は、神(創造主)と宇宙(被造物)は全く別物であり、人間と神は全く乖離した存在であると主張しているのだ。
ヘルメス思想においては、創造主と被造物は本質的に同一物であり、同じ一者の異なる現れにすぎない。「全は一であり、一は全である」のだ。そして、下のものと上のもの、小宇宙と大宇宙が本質的に同一であり、互いに照応し合っていると考える。
大宇宙(外界)は小宇宙(人間)を包んでいる。だが、この大宇宙はまた、光の世界に包まれてもいる。光の世界とは霊の世界、すなわち人間の内的世界であって、ここに、内なる世界が外なる世界を包み込む、という入れ子構造が見られるのである。

↑ウロボロスの環
この図は「宇宙」や「永遠」を意味し、
世界(宇宙)が終わりなき「円環運動」を
続けていることを象徴している。
以上、簡単にヘルメス思想の全体像を紹介してみたが、なかなか面白い「宇宙思想」であることが分かるだろう。実際、このヘルメス思想は古くから多くの知識人を魅了してきた。特にこのヘルメス思想がヨーロッパの知識人によって“再発見”され、キリスト教社会に多大な影響を与えた時代があった。いわゆるルネサンスの時代である。
※ このルネサンスとヘルメス思想の関係については、
こちらのファイルで詳しく触れたいと思う。