| ヘブライの館2|総合案内所|休憩室 |
No.a2f1001
作成 1997.1
★去年(1996年)の9月初頭に、アメリカは1発4億円の「トマホーク・ミサイル」を44発も発射して、イラク攻撃を強行したわけですが、この事件はまだ皆様の記憶に新しいと思います。
結果的に、アメリカの行為は国際的な支持を得られず、フランス・ロシア・アラブ諸国などから強い非難を浴びていたのが印象的でした。
★この事件は未だに「湾岸戦争」当時の緊張関係が中東全体でくすぶり続けていたことを、我々に再認識させてくれたのですが、パレスチナ紛争と違って、「湾岸戦争」はもはや“民族や宗教”といった対立より、“利権”の悪臭のほうが遥かに強く漂っています。紛争の歴史には、その裏に必ず、人々を戦いに駆り出す利権争いと、そこで死体を見ながら札束を数える軍需産業の介在があったわけですが、現在、ますますその傾向は水面下でエスカレートしていると言えます。
そのため、表の動きだけを追っていると、どうしても紛争の真相が読み取れません。
★この記事はネット・ニュースにポストしたものです。(ところどころ私の主観が混じり込んでいますが、お許しを)。
──「湾岸戦争」の舞台裏・上 ──
●そもそも「イラン・イラク戦争」当時、双方の軍拡政策に手を貸して、イラクを世界第4位の軍事国家に仕立て上げたのは、アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、ソ連などなどの、湾岸戦争の中核を成した多国籍軍であった。
そして国連(United Nations/連合国)そのものであった。
●“ホメイニ革命”の中東への波及阻止という大義名分を掲げながら、これらの国々は膨大な兵器をイラク・イラン双方にタレ流して荒稼ぎしていたわけだ(アメリカは宿敵イランにも兵器を売っていたのだ/イランゲート事件)。
この狂気のビジネスマン(死の商人)たちが火に油を注いだおかげで、「イラン・イラク戦争(イライラ戦争)」は長期化したわけだが、イラン・イラク双方の死傷者は、合計100万人を下らないという。
ちなみに、この“イラ・イラ戦争”が続いていた1985年に、クウェートの貨物船はイラクのフセイン向けに武器を輸送していた。
●湾岸戦争直前のフセインに資金を送り続けていたのはイタリアの「国立労働銀行」であり、化学兵器を造らせてきたのはドイツやソ連であり、原子炉と濃縮ウランは堂々とフランスから売却され、恐怖のスーパー・ガンはイギリスから正式に輸出され、地下秘密基地を建設したのはイギリスとベルギーであり、アメリカは軍事用スーパーコンピュータを与えていた。
この件についての詳細を知りたい方は、ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の報告をまとめた『1985—89版年鑑』(東海大学出版会)などを参考にするといいと思われる。1991年2月5日付の『朝日新聞』が、世界各国のイラクへの武器輸出状況を「兄弟兵器」という題名で特集しているが、この特集だけでもかなり具体的なデータが得られる。
●また、アメリカは、フセインがクウェートに侵攻する1カ月前まで、フセインに対して農務省を通じて莫大な支援を行っていたことが1992年2月23日付の『ロサンゼルス・タイムズ』によってスッパ抜かれている。
同紙によると、援助はアメリカ農産品購入に伴う信用供与で、政権内部の「イラクの軍備増強につながる」との反対論にもかかわらず、“イランとの軍事バランス維持のため”などの観点から正当化されたという。
また同紙は、国家安全保障会議の内部議事録を引用し、ブッシュ大統領の側近が90年春ごろまでにイラクが核兵器開発を進めているとの情報をつかんでいたにもかかわらず、「イラクが汎用技術を購入できるようにすべきだ」などと主張。さらに「大統領は特にイラクだけを軍事大国として警戒することを望んでいない」などと述べていたことを暴露している。
●また『ニューヨーク・タイムズ』も、イラクは1983年からアメリカ農務省を通じての援助を受けており、1989年には年間10億ドル強の規模に達し、フセインはそれを武器購入に当てていたが、アメリカ政府がそれを黙認し続けていたことを報じている。
◆
●フランス人ピエール・ジョックスやマルセル・ダッソーという“死の商人”は大量の爆撃機「ミラージュ」をイラクに売り込み、フセインはその見返りにイラクの石油をフランスの国営石油会社「エルフ・アキテーヌ」などに優先的に販売する取引を行ってきたが、イラクのクウェート侵攻はこのミラージュによって行われ、迎撃したクウェートの戦闘機も同じミラージュであった。ちなみにピエール・ジョックスは、湾岸戦争時に、自らフランス国防大臣の座につき、残忍な陸上戦の強行を主張し、実行に移していた。
また、ミッテラン仏大統領はブレゲ一族であるから、「ダッソー・ブレゲ社」のミラージュを販売した背景と犯罪はあまりに露骨であった。湾岸戦争直前のフセインは、フランスに30億ドルという巨額の武器購入のための借金を取り立てられる立場にあり、あやつり人形になっていた。クウェート侵攻直後のフセインが、フランス人捕虜を特別措置としていち早く解放するという謎の行動に出たのは、こういう背景があったためである。
●また、「スカッド・ミサイル」が一躍有名になったが、実際の主力ミサイルはスカッドではなく、これもフランス製である軍艦攻撃用「エグゾセ・ミサイル」であった。しかも、このミサイルはミッテランの弟ジャックが総裁を務めた「アエロスパシャル社」の製品であった。ミッテランは国連で中東和平のための提案を行っていたが、厚顔無恥ここに極まれりといったところか。
◆
●湾岸戦争の直接のきっかけは、1990年7月17日に、イラクがクウェートとアラブ首長国連邦に対して、石油価格の値上げに同調しないことを非難し、「直接行動も辞さない」と宣言したことに起因しているが、イラクの不審な動きに不安を感じたクウェートが、アメリカ政府にそのことを打診したところ、返ってきた返事が「イラクの動静に心配はない」という内容であったという。
しかし、状況を重く見た特権階級のクウェート人は、1990年7月23日に、イラクが二個師団をクウェート国境に差し向けた時、既に財産ともども国外へ脱出していたのであった。
また、中東全体に情報網を張り巡らしているイスラエル共和国の国防相モシュ・アレンスは、アメリカのチェイニー国防長官に対して、イラクによるクウェート侵攻を警告していたが、チェイニーはこれを無視していた。
●しかも、軍事偵察衛星から送られてくる写真から、米ソはイラクがクウェートに攻め込む何日も前から、フセインの軍隊の大規模な移動と、クウェート国境への集結を確実に把握していたことが、関係者の証言で明らかになっている。
中でも、1990年7月20日に打ち上げられたソ連製スパイ衛星「コスモス2086」が、突然軌道を変え、侵攻直前のクウェート上空を集中的に飛行していたことが、徳島市の「民間・人工衛星追跡組織(LAT)」の調査によって明らかにされている。
この件については、1990年10月23日付の『朝日新聞』によっても報じられていたが、軍事評論家らによると、レーダーや望遠鏡で他国の衛星の位置を確認しているアメリカなどが、このソ連衛星の動きを察知していたのは確実で、“奇襲”とされるイラク軍の侵攻を軍事大国が事前に知っていた可能性が強いとしている。
◆
●イラクの不穏な動きは上空に根を張っているスパイ衛星群や、周辺国でもキャッチされていたわけだが、本来ならこの時点で、アメリカが第七艦隊をペルシア湾へ向かわせ、イラクへ警告を発していれば、湾岸戦争は回避されていたと言われている。しかし、アメリカは見て見ぬふりをした。明らかにアメリカはイラクに開戦させたかったといえる。
そして、その決定打となったのが当時のイラク駐在のグラスピーというアメリカ女性大使が、フセインの国家再建努力を褒めちぎりながら語った「アメリカはイラクの行動には関心がない」という甘い誘い文句であった。この7月25日の時点で、既にイラクが10万の兵力、3500両の戦車、1000台の装甲車をクウェート国境に張り付けていたにもかかわらずである!
●そしてそれに拍車をかけるようにして、ジョン・ケリー国務次官補が記者会見において「クウェートが攻撃されてもアメリカにはクウェートを助ける責任がない」と公言していた。彼は国務省の中東のエキスパートである。彼の発言はひときわ重く響いた。
かくして、1990年8月2日、イラクのサダム・フセインはアメリカの甘い罠にまんまとはまり、安心してクウェートに侵攻したため、湾岸危機が発生したわけだ。
◆
●イラクのクウェート侵攻当日、ベーカー国務長官はソ連のイルクーツクでシェワルナゼ外相と米ソ外相会談をしながら、仲良く魚釣りに興じていた。そしてイラク侵攻の報告に、米ソ外相2人は、いかにも驚いたふうに「これは遺憾である」などと共同声明を発し、フセインのクウェート侵攻が予期せぬ唐突な事態であったことを世界にアピールした。
そしてこの日を境にしてアメリカ政府は、それまで見せ続けていた無関心な態度とは打って変わって、待ってましたとばかりにイラクを強く非難する強硬姿勢に転じ、各国の支持を得るための活発な外交活動を展開。そして、またたく間に世界28ヶ国の軍隊を寄せ集めたアメリカ軍主導の“多国籍軍”なる代物を生み出すことに成功したのである。
●この一連のパターンは、真珠湾攻撃を様々な方面で事前にキャッチしておきながら黙認し、日本に先に手を出させて国際的な“大義名分”を得た、当時のアメリカ政府のしたたかさを思い起こさせる。(真珠湾攻撃の真相は専門家によって明らかにされつつあるが、だからといって日本の軍事行動が全面的に正当化されることはないだろう)
●そもそも湾岸戦争直前のイラクは、長期にわたって続けられた対イラン戦争に10兆円以上もの軍事費を投資したことや、石油の世界的ダブつきが原因で、既に国家財政が破綻していたわけだが、イランとの戦争でバランスが保たれながら肥大化していたイラク軍の後処理問題が残されていたわけだ。好戦的なフセインが、イランに向けていた矛先を宿敵イスラエルに変えて、新たな軍事行動を展開する危険が大であった。イラクの軍事力を放置することは、そのまま中東全体が火の海になる危険性を放置することに等しかった。
そのため先進諸国は、窮地に立たされていたフセインが勝手な暴走を開始する前に、自らの手で膨らませてきたイラクの軍事力を、自らの手で始末(ガス抜き)する必要が生じ、そのための手として、クウェートが一時的な犠牲(エサ)にされたと私は見ている。
◆
●イラク軍がクウェートへ侵攻を開始すると、アメリカ、イギリス、フランスなどの旧植民地主義の国々は“人道主義”の名を掲げて、イラクを非難し始めたわけだが、未だに自由を保障しない「封建国家クウェート」の解放を唱えること自体に、西側諸国の“偽善”が存在していた。
ちょっと調べれば分かると思うが、クウェートは民主国家ではなく「サバーハ家」による首長制国家である。しかも醜聞が多く、現地での評判がすこぶる悪いファミリーである。そのため、石油成金で財テク野郎のジャビル国王が、イラク軍にビビッて、サウジアラビアに脱出したとき、アラブの民衆たちはサダム・フセインに喝采を浴びせ、大いに溜飲を下げたという。
それほどまで、クウェート国王はアラブの世界では鼻つまみ者だったのである。
●また、アメリカは湾岸戦争のとき、サウジアラビアにベトナム戦争以来最大の20万の兵力を送り込み、現在に至るまでそのまま居座っているのだが、このサウジアラビアという国も民主国家とは程遠い王制国家である。アメリカはイラクを“非民主国家”だと強く非難していたが、クウェートやサウジアラビアのみならず、オマーン、カタール、バーレーンなどの中東の湾岸王制諸国を“民主主義の敵”として非難することは決してない。なぜならば、アメリカの利益と国王の利益が一致しているためである。
そのため、クウェートのジャビル国王による実質的な専制政治は湾岸戦争以後も変わらず、貧富の差はますます広がる一方である。
◆
●ところで、あまり話題にされることのない事柄だが、イラク南部に位置する親米国家サウジアラビアには、アメリカによって作られた軍事秘密都市が3ヶ所ある。ヨルダン国境に面した「タブーク」、イエメン国境にある「カミス・ムシャイド」、イラクとクウェート国境に接した「アル・バティン」である。
それで、今回の湾岸戦争で注目されているのは「アル・バティン」なのであるが、この軍事秘密都市はサウジ北東部(イラク・クウェート国境)からのイラク軍の突然の侵攻に備えるために、わざわざ緊急かつ隠密裏に、アメリカが1985年に建設したばかりのものである。
フセインがクウェート侵攻1週間前にイラク軍を移動させたイラク南端地域は、この出来たてホヤホヤの軍事秘密都市「アル・バティン」の警戒エリアそのものであった。アメリカは厳重な報道管制を敷くことによって、この軍事秘密都市の存在そのものを世界の一般大衆の目から隠すことに成功していたわけだが、この軍事秘密都市の警戒エリア内に堂々と移動して来たイラク軍の動静について、アメリカ軍部は分かりすぎるほど分かっていたといえよう。
●この件について、昭和経済研究所アラブ調査室長で東京国際大学教授の渥美堅持氏は、以下のような見解を示している。
「アメリカは常々、フセインの軍事戦略を危険視していた。アメリカ女性大使とフセインの交渉には不可解な部分が多い。〈中略〉アメリカはサウジのアル・バティン軍事都市を使いたがっていたはずだ。基地というものは使わなければ意味がない。そしてサウジ国民各層の動揺ぶりも知りたかった。〈中略〉湾岸戦争はアメリカが自国の権益を守るために仕組んだ戦争といえる」
◆
●で、結局、湾岸戦争で一番得をしたのは、誰か?
それは「軍産複合体」と呼ばれる軍事兵器企業群である。湾岸戦争前、軍産複合体は“冷戦終結”のせいでレイオフに次ぐレイオフを続けていた。全米で1位と2位の軍事企業「マクダネル・ダクラス社」と「ゼネラル・ダイナミックス」の両社は、国防総省が「倒産」を口にするほど危機に陥っていたのだ。
それが、湾岸戦争のおかげでそれまでの「軍縮ムード」が一気にブッ飛び、危機に陥っていたはずの軍産複合体は莫大な暴利を手にし、救済され、息を吹き返したのである。
●アメリカにある民間軍事研究機関「ディフェンス・バジェット・プロジェクト」による推計によると、「砂漠の嵐作戦」で中東に展開したミサイル、戦車、ヘリコプター、戦闘機といった陸・空の主要兵器だけで総額は約2740億ドル(約36兆1680億円)にのぼり、各兵器企業の儲けは以下に記すように、莫大な金額を計上していたのである。
(当時1ドル=130円)
●ゼネラル・ダイナミックス社は、巡航ミサイル「トマホーク」で1.7億ドル、「F16戦闘爆撃機」で21.1億ドル、「M1戦車」で3.4億ドルの儲けを上げた。
マクダネル・ダクラス社は、「F15E戦闘爆撃機」で47.6億ドル、「F/A18ホーネット」で40.3億ドル、「A−H64アパッチヘリ」で11.1億ドルの儲けを上げた。
グラマン社は「F14戦闘機」で58億ドル、「A6攻撃機」で42.4億ドルの儲けを上げた。
レイセオン社は湾岸戦争で一躍注目を浴びた地対空ミサイル「パトリオット」で1.4億ドルもの儲けを上げた。
ロッキード社は初めて実戦参加させた「F117ステルス爆撃機」だけで、なんと130億ドル(1.7兆円)もの荒稼ぎをしていた!
◆
●兵器産業に負けず、石油メジャーもボロ儲けである。
イラクのクウェート侵攻によって、OPECは分裂状態となり、その結束力は急激に弱体化。必然的に、アメリカおよびメジャーの石油価格に対する統制力は大幅に回復したのである。そして原油価格の高騰により、1990年末の四半期で、アメリカ大手石油18社の純益は前年の250%という途方もない額に達し、最終的に、有史以来の大儲けを記録し、テキサスなどの国内石油も採算ベースに乗ったほどであった!
●ところで“テキサス”と言えば、湾岸危機・湾岸戦争を含め、ブッシュ政権の外交政策のほとんどを立てていたベーカー国務長官は、テキサスに大きな影響力を持つベーカー=ロヴェット=ブラウン兄弟一族の出身で、この一族は世界的なマーチャント・バンカーとして有名であり、また、テキサスの石油成金ブッシュ・ファミリーと同じ事業に参加してもいた。この石油成金のブッシュは大統領選の時にテキサコの資金援助を受けていたし、彼がテキサスに創立した「サパタ石油」は、クウェートから採掘してきた石油を扱う会社であった。
●このように、湾岸戦争に踏み切った、ブッシュとベーカーという、したたかなビジネスマン・コンビは、故郷テキサスの一族やアメリカの軍事産業界に莫大な恩恵をもたらしていたわけだ。いや、軍事企業や石油産業だけでなく、各種コンピュータ産業や、各種部品製造会社、医薬品業界、毒ガス用マスク製造会社から弾薬会社に至る全ての末端企業まで、大車輪でフル操業しても間に合わなかったといわれるほど、大儲けをしていた。
おまけに、その影響は戦争が終結した後も続き、アメリカ製の兵器は、それ以後世界最大の売れ行き高を示し、現在もアメリカの軍需産業は量産に量産を重ねながら、兵器輸出国のトップ状態を維持したままである。
◆
●さらに湾岸戦争後、ビジネスとして最大の焦点となったのは、破壊されたクウェートを復興するのに、一体どれほど金がかかるかということだった。それは実に約800億ドル、およそ10兆4000億円という試算さえ出されるほど巨大な事業だったが、このクウェート復興事業のほとんどは、世界最大のゼネコン「ベクテル社」をはじめとするアメリカの企業が受注し、残りをイギリスがさらっていった。
「ベクテル社」は年間売上4兆円を超す世界最大の企業でありながら、株式非公開で資産も公開しない“個人の会社”のため、日本ではあまり知名度は高くない。アメリカ政界に大きなコネを持っている「ベクテル社」の実態については、別の機会に詳しく触れたいと思う。
●現在、「ベクテル社」は湾岸戦争前から、ペルシャ湾岸に1997年の完成を目指して進行中の「アルジュベール工業都市建設」(投資額200億ドル)「リヤド国際空港建設」「ダーラン国際空港建設」などの、サウジアラビアにおける巨大プロジェクトを請け負っているのだが、サウジアラビアは昔から、欧米の多国籍企業が“利権”を争う場として、絶対にアラブ諸国の干渉を許すことのできない“聖域”に指定されていた。特に、サウジアラビアの特定のプロジェクトは、アメリカ企業に限定されており、サウジの肝心な部分はアメリカが押さえている状態にあった。
それを象徴するかのようにアメリカは、フセインがクウェートに侵攻するや否や、世界がびっくりするほどの電撃的な速さで、サウジに大量のアメリカ軍を派遣し、サウジ国民の困惑をよそにして、現在に至るまで駐留し続けている。現在、サウジ並びにサウジ周辺のペルシア湾に展開しているアメリカ軍は、サウジ国民のためというより、サウジにいるアメリカ企業(特にベクテル社)のための信頼厚き「守護神」としての役割を果たしていると言っても過言ではなかろう。
◆
●以上のように、フセインを一方的に“悪者”扱いした国際世論に押される形で、アメリカ経済全体が活性化されたわけだが、実に湾岸戦争はアメリカにとってメリットだらけであったことが、イヤというほど分かるだろう。
彼らは、中東を破壊し、中東を再建し、中東に莫大な負債をもたらすというパターンを繰り返すことで、自分たちの生活を保証してきたのである。
※ この続きは「湾岸戦争の舞台裏・下」へ続いております。


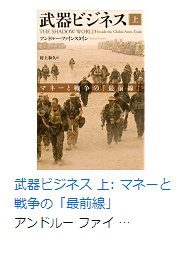

Copyright (C) THE HEXAGON. All Rights Reserved.