| ヘブライの館2|総合案内所|休憩室 |
No.a6fhb812
作成 2003.4
●中東問題の研究家である立山良司氏(防衛大学教授)は、ホロコーストをめぐる問題について、著書『揺れるユダヤ人国家』(文藝春秋)の中で興味深い指摘をしている。
参考までに紹介しておきたい。
立山良司(たてやま りょうじ)
1947年、東京生まれ。早稲田大学
政治経済学部政治学科卒。在イスラエル
日本大使館専門調査員、国連パレスチナ難民
救済事業機関職員、財団法人中東経済研究所
研究主幹などを経て、現在、防衛大学教授。
専攻は中東を中心とする国際関係論。
※ 以下の文章はこの本からの抜粋です
(各イメージ画像は当館が独自に追加)
■「石鹸」と呼ばれた生存者
1950年までに、イスラエルには約35万人のホロコースト生存者が移民してきた。ナチスの強制収容所でかろうじて生き延びたか、何らかの方法でナチスの手を逃れていた者たちだった。
その彼らをイスラエル社会は「弱さ」の象徴と見なした。〈中略〉
ホロコースト生存者たちは初めのころ、イスラエル生まれの若者たちに「サボン」と呼ばれた。「サボン」とはヘブライ語で「石鹸」を意味している。ガス室をシャワー室と偽り、死の直前の犠牲者に石鹸を配布したというナチスの行為を連想させる言葉だ。
イスラエルの作家アモス・エロンは「サボンという単語は次第に、臆病者とか意気地なしを意味するようになった。また、“石鹸で洗う”と動詞で使うと、相手を破滅するという意味合いを持った」と書いている。
一方、ほとんどのホロコースト生存者は、自分たちの忌まわしい経験について何も触れたくないし、何も語りたくないと考えていた。加えて、イスラエル社会にも生存者から真剣に話を聞こうとする雰囲気はなかった。
この結果、多くのホロコースト生存者は自らの経験についてかたくなに沈黙を守るようになった。また、一部の者はポーランド語やドイツ語風の名前をヘブライ語風に変えたり、腕に彫られた入れ墨を手術で消した。

アウシュヴィッツ収容所
■賛否両論だった賠償受け取り
こうした中、ドイツからの賠償問題がイスラエル社会を大きく揺るがした。西ドイツはイスラエルおよびユダヤ人関係組織と1952年、ルクセンブルク協定に調印し、イスラエルと個人の被害者に対する賠償が開始された。
戦後の混乱期、さらにはヨーロッパで東西対立が急速に激化した直後の再軍備期にあって、ホロコーストに対する賠償を支払うか否かはドイツ国内でも賛否両論を呼んだ。


一方、イスラエル国内でも賠償受け取りに対する激しい反対運動が起き、クネセト(イスラエル国会)の建物が反対デモに襲撃され警官隊が出動するなど、政治問題が暴力的な対立にまで発展した珍しいケースとなった。
反対運動の先頭に立ったのは右派政党ヘルート(後のリクード)党首メナヘム・ベギンだった。
ベギンは賠償交渉を推進したベングリオン首相に対し、「汚らわしい利益のためにイスラエル国民の尊厳を売り渡すのか?」、「ドイツ人は誰でも人殺しだ。それに対して金、金、金と計算するのか。これはわが民族に対する永遠の屈辱だ」
とセンセーショナルな演説で反対運動を煽った。

第6代イスラエル首相
メナヘム・ベギン
一方、イスラエル政府は何が何でもドイツからの賠償を必要としていた。
ベギンらの反対論に対し、ダヴィド・ベングリオン首相は「ドイツ人はユダヤ人に対し虐殺と略奪の限りを尽くし、今やその利益を享受している。わが民族を殺した者たちにそんな利益を享受させてはならない」と、やはり感情的な調子で反論した。

ダヴィド・ベングリオン
シオニズム運動の「建国強硬路線」をとる
彼の指導のもとに、ユダヤ人の独立国家をつくる
基盤は着々と準備された。イスラエル建国後に、
初代、並びに第3代イスラエル首相になる。
結局、イスラエルは国家として1966年までの14年間にわたり、総額30億マルク相当の物資を賠償として西ドイツから受け取った。
それらの物資はイスラエルがもっとも必要としていた石油をはじめ、鉄道や通信関連設備、重機械などであり、歴史家のハワード・サハールは「イスラエル経済のあらゆる分野が、ドイツからの物資流入で質的な転換を遂げた」と述べている。
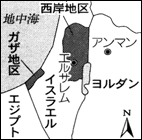

(左)イスラエル(パレスチナ地方)の地図 (右)イスラエルの国旗
※ ユダヤ人の国イスラエルは、戦後1948年5月に中東に誕生した
いずれにしても1950年代までのイスラエル社会では、ホロコーストをどう位置づけるか定まった見方はなかった。
ハイファ大学のイェハイム・ワイツが述べているように、すべてを政治化してしまうイスラエルでは「ホロコーストすら政治のプリズムを通して見ていた」のかもしれない。あるいはあまりにも傷跡が深すぎて、一定の公的な見方を示せなかったのかもしれない。
こうした状況を決定的に変えたのは、「アイヒマン裁判」だった。
■ハンナ・アーレントによる批判
ゲシュタポの「ユダヤ問題」担当責任者アドルフ・アイヒマンが、逃亡先のブエノスアイレスで捕らえられたのは1960年5月だった。
イスラエルの情報機関モサドによって拉致されたアイヒマンは、そのままイスラエルに連行された。それから約1年後の1961年4月に裁判は始まり、その年の12月に死刑判決が下された。
多くの傍聴人やジャーナリストを収容するため、裁判はエルサレム市内の劇場に特設された法廷で行われ、その模様はすべてラジオで生中継された。裁判の最中、イスラエル国民のほとんどすべてがラジオに縛り付けられたように聞き入り、通りには人影すらなかったという。


アドルフ・アイヒマンSS中佐
戦後、アイヒマンは南米アルゼンチンで
逃亡生活を送っていた。しかし、イスラエルの秘密情報機関
「モサド」の秘密工作チームによって1960年5月11日に誘拐・逮捕され、
イスラエルへ空輸された。この「アイヒマン拉致事件」は、イスラエル政府が
アルゼンチン政府に対して正式な外交的手続きを踏んだものではなかった。
そのため、アルゼンチン政府は「主権侵害」と猛抗議、大使召還、
国連提訴など、解決まで2ヶ月間もめた。


アイヒマンの裁判は世界注視の中で1961年4月11日にエルサレム地裁で始まった。
アイヒマンの座る被告席は、防弾ガラス張りになっていた。約8ヶ月の審理ののち同年12月15日に
死刑判決が下され(これはイスラエル唯一の死刑判決である)、翌年5月31日、絞首刑が執行された。
アイヒマンの死体は彼の希望通り火葬にされたが、遺骨はイスラエルの領海外の海中に投じられた。
「アイヒマン裁判」で弁護側が争った一つの問題は、イスラエルにアイヒマンを裁く権利があるのかという点だった。
これについて判決は「何百万人というユダヤ人を殺戮したナチスの犯罪は、(ホロコースト)生存者のための国家が樹立される主要な原因の一つであった。それ故、ホロコーストの根元と当該国家(イスラエル)を切り離すことはできない」と述べ、ホロコーストとイスラエルとの間には連続性があり、それ故に裁判を行う正当性があるとの判断を示した。
アイヒマンは上告したが却下され、刑は1962年5月に執行された。遺体は焼かれ、灰は地中海に棄てられた。
◆
米誌『ニューヨーカー』の特派員として裁判を取材したハンナ・アーレントは、「アイヒマン裁判」を「ベングリオンが演出したショーだった」と厳しく批判した。


(左)ユダヤ人政治思想家ハンナ・アーレント
(右)彼女の著書『イェルサレムのアイヒマン ─
悪の陳腐さについての報告』(みすず書房)
アーレントによれば、ベングリオンは裁判で次のような「教訓」を世界やイスラエル国民に伝えようとした。
第一に非ユダヤ人世界は、「たまたまユダヤ人だった」ことを理由に殺されたという事実を認識し、そのことを恥としなければならない。
第二にディアスポラ・ユダヤ人は、イスラエルの建国によって初めて、ユダヤ人が「羊のように無抵抗で殺される」ことなく防衛のためには反撃する民族になったという事実を銘記しなければならない。第三にイスラエルの若いユダヤ人は、ユダヤ人に対し何が起きたかを知り、記憶することで、ユダヤ人としての意識を保たなければならない。
つまりアーレントから見れば、「アイヒマン裁判」はこうした教訓を伝えることでシオニズムのイデオロギーを語る舞台としての役割を担い、ベングリオンはそのための演出家だったのである。
後に『イェルサレムのアイヒマン』という一冊の本にまとめられた彼女の批判は、多くの反批判を招いた。特にそのトーン──加藤典洋氏がいうところの「語り口」──はユダヤ人の間に激しい反発を引き起こした。
しかし、「アイヒマン裁判」がイスラエルのユダヤ人、さらにはディアスポラ・ユダヤ人に与えた影響は、ユダヤ人意識を強化したという点において、まさにアーレントが指摘したようにベングリオンの意図通りとなった。
■「英雄物語」とセットで
「イスラエル人が自分達とホロコーストをどう関係づけるかという点で、『アイヒマン裁判』は劇的な変化の始まりとなった。深い沈黙を破って語られた恐怖の話を聞くことによって、イスラエル人は自分達をホロコースト犠牲者や生存者と結びつけた」
とトム・セゲブが述べているように、「アイヒマン裁判」はイスラエルにおけるホロコースト認識に転換点をもたらした。
裁判直後にヘブライ大学の学生を対象に行われた裁判の影響に関する調査結果によると、身内が何らかの形でホロコーストの犠牲になった学生も、何の関係もない学生も一様に、悲観的な世界観を持つようになり、その中心にホロコーストを位置づけるようになった。また、誰もが自分自身を「ホロコーストの生き残り」と見なし、ユダヤ人としての連帯感を強めたという。
かくして1960年代以降、ホロコーストの記憶はユダヤ人ないしイスラエルの国民意識を形成する重要な市民宗教の柱となった。エルサレムにある「ヤド・バシェム(ホロコースト博物館)」にはいつも大勢の中学生や高校生、若い兵隊が見学に訪れ、ホロコーストの記憶を新たにしている。
ほとんどがホロコーストと直接関係を持っていないオリエント系ユダヤ人の間でも、自らをホロコーストに結びつけて自己規定する傾向が強まっている。
◆
学校教育においてもホロコーストが取り上げられるようになった。
1980年代前半にイスラエルの公立幼稚園、小学校に通った私(立山)の娘が最初のころに覚えたヘブライ語の単語の一つは「ナツィ(ナチス)」だった。また、小学校の国語(つまりヘブライ語)の教科書にはホロコーストや強制収容所の話が、鉄条網の挿し絵とともに必ず登場した。
大変興味深いのは、教科書で扱われるホロコーストの話は、そうした苦しみの中にあっても自分を犠牲にしてまで何とかほかの人を助けようとする勇気ある子供たちの「英雄物語」とセットで登場することだ。例えば、夜中、勇敢にも強制収容所から抜け出し、ほかの人のために食料を手に入れてくる子供たちの話などだ。
この点に関連しイスラエルの社会学者S・N・アイゼンシュタットは、ホロコーストは二つのメカニズムを通じて、シオニズムおよびイスラエルという国家に正統性を提供していると説明している。
一方で、多数の無力なユダヤ人が殺戮されたという事実は、ユダヤ人が拠点となり、かつホロコースト生存者を保護する場所として自分たちの国を持つべきだというシオニズムの基本的な前提を正当化する。他方で、1943年に起きたナチスに対するワルシャワ・ゲットーでの武装蜂起のようなホロコーストにおける英雄的な行為は、シオニズムあるいはイスラエル建国後のヒロイズムの前史と見なされ、それによってシオニズムはユダヤ人の過去と歴史上の連続性を獲得したという。
このように見るならば、ホロコースト記念日の正式名称が「ホロコーストの殉教者、および英雄を記念する日」であるように、ホロコーストの悲劇とそれにかかわる「英雄物語」はつねにセットで提示されなければならないのである。
■「普通」と「特殊」のジレンマ
かくして「アイヒマン裁判」とその後のイスラエルにおけるホロコースト体験の重視は、ユダヤ人ないしイスラエル国民としてのアイデンティティに強固な基盤を提供してきた。
しかし、ホロコースト体験に基づくアイデンティティ確立の試みは、「普通」か「特殊」かというシオニズムの根底にある矛盾をそのまま抱え込んでいる。テオドール・ヘルツルらシオニズム主流派の先駆者たちがシオニズム運動に託したのは、ユダヤ人が「普通の国家」を持ち「普通の民」になることだった。
しかし、アーレントが指摘しているように、「アイヒマン裁判」以降のイスラエルにおける「ユダヤ人意識」の形成は「ユダヤ人と非ユダヤ人という二分法」に依拠しているのであり、結局「ユダヤ人は特殊だ」と宣言することになる。
こうした国家によるホロコースト体験の強調は、安全保障面ではB・キマーリングがいうような「シビリアン・ミリタリズム」、つまり文民が軍を統制しているが、軍事的な思考や「国家安全保障」という概念が政治や経済、イデオロギーなどのすべてに優先する状況を生みだしてきた。

さらにイスラエルのコラムニスト、ボアス・エプロンが指摘しているように
一部では「他の民族との関係において、ユダヤ人を守るためには何をしても構わない」という思考にまでエスカレートした。
その極端な例は過激な大イスラエル主義者の主張である。
彼らは「エレツ・イスラエル(イスラエルの地)」を絶対視する大イスラエル主義のイデオロギーと、ユダヤ人と非ユダヤ人という二項対立的な世界観を重ね合わせ、占領地からの撤退を阻止するためであれば非ユダヤ人に対するテロ行為も許されると考えている。
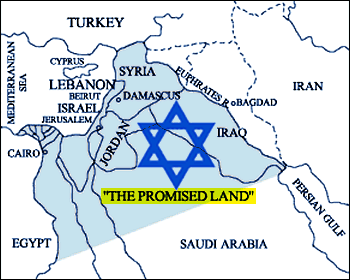
↑「大イスラエル」の完成予想図
シオニスト強硬派は、ナイル川からユーフラテス川
までの領域を「神に約束された自分たちの土地だ」と主張し
続けている(これは「大イスラエル主義」と呼ばれている)。
いずれ、イラクやシリア、ヨルダンなどのアラブ諸国は
シオニズム信奉者たち(アメリカ軍含む)によって
破壊(解体)される可能性が高い…。
イスラエル生まれでドイツ・イスラエル関係史を専門としているミヒャエル・ヴォルフゾーンは、「彼ら(ユダヤ人)はユダヤ教と切り離されてしまった自分のアイデンティティを民族の歴史を通じてふたたびユダヤ化するために、ホロコーストにしがみつかねばならない。そのために彼らは、とりわけホロコーストというカインのしるしのついたドイツを必要とするのである」と述べ、「ドイツがユダヤ人に縛られているのと同様に、ユダヤ人もドイツに縛りつけられている」と論じている(『ホロコーストの罪と罰』)。
このヴォルフゾーンの議論はユダヤ人、特にイスラエル・ユダヤ人のアイデンティティ問題をあまりにも単純化しすぎているように思われるが、一定の核心をついていることは確かだ。
今後、アイデンティティのパッチワーク化がさらに進行する中で、ホロコースト体験はこれまで以上に国民統合のシンボルとしての役割を担っていくのだろうか。
※ 以上、立山良司著『揺れるユダヤ人国家』(文藝春秋)より

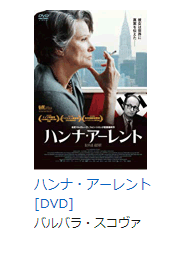


Copyright (C) THE HEXAGON. All Rights Reserved.