| ヘブライの館2|総合案内所|休憩室 |
No.a4fhc414
作成 2003.5
●多数のベストセラーで有名な渡部昇一氏(上智大学名誉教授)は、著書『まさしく歴史は繰りかえす ~今こそ「歴史の鉄則」に学ぶとき~』(クレスト社)の中で、ユダヤ人について詳しく論じている。
少し長くなるが参考までに抜粋しておきたい。

『まさしく歴史は繰りかえす
~今こそ「歴史の鉄則」に学ぶとき~』
渡部昇一著(クレスト社)
※ 以下の文章はこの本からの抜粋した
ものです(P65~67、76~79、83~103、
111、112、118、121~125、130~133)
※ 各イメージ画像とキャプションは当館が独自に追加
■■Part-1
■「ユダヤ化」こそ、明日を読むキーワード
「現代の自由主義経済はグローバル化、ボーダレス化の方向に向かっている。これからの日本も規制緩和と行政改革によって、この大競争時代に勝ち残っていかなければならない」とは、よく言われることだが、ことはそれほど単純ではない。
国境を低くし、世界規模で自由競争を行うというのは、言うなれば新しい時代の参加資格にすぎない。規制緩和をし、グローバル・スタンダードに合わせれば誰でも勝てる、みんなが幸せになれるというのであれば、こんなに簡単な、素晴らしい話はないが、現実はそうではない。そこにはやはり「勝つ原理」が厳然と存在するのだ。
私は、この大転換期を見通すうえでのキーワードとして「ユダヤ化」という単語を提示したいと思う。
私の言う「ユダヤ化」とは、その勝つ原理を解くためのキーワードである。すなわち、グローバル時代、ボーダレス時代における「成功の原理」はユダヤにあるというのが、私の仮説である。
だが、ユダヤ化といっても「現在のグローバル経済を陰で操っているのはユダヤ資本である」とか「ユダヤ人の陰謀が日本経済を破綻させた」と言うのではない。その点は強調しておきたい。
複雑系とも言われる自由経済を、一握りの人間が自由に動かせるなどというのは、空想小説としては面白いかもしれないが、現代経済においては現実に起こりえないことである。
私の言う「ユダヤ化」というのは、簡単に言えば、現在のグローバル化の流れにおいて、最も成功するのはユダヤの流儀である、ということなのである。もちろん、その”筋”はユダヤ人が仕組んだものではないし、陰謀でもない。あるいは、世界の指導者たちがユダヤ人に好意的で、ユダヤ人向きになるように世界経済を誘導したのでもない。たまたま世界の潮流が、ユダヤ人に有利な方向に流れるようになったということなのである。
ここで私の言う「ユダヤ化の方向」というのは、たとえて言えば、現代が女性解放のほうに流れているというのと似ている。女性を解放した本当の力は女性ではない。たいていは男である。
たとえば妊娠調節のピルを発明し、企業化したのは女性ではない。電器炊飯器や電器洗濯機を開発し、工業化したのも女性ではない。給料の銀行振込制度を可能にしたのも女性ではない。いずれも男たちがやったことであり、彼らこそが現代の女性解放を可能にする条件を作ったのである。
こうした男たちの発明がなければどうなっていたかは、男たちが近代科学に基づく発明をせず、その工業化もろくにしていない国々を見ればすぐに分かることである。そうした国では今でも、男女の同権、男女の共生は夢物語である。
つまり、「女性に有利な社会」の基礎を作ったのは男たちである、という意味で、ユダヤ化──ユダヤ人的生き方の有利な世界──を実現するもとになったのは、当事者のユダヤ人ではなく、非ユダヤ人なのである。
ユダヤ人は中世から金融業をほぼ独占してきた。これもユダヤ人がやったというよりも、中世のキリスト教会がカネを貸して利息を取ることを禁じたために、金貸しが非キリスト教徒であったユダヤ人の独占みたいになったのである。〈中略〉
■ボーダレス時代はユダヤの時代
……かように近代のユダヤ人ほど国家と国境に苦しめられた人たちはいない。そのユダヤ人たちが、今のグローバル化、ボーダレス化の状況をいかに歓迎しているかは、あらためて言うまでもないわけだが、それを私自身もつい先日実見する機会に恵まれた。
昨年の秋、オランダのハーグで開かれた国際ビブリオフィル学会(愛書学会)に出席したとき、私は家内や娘を伴ってドイツ留学時代の恩師に会いに行った。恩師もすでに85歳である。これまで何度か、日本にお招きしたこともあったが、「もう飛行機に乗って旅行するだけの体力もないよ」とおっしゃっておられるので、多少、日程的に無理をしてでも恩師のお宅を訪ねようと思ったのである。オランダからドイツヘは車で行った。といっても高速道路を使えば、数時間の距離である。
ところがそこで驚いたのは、オランダとドイツとの間にはもはや国境の掲示すらないという事実である。その高速道路は今まで何度も利用したことがあったが、そのときにはまだ税関(といっても、実際には何も調べないが)があった。ところが、国境と思しきところで注意深く観察したが、今ではその標識すらないのである。オランダ人の運転手に「もうドイツに入ったのか」と尋ねたが、プロのオランダ人のドライバーですら、そこがドイツなのかオランダなのかが分からないのである。
1999年の通貨統合を控え、すでにヨーロッパ大陸では国境そのものが消滅しようとしているとは新聞や雑誌を通じて知っていたが、国境の表示すらすでに撤去されているとは思いもよらなかった。
そのときの体験があまりに印象的であったので、私は翌日、その学会のパーティでこのことを話した。すると、それを聞いて一番喜んだのがアメリカのユダヤ人であった。彼は私の話を聞くや、「ワンダフル」と叫んで飛び上がらんばかりであった。
その姿を見て、「やはりユダヤ人にとって国境とは仇(かたき)同然であったのだ」とあらためて確認した。彼らユダヤ人からすれば、忌まわしき国境がなくなっていくグローバル化時代は、まさに長い間待ち望んだ「わが世の春」という思いなのであろう。
ユダヤ人たちは長年にわたって国家や政府にあまり頼らない生活を送ってきた。というよりも、国家などに頼ることができなかった。
ところが、そのハンディキャップは今日になってみれば、測り知れないほどのアドバンテージとなった。国家や国境の存在を当然のように思ってきた非ユダヤ人にとって、ボーダレス社会が未経験のものであるのに対し、ユダヤ人は昔から「国境なき社会」を生きてきたのであるから。
■ユダヤ流の「勝つ原理」─ 3つの特徴
これまで見てきたように、ユダヤ人は自分の国を持たない少数民族として、迫害を受けつつ生き延びてきたわけだが、その中で培われたユダヤ人の生き方の特徴、あるいは知恵として、私は次の3つの点を特に指摘しておきたいと思う。
その3つとは、すなわち
【1】血縁によるグローバル化
【2】契約書至上主義
【3】徹底した才能尊重
である。
この3つの特徴は、かつてはユダヤだけのものであったわけだが、今日においては非ユダヤ人の中にも急速に普及している。この3つが言うなれば、ユダヤ流の「勝つ原理」とも言える。
そこで、まず第1の「血縁によるグローバル化」から考えてみよう。
■血縁によるグローバル化 ─ 海外分散の知恵は、なぜ生まれたか
経済の国境が低くなっていく状況に対応するため、先進国の企業は先を争ってグローバル化を進めている。企業活動を一ヵ所に集中させるのではなく、それぞれのセクションがその機能に最もふさわしいところに活動拠点を定めるという「分散型グローバル化」が、これからいっそう盛んになっていくだろうと言われている。これは、読者もご承知のとおりである。
だが、この分散型グローバリゼーションヘの流れも、ユダヤ人に言わせれば「われわれの時代が来た」という思いであろう。というのも、ユダヤ人たちは昔からそれを実行してきたからである。
ユダヤ最大のロスチャイルド財閥の創始者マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドは、18世紀ドイツのフランクフルトで両替商として成功を収めた人物であるが、彼は長男だけはフランクフルトに残し、あとの子どもたちにはすべて外国で開業させた。
すなわち次男をウィーン、三男をロンドン、四男をナポリ、そして五男はパリに送って、各地でロスチャイルド商会の看板を掲げさせたのである。自分が住んでいるところの皇帝や王侯の気が変わって、迫害されることになっても、別の国の血族を頼って逃げていけばよい。迫害がない場合でも情報網として役立つからだ。〈中略〉


(左)ロスチャイルド財閥の創始者
マイヤー・アムシェル・ロスチャイルド
(ロスチャイルド1世/1744~1812年)
(右)獅子と一角獣が描かれているロスチャイルド家の紋章





ロスチャイルド1世には5人の息子がいたのだが、それぞれをヨーロッパ列強の首都に
派遣して次々と支店を開業させ、それぞれがロスチャイルドの支家となった。上の画像は左から、
長男アムシェル(フランクフルト本店)、次男サロモン(ウィーン支店)、三男ネイサン
(ロンドン支店)、四男カール(ナポリ支店)、五男ジェームズ(パリ支店)である。
■ユダヤ財閥ロスチャイルド成功の秘密
……ロスチャイルドの創始者がその子息たちを海外に分散させた最大の理由は、情報網の構築ということだけではなかった。それよりも切実な動機としてあったのは「ユダヤ人が一国だけで商売を続けていることは危険だ」という思いなのである。
ヨーロッパにおいてユダヤ人がどれほどの迫害に遭ってきたか──そのことを語りだせばきりがないが、そのひどさは多くの日本人の想像を超えたものである。一夜にして法令が変わり、財産はもとより、住むところさえ失ってしまったユダヤ人の話は、何もナチス・ドイツだけのことではない。経済的に成功したユダヤ人に対しては、当局も民衆も容赦はしなかったのである。
ロスチャイルドの創業者マイヤー・アムシェルが何よりも心配したのは、そのことであろう。
フランクフルトで、ヘッセン伯ウィルヘルム9世の寵(ちょう)を得、宮廷銀行家として成功はしたけれども、その座は決して安泰ではない。むしろ成功すればするほど、より一層危険な段階に突入したと考えなければならない。
そこで彼は、フランクフルトだけに財産を置くのではなく、分散する方法を選んだ。それで息子たちをあえて外国に送って、そこでロスチャイルド商会を開業させたわけである。そうすれば、かりに一ヶ所が閉鎖のやむなきに至っても、ロスチャイルド家全体は生き残ることができる。
この海外分散の知恵は何もロスチャイルドだけの専売特許ではない。ユダヤ人なら当然のことなのである。
私の知合いのユダヤ人古書籍商にも、同じように親戚が海外に散らばって、それぞれの土地で古書店を開業している人がいる。その人の場合も、オランダで古書籍商を開業した祖父が「一ヶ所に集中しているのは危険だ」という判断から、各地に子どもたちを分散させたのだという。言われてみると、その古書籍商と同じ名字を持つ本屋はロサンゼルスにもあるし、またパリにもある。古書といっても、安いセコハンではなく、アンティクェリアンと言われるもので、10万円台から何億もする古書や古写本を扱う店である。
かようにユダヤ人として生きていくのは、まことに大変なことであったわけだが、それが20世紀も終わりに近づいてくるに従って、逆にそうした生き方をするほうが得をするという時代になったのである。
私の知人の古書籍商にしても、先祖は危険分散のために各地に出店を作らせたわけだが、これだけインターネットをはじめとする通信網が整備されれば、各地に血の繋がった同業者がいることがますます有利に働いていることは、あらためて説明するまでもない。
■■Part-2
■「日の沈まぬ帝国」を作ったユダヤ人
何度も繰り返すように、現在の世界がユダヤ人に有利なようになったのは、決してユダヤ人自身の「陰謀」からではない。しかし時代の流れは、間違いなくユダヤ的な行動原理のほうが得をするような形で進んできたのである。国境を越えた経済活動を行おうと思えば、ユダヤ人のやり方に学ぶことが最も成功に近いのだ。
ユダヤ人に学んだものが成功を収める──そのことは近代史の流れを俯瞰(ふかん)してみると、より明確になる。
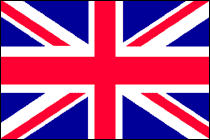
近代のヨーロッパ諸国において、ユダヤ人に対して最も寛容だったのは大英帝国であろう。19世紀後半、つまり大英帝国の絶頂期に、イギリス保守党出身の首相となったのがベンジャミン・ディズレーリである。
ディズレーリ(Disraeli)、つまり「デ・イズラエリ」(イスラエルから来た人)という姓が示すように、彼はユダヤの血を引く人間であった。父親の代になってキリスト教に改宗したため、厳密な意味でのユダヤ人とはいえないが、彼がユダヤの出身であることは当時から周知の事実であったことは言うまでもない。
19世紀の大英帝国が、ユダヤの血を引く人間を首相に据えたという意味は、今日のわれわれが想像するよりも、ずっと大きなものがある。
前にも書いたように、ユダヤ人は確かにヨーロッパの各地で成功を収めていたが、それはあくまでも経済的な面でのことであり、彼らが政治の世界に参加することはタブーに近かった。ヨーロッパ各地に暮らしているユダヤ人が、一つの国家に忠誠を尽くすとは思われていなかったからである。大英帝国がユダヤ人を首相にしたというニュースは、おそらく欧州大陸の人びとにとって眉をひそめるような話であったに違いない。
ところが、結果を見てみれば大英帝国はユダヤ人ディズレーリを首相にしたことによって、「日の沈まぬ帝国」になったのだ。1877年、ビクトリア女王をインド帝国初代皇帝にしたのもディズレーリだし、また膨張主義を採るロシアの南下政策をベルリン会議で封じることに成功したのもディズレーリの功績である。

ベンジャミン・ディズレーリ
(1804~1881年)
イギリスのヴィクトリア朝の
政治家。小説家としても活躍。
彼はユダヤ人であったが、子供の時に
ユダヤ教から英国教に改宗した。
■ユダヤ・コネクション
この大英帝国の外交的勝利は、ひとえにディズレーリというユダヤ人を宰相の座に据えたことにあったと言っても過言ではないだろう。ユダヤの知恵を活用することによって、イギリスは世界帝国になったのである。
そのことを象徴するエピソードが、1875年の「スエズ運河会社」の株の買収である。
アジア大陸とアフリカ大陸の境界にあるスエズ地峡に運河を拓(ひら)くことは、イギリスにとって長年の課題であった。スエズ運河が完成すれば、イギリスからインド、さらにアジアヘと向かうルートは一挙に短縮できる。アフリカ大陸南端の喜望峰を迂回していく船が、地中海から一気に紅海、そしてインド洋に出ることができれば、イギリスの植民地政策は一層堅固なものになるであろうし、また貿易もより盛んになるはずであった。
ところが、このスエズ運河の利権を得たのは、ライバルのフランスであった。フランス人レセップスがスエズ運河の利権を入手し、1869年、スエズ運河はついに完成する。

開通当時のスエズ運河
ヨーロッパとアジアを結ぶスエズ運河は、世界の
海運の流れをガラリと変える画期的なものだった
このスエズ問題はイギリスにとって頭痛の種であった。もし、フランスがイギリス船舶のスエズ通行を阻止すれば、イギリスのアジア植民地は孤立してしまうであろう。大英帝国にとって、スエズは文字どおりの生命線なのだ。
このスエズ運河問題に解決の糸口をもたらしたのは、他ならぬ「ユダヤ・コネクション」だった。
1875年のある日曜日、ディズレーリはロスチャイルド家の晩餐に招かれていた。ロスチャイルドとディズレーリとは、ユダヤ同士ということから古くからの友人であった。
その食事中、当主のライオネル・ロスチャイルドのもとに一片の電報が届いた。それは、パリにいたロスチャイルドの関係者から送られたもので「エジプトの副王が、自分の持っているスエズ運河株の売却をフランス政府に申し出たが、フランス側はまだ受諾していない」というニュースであった。
この電報を示されたディズレーリが、その場で総額400万ポンドのスエズ運河株の買収を決断したのはいうまでもない。スエズ運河の株をイギリス政府が取得し、その経営権を得るということは、すなわち地中海からインド洋への最短ルートを買うことに他ならない。ただちにディズレーリは秘密裡に閣議を召集し、株取得の了承を得た。
■ユダヤ人を味方にした国家は栄える
ところが、困った問題があった。折しも英国議会は休会中であった。議会の承認がなければ、株取得のための予算調達ができないのだ。議会の休会中にイングランド銀行が政府に融資することは法で禁じられていたし、かりにそれが可能であったとしても、イングランド銀行にしても400万ポンドもの現金をすぐに調達することはできなかった。
そこでディズレーリは再びロスチャイルドを訪れることにした。ディズレーリはロスチャイルドに対して「明日までに400万ポンドを融資してくれ」と頼んだ。このときロスチャイルドは「担保は何ですか」とたずね、首相は少しも騒がず「大英帝国が担保だ」と答えたと伝えられている。
ロスチャイルドが400万ポンドをただちに融資したのは言うまでもない。かくしてイギリスはスエズ運河に対する支配権を手に入れ、その後、インドはもとより極東にまでその勢力を拡大することになったわけである。
イギリスがスエズ運河を支配することができたのは、ひとえにユダヤ・コネクションのおかげであった。エジプト副王がスエズ株を売りたがっているという情報も、また400万ポンドという巨額の買収資金も、ユダヤ人のディズレーリとロスチャイルドの間の信頼関係、そしてロスチャイルドの情報網と資金力がなければ大英帝国は手に入れることができなかった。
しかし、この話からユダヤ・コネクションの強さだけを学ぶのは即断にすぎる。
本当に偉いのはユダヤ人ではなく、そのユダヤ人を首相にした大英帝国なのである。この一件でディズレーリは名宰相という評判を得たし、またロスチャイルドも多額の金利を得たわけだけれども、最も得をしたのは大英帝国なのである。
「運をよくしようと思えば、運のいい人と付き合え」とは千古の知恵だが、同じように「豊かになるには、豊かな人と付き合うべし」と言ってもよい。国家を豊かにするには、豊かなユダヤ人を味方にすることが最善の道であることを大英帝国の繁栄は教えてくれるのである。
他のヨーロッパ諸国が裕福なユダヤ人を妬み、ゲットーに押し込めていた時代、大英帝国はユダヤ人を首相に据えるほどユダヤ人に対して寛容であった。1848年には、選挙によってユダヤ人のロスチャイルドが英国下院の議員に選ばれたほどである。
■今なおイギリスに好意的なユダヤ人
イギリスはユダヤ人に対する偏見が少ない、という評判が、大英帝国にとってどれだけの益をもたらしたか測り知れない。イギリスに定住する豊かなユダヤ人が増えれば、当然のことながら、それだけイギリスの富が増えるわけだが、恩恵はそれだけに終わらない。
ワーテルローやスエズのエピソードが示すように、ユダヤ人はどんな国の政府よりも優れた情報網を持っている。そこで自然とイギリスに第一級の情報が流れ込むようになった。大英帝国の繁栄は、そうしたユダヤの情報ネットワークと密接に関係していたわけである。
また、今日でも世界の人びとがイギリスに対して好印象を抱いているのも、ユダヤを味方に引き入れたことが大きい。「近代民主主義発祥の国」というイメージが強いイギリスが、過去にどれだけの悪事をなしたことか。
イギリスはシナ人にアヘンを売り付け、挙げ句の果てに「アヘン戦争」までやった。また、1886年にビルマ(現ミャンマー)を武力併合したときには、ビルマの国王と王妃を逮捕し、セイロン(現スリランカ)に流刑にしたばかりか、その王女たちはイギリス兵(インド人)に「戦利品」として分配された。さらにインド支配において、どれだけインド人が虐げられたかは言うまでもない。
ところが、今日になってみると、こうした歴史的事実はあまり強調されないし、思いだす人も少ない。これは、やはり全世界の主要マスコミを支配するのがユダヤ人であることと大いに関係があるのだ。
しばしば「ジューヨーク・タイムズ」(ジューとは、ユダヤ人のこと)と揶揄(やゆ)される『ニューヨーク・タイムズ』をはじめ、欧米、ことにアメリカの報道機関にはユダヤ資本が少なくない。また、優れたジャーナリスト、作家にもユダヤ人は多い。彼らはイギリスのよい面だけを報道しつづけ、イギリスに敵対する国を残虐・野蛮として描きつづけているのである。
イギリスがユダヤに寛容であったという事実をよく知っている彼らが、イギリスに対して好意的なスタンスを取るのは人情として当然のことである。イギリスが19世紀末にユダヤ人に寛容であったことは、いまだに巨大な情報財産として残っているわけである。
■■Part-3
■アメリカに渡ったユダヤ人たち
さて、この大英帝国に続いて「ユダヤの知恵」を取り込むことに成功したのが、アメリカであった。
アメリカという新天地は、ユダヤ人にとって非常に魅力的に見えた。なぜならアメリカは移民の寄せ集めの国家であって、歴史も伝統もない。だからユダヤに対する偏見や差別も、あったにせよ伝統のあるヨーロッパほどではなかった。
そもそもユダヤ人がヨーロッパで差別されたのは、彼らが「後から来たよそ者」であり、宗教が違うからだ。アメリカはみな新参者の集まりであり、宗教もカトリック、さまざまなプロテスタント宗派、オーソドックス(ロシア正教)、モルモンなど、ヨーロッパのどの国よりも多様に入り交じっているのだから、ユダヤに対する偏見が薄くなるのも当然である。そこで、アメリカには迫害を逃れるために移住するユダヤ人が跡を絶たなかったのである。
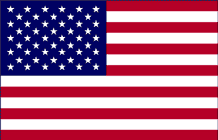
アメリカはWASPの国、つまり白人のアングロ・サクソン系でプロテスタントが主流を占める国家だと言われる。それはたしかに事実である。だが、その一方で、ユダヤ人なかりせば今日のアメリカはありえなかったというのも、また事実なのだ。
たとえば、アメリカを特徴づける産業の一つ、ハリウッドの映画業界はユダヤ人たちが興したようなものである。MGM、20世紀フォックス、パラマウント、コロンビア・ピクチャー、ワーナー・ブラザース……我々が知っている主要映画会社はみなユダヤ人によって作られたと言ってもいいし、今でもユダヤ資本の力は強い。
また、アメリカのジャーナリズムも、一時はすべてユダヤ資本がそのほとんどを占めるという時代があった。最近のM&Aブームで多くの新聞社、雑誌社は大企業や海外資本の傘下に入り、ユダヤ資本は以前に比べれば少なくなったとも言われるが、たとえば最も信用の高い『ニューヨーク・タイムズ』や『ワシントン・ポスト』は今なおユダヤ資本であるし、また有名なジャーナリストの多くがユダヤ人である。
だが、何と言ってもユダヤ人がアメリカに最も貢献したのは金融業であろう。アメリカの金融業の歴史はそのままユダヤ人の歴史であると言ってもいい。
一例を挙げれば、アメリカ最大の銀行の一つである「チェース・マンハッタン銀行」は、ロックフェラー財閥系の「チェース・ナショナル銀行」とクーン・ローブ財閥系の「マンハッタン銀行」が1955年に合併して生まれたものだが、後者のクーン・ローブ財閥はドイツ系ユダヤ人のクーンとローブが興したものである。このチェース・マンハッタンにかぎらず、アメリカの主要銀行、主要証券会社の多くはユダヤ系資本によって作られたものである。
ウォール街では、今でもユダヤ教の休日になると、証券や債券の取引が減るのだという。いかにユダヤ人がアメリカの金融界で活躍しているかが、この一事をもってしても分かるではないか。



(左)「クーン・ローブ商会」。1867年、ドイツ系ユダヤ人によって
ニューヨークに設立された。(右)チェース・マンハッタン銀行
■ユダヤ人たちの「アメリカン・ドリーム」
現在のアメリカ経済が発展するようになったのも、結局はユダヤ人が自由に活躍できる場を提供したことに深く関係している。
国際的なコネクションを持つユダヤ人が集まるところには、世界の情報が集まる──経済の発展、ことに国際金融の発展にとって、これほど有利なことはない。ワーテルローの戦いにおけるロスチャイルドの故事を見ても分かるように、良質な情報を手に入れられるか否かが金融業の生命線なのである。いかに大きな資本を持っていても、どこに投資すべきかという情報がなければ、そのカネは死んだも同然である。
その点において、アメリカは実に大きな力をユダヤ人から得た。ユダヤ系の金融機関、ユダヤ系のジャーナリズムの情報力によって、アメリカ経済は発展のきっかけを掴んだ。国際政治の世界においても、ユダヤ人の情報力がアメリカの役に立ったことは数知れないだろう。
一方、ユダヤ人の実力も、アメリカという土地を得て、さらに発展することになったと言える。新世界においては、ユダヤ人もWASPもスタート・ラインはほとんど同じなのだから、ユダヤ人はいくらでもその能力を伸ばすことができた。ヨーロッパにおいては、ロスチャイルド家だけが有名なユダヤ財閥であるが、アメリカにおいては無数のユダヤ財閥が誕生した。「アメリカン・ドリーム」という言葉は、何よりもユダヤ人のためにあった言葉ではなかっただろうか。
■日露戦争とユダヤの意外な関係
少し余談になってしまうが、明治の日本が日露戦争において勝利を収めえたのも、一つにはユダヤ人を味方に付けたからであった。
明治維新からわずか36年後の1904年、朝鮮半島に南下しようとするロシナを阻止し、自らの独立を守るため、戦うことになったとき、当時の日本政府が最も頭を悩ましたのは軍資金の問題であった。何しろ、相手は世界でも有数の軍事大国である。ロシアには巨大な陸軍があり、また東洋艦隊バルチック艦隊がある。このロシアを相手に戦うには多額の戦費が必要になるのは誰の目にも明らかであったが、当時の日本経済の実力ではそれを賄うだけの力はない。
そこで日本は欧州において戦費を調達することにした。戦争公債を発行して、ヨーロッパの投資家たちに買ってもらおうというのである。日銀副総裁であった高橋是清(後の大蔵大臣)が欧米に飛び、公債を売ることになった。当初の目標は1000万ポンドであった。

高橋是清
(たかはし これきよ)
日銀副総裁。のちに蔵相、首相。
「ダルマ首相」と呼ばれて親しまれた。
高橋是清の責任は重大であった。もし日本の公債が売れなければ、ロシアと決着をつける前に戦費の重みで日本経済は完全に破綻してしまうのだ。公債募集は実際の戦闘と同じくらいの重みがあった。高橋是清はそれを一人でやり遂げなければならない。高橋是清の送別会で、元老・井上馨は泣いてスピーチができなかったという。維新の元勲ですら泣かずにはいられなかったほど、高橋の任務は重大であったし、また困難なものであった。
最初、高橋は船に乗ってサンフランシスコ経由でニューヨークに行き、日本に好意的なアメリカで公債を売ろうとしたのだが、当時のアメリカは外国への投資よりは自国の産業育成のための外資導入に熱心な段階であったので問題にならず、当初の目的であったロンドンに入った。だがロンドンでも高橋はたちまち壁にぶつかった。国際金融の中心地であったロンドンの投資家たちも、日本の公債など買ってくれなかったのである。
誰も日本の公債を買わなかったのは、当然のことであった。なぜなら、当時の人間にとって、日本は近代化を始めて30年そこそこの赤ん坊のような国家である。それがナポレオンにも勝ったロシアと戦って勝てるわけがない、というのが当時の常識であった。負けて滅びるような国家の債券を買う人間はいないのである。
そこで高橋はやむなく債券の利回りを4%から6%に上げた。公債の利息が6%というのは常識外れに近い高利であり、返済に苦労するのは分かっているが背に腹は代えられない。何としてでも戦費を集めなければならない。
高橋是清、そして日本にとって幸運だったのは、彼がロンドンに到着してから12日後に、ロシア太平洋艦隊の旗艦ペトロパウロウスクが旅順沖で機雷に接触して轟沈し、同艦に乗っていた司令長官マカロフ中将が戦死するという出来事が起こった。その結果、日本の制海権把握に信頼が生じたこと、および日本政府が公債の支払いに几帳面であった実績が物を言って500万ポンドの公債発行契約が成立した。
だが、それでもようやく公債は計画の半分を売っただけにすぎない。戦争継続にはとうていそれでは足りないのである。
■ユダヤ・コネクションがあれば歴史は変わった
ところが、そこに奇跡のようなことが起こった。
ロンドンで知人の家に招待された高橋是清は、そこでヤコブ・シフというユダヤ系アメリカ人の銀行家に紹介された。食事の際に話していると、シフはスティーブンソン(『宝島』の作者)の書いた吉田松陰の話を読んだことがあり、日本に対して並々ならぬ関心を抱いていることが分かった。そして話題は日本の公債のことに及び、高橋は率直にその実情を語った。


(左)アメリカ・ユダヤ人の中心的存在だった
ユダヤ人金融業者ヤコブ・シフ (右)司馬遼太郎
が書いた歴史小説『坂の上の雲』(文藝春秋)
(この本の第4巻にシフが登場している)
シフは1847年にドイツのフランクフルト
で生まれ、1870年にアメリカに帰化した。
※ ヤコブ・シフの祖先はドイツのフランクフルトの
旧ユダヤ人街区にある一軒の家をロスチャイルド家と共有
して住んでいた。シフ(schiff)家の側には「船(schiff)」が、
ロスチャイルド(rothschild)家の側には「赤い盾(roter Schild)」
が描かれてあり、両家の姓はそこに由来していると言われている。
するとその翌日、日本の公債を引き受けたイギリスの銀行のロンドン支店長が高橋のところを訪れ、「アメリカのクーン・ローブ銀行が残りの公債を全部引き取る意向を持っています」と言うのである。高橋是清にはクーン・ローブという名前は初耳だった。聞くと昨夜、吉田松陰の話をしたシフという男が、その銀行の頭取であるという。高橋は最初信じられない思いであったが、その申し出をありがたく受け入れた。
かくして日本が当初目標としていた1000万ポンドの調達は成功したわけだが、シフが巨額の日本国債を引き受ける気になったのは、要するにこういうことであった。
今のロシアはユダヤ人を迫害している国である。その国と戦っている日本のために起債に応じてもよい──もちろん銀行家としてシフは、戦局に対する一応の見通しや、日本政府の誠実さを計算していただろうが、起債に応じた動機は反ユダヤ的ロシアと戦っている日本を助けたいということであったのだ。
当時のヨーロッパにおいて、ロシアほどユダヤ人を迫害した国はなかった。ロシアにおけるユダヤ人迫害はこの時期、最も猖獗(しょうけつ)をきわめていた。もともとロシアのユダヤ人は法律によって自由が奪われ、ひどい差別を受けていたのだが、1880年代に入って「ポグロム」が始まったのである。
ポグロムとは、ロシアにおけるユダヤ人の虐殺を指す用語である。社会不安が高まったロシアの社会は、その捌け口をユダヤ人に見出した。至る所で暴徒はユダヤ人を虐殺、暴行、略奪した。これに対して、ロシア政府は何の取締まりをしなかったばかりか、逆にユダヤ人の自由を制限する法律を公布した。日露戦争の前年にもオデッサ近くの都市でポグロムが発生したが治安当局は見て見ぬふりであった。そのため、日露戦争当時はロシアから多数のユダヤ人が難民として逃げ出していたのである。
シフは、ロスチャイルド家と同じくフランクフルト(ドイツ)のユダヤ人旧家の出身である。渡米して金融業を始め、ユダヤ人のクーンとローブが経営する「クーン・ローブ銀行」に入社、のちにローブの娘と結婚し、また金融手腕も認められて同銀行の頭取になっていたのである。また彼は「全米ユダヤ人協会」の会長であり、ロシアで迫害されているユダヤ人(アシュケナジーという)の支援運動を行っていた。その運動の一環として日本の公債を買うと言うのである。
■ユダヤ資本と戦争
かくして高橋是清は公債をすべて売ることができ、日本はその戦費を使ってロシアに勝てた──つまり、ユダヤを敵に回したロシアは敗れ、ユダヤを味方に付けた日本は勝ったわけだが、残念なことに日本とユダヤとの縁は、そこで切れてしまったようである。
もし、あのときのシフと高橋是清との出会いが、そのまま続いていたら、戦前の日本はもっと経済的に栄えていたに違いない。私はそのことを思うと残念でならないのである。
すでに述べたように、世界史においてユダヤ人を味方に付けた国はみな栄えた。逆にユダヤをいじめたロシア帝国は滅び、こともあろうに共産主義の国家になってしまった。ユダヤ人は世界史においていつも脇役であって、ずっと主役になれなかった民族であるが、彼らは国家の命運を左右する重要な存在なのである。
そこで一つ付け加えておけば、日露戦争とユダヤ金融業の関係は高橋とシフだけのことではなかった。
ポーツマスにおける日露和平交渉では、最後の段階で日本が譲歩して和議が成立した。日本代表は小村寿太郎、ロシア代表はウィッテである。
この和議成立の知らせを、ウィッテはまずロシア皇帝に伝えるべきであった。だが、ウィッテが最初に電報を打ったのは、ベルリンのユダヤ人銀行家メンデルスゾーン(作曲家メンデルスゾーンの一族)であった。ロシア皇帝への電報はメンデルスゾーンの次であった。
ウィッテは大蔵大臣をやったことのある財政家である。ロシアの経済もユダヤ人のお金がなければもたないことを知っていた。ウィッテはポーツマスに来る前にユダヤ人の銀行家たちから「戦争を続ける気ならロシアには一文も融資しない」と言い渡されていたのである。ユダヤ人たちが心情的には日本を応援していたのは事実だが、日本もロシアも戦費の多くをユダヤ人に頼っていたことは見過ごすべきでないであろう。
話を戻せば、明治の日本が日露戦争のときに得たユダヤ・コネクションを、もしも上手に活用していれば、日本には重要な情報がたくさん入ってきただろうし、またユダヤ資本と協力してさらに産業も大きくできたかもしれない。たとえば満洲の重工業にユダヤ資本を参加させていたら、イギリスやアメリカの満洲国に対する態度は、別のものになっていたはずである。だが、現実はまったく逆であった。
戦前の軍部は、ユダヤ人を迫害したナチス・ドイツと同盟を結んでしまった。これでは日本の運命が悪くなるのも当然と言わざるをえない。
1940年(昭和15年)9月、日独伊三国同盟が締結された。この年の終わり頃、クーン・ローブ銀行の紹介状を持った2人のカトリック神父がやってきた。その目的の一つは、ユダヤ排撃を政策として打ち出しているヒトラーと日本との同盟に関係したものであったに違いない。
その時、もし高橋是清が生きていたら、シフの銀行の紹介ということで対応も違っていたであろう。しかし、高橋はその4年半前に2・26事件で青年将校に殺されていたのである。嗚呼(ああ)。
事実、三国同盟締結と時を同じくしてアメリカは蒋介石の重慶政権に1億7500万ドル、イギリスも1000万ポンドの借款を与えているのだ。このカネがユダヤ人と関係しているのは明らかである。蒋介石は外貨に不自由しなくなったのである。
対米戦争を始めることになったのも、もとはといえば日本がアメリカから石油禁輸を受け、にっちもさっちも行かなくなったからだが、アメリカ経済に隠然たる力を持つユダヤ人を味方に付けていれば、そこまでアメリカは日本をいじめることもなかったのではないか──今さら悔やんでも仕方のないことだが、私には残念でならないのである。
■■Part-4
■「ユダヤの原理」とは何か
ヨーロッパのユダヤ人は中世以来、国家や政府からの保護のないところで経済活動をし、成功を収めてきた。それに対して、日本人を含む非ユダヤ人は、国家や政府の規制を前提にして活動してきたわけである。
ところが今日の先進国では、規制緩和によって経済活動から国家や政府が関与する部分は急速に減りつつある。となれば、ユダヤ人的生き方のほうが主流になってくる、つまり世界が「ユダヤ化」するのは当然の結果であろう。
実際、現代世界において、英米、つまりアングロ・サクソン系の金融資本が成功を収めているのも、結局はイギリスやアメリカがユダヤ人に比較的自由な活動の場を与え、そのユダヤの知恵や資本をうまく吸収・活用したからに他ならない。グローバル社会に参加するわれわれ日本人も、否応なく「ユダヤの原理」に合わせていかざるをえないのである。
では、そのユダヤ化の特徴とは何か──その第2の特徴として、私は「リーガライゼーションの進行」を挙げたい。すなわち、法や契約を非常に重視する傾向、言い換えれば「契約書至上主義」である。〈中略〉
……さて、このユダヤ的な契約絶対主義は、ヨーロッパではまだまだ全体に普及していたわけでなかったが、その精神はアメリカで花開くことになった。〈中略〉 アメリカの法曹界ではユダヤ系の勢力は非常に強いそうだが、これもまた不思議なことではない。法律や契約書に関するかぎり、どんな国民よりもユダヤ人のほうが、その歴史が長いのだから。
さすがに昨今のアメリカでは、増えすぎた訴訟合戦に対する反省が起こっているそうだが、この傾向を止めることはできないし、むしろアメリカ以外にも広まっていくことであろう。なぜならグローバル化が進めば進むほど、契約書の重要性は増していくし、裁判も増えていかざるをえないからである。文化も言語も習慣も違う人びとがグローバル社会の中で取引をするのだ。そこで唯一確実なのは紙に書かれた契約書だけである。シェークスピアの名作『ヴェニスの商人』のシャイロックのごとく行動しなければ、生きていけないし、シャイロックのような疵(きず)のある契約書を作ったのでも生きていけないのがグローバル社会なのである。
ベルリン大学教授として資本主義の合理的理解に大きな貢献をなしたヴェルナー・ゾンバルトも「アメリカ合衆国は、おそらく他のどの国よりも強烈に、徹頭徹尾、ユダヤ的性格に満たされている……」とか、「われわれがアメリカニズムと呼んでいるものは、それこそ大部分が流入したユダヤ精神に他ならない……」と言っている(『ユダヤ人と経済生活』荒地出版社)。

ドイツの経済学者
ヴェルナー・ゾンバルト
■日本にも押し寄せるリーガライゼーションの波
今や「ユダヤ的アメリカ資本主義」はグローバル化、ボーダレス化の世界において急速に普及しようとしている。
好むと好まざるとにかかわらず、アメリカ流のやり方、つまりユダヤ流のやり方を真似しなければ、「大競争の時代」に生き残れないのが現実である。何事においても契約書が絶対視されるという風潮も、もはやアメリカだけのものではない。
このユダヤ化の流れを、最初に痛感したのは海外に進出した日本企業であろう。どれだけ多くの日本企業が、契約書の不備を相手側に突かれ、痛い目に遭ったことか分からない。著作権や特許権を巡って、日本企業が多額の賠償金を払うという例が1970年代から80年代にかけて続出したことはご記憶だろう。
その経験を活かして、すでに大企業の中には法務部門を新設し、対応策を整えているところが増えている。これは慶賀すべき話であるし、今後はさらにその傾向が進むことだろう。〈中略〉
■徹底した才能の尊重 ─ なぜ、ユダヤ人に学者が多いのか
リーガライゼーションと並ぶ、ユダヤ化のもう一つの流れは「国家離れ」「組織離れ」の傾向である。グローバル化によって国境が低くなっていけば、そこに暮らす個人の生き方も変わってこざるをえない。個人が国境を自由に飛び越えて活動できるようになれば、国家や企業といった組織の持つ意味はどんどん薄まっていくのだ。〈中略〉
前にも触れたように、近代に入ってからのユダヤ人は、絶えざる迫害の中で生き延びていく過程で、さまざまな知恵を身につけてきた。いわゆるユダヤ人迫害がキリスト教圏で始まったのは1096年の第一回十字軍の結成のときからだと言うが、この年には半年ぐらいの間に、神聖ローマ帝国内のユダヤ人が3分の1から4分の1ぐらい殺されたという。
聖ベルナルド(1091~1153年)、教皇ユージェニウス3世(在位1145~53)、皇帝コンラート3世(同1138~52)らがユダヤ迫害の波を止めようと努力したにもかかわらず、その流れは西ヨーロッパ一帯に広まり、勢いを強めた。
1215年の「第4ラテラノ公会議」(一般に「大会議」と言われている)において、カトリック教会(教皇イノセンティウス3世)は、キリスト教圏におけるユダヤ人(そしてサラセン人)の地位を定め、その第68条においてはキリスト教徒と違う服装をしてバッジを付けることを命じ、第69条においては公職に就くことを禁じた。
このような風潮の下において、王侯貴族が何かと口実を作ってユダヤ人の財産没収をやったとしても不思議ではない。いつ住居から追い出され、国外退去にされ、財産を根こそぎ奪い取られても生きていけるようにするには、どうしたらいいか──そこでユダヤ人が学んだ教訓は、「自分の身に能力を付けよ」ということであった。
なぜなら、有形の財産だけで満足するのは危険である。土地や屋敷はもちろんのこと、たとえ金貨や宝石といった持ち運びやすい形で財産を持っていたとしても安心はできない(現に、ヒトラーのドイツは、ユダヤ人の所有品を根こそぎ没収したではないか)。
そこでユダヤ人たちは、たとえ裸一貫になっても暮らしていけるだけのノウハウを身につけようと努力した。今日でも、ユダヤ人が活躍している分野は、金融業をはじめとして、いずれも地位や財産だけではなくノウハウがものを言う業種である。
たとえば宝石鑑別業なども、その一つであろう。欧州における宝石取引の中心地はアムステルダムだが、この街で宝石業界を事実上牛耳っているのがユダヤ人たちであることは有名な事実だ。ユダヤ人が宝石関係の職業を好むのは、彼らの防衛本能から出たものである。宝石は小さいので、いざというときにも持ち出しやすいということも、彼らがこの職業を選ぶ理由の一つであろう。
だが、それ以上に重要なのは、かりに宝石すら没収されるようなことがあっても、宝石の目利きの能力さえあれば別の土地で再出発できるという点だ。ユダヤのような人びとにとって、宝石よりも頼りになるのは、宝石の目利きとしての能力なのである。
ユダヤに学者が多いというのも、実は同じ理由からだ。イスラエルを含むユダヤ人の総人口は、東京都のそれと同じくらいなのに、「ノーベル賞学者の2割はユダヤ人である」と言われるほど、ユダヤ出身の学者は多いわけだが、これは何もユダヤ教徒が他のグループよりも知的能力が高いからではない。ユダヤ人にとって、学者とは「いざとなったら、どこの国に行っても食っていける商売」なのだ。だからこそ、彼らは学者の道を選択するのである。
■アメリカの学問が世界最高になった理由
アドルフ・ヒトラーがユダヤ人を迫害した目的の一つは、「ドイツのアカデミズムからユダヤ人を追放するためであった」と説明する学者がいるほど、戦前のドイツの大学にはユダヤ人教授が多かった。
実際、ヒトラーは政権の座に就くとユダヤ人教授を追放したのだが、そこで職を失ったユダヤ人学者たちの中には、ただちにイギリスやアメリカで大学教授になった人が少なくなかった。いかにヒトラーといえども、彼らが他国に職を求めることまでは妨害できなかった。

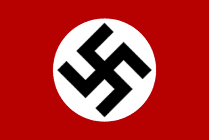
(左)アドルフ・ヒトラー (右)ナチス・ドイツの旗
ヒトラーのために、ヨーロッパからアメリカに渡った学者たちによって、アメリカの大学の水準は大いに高まった。
事実、ヒトラーが政権を取る1934年以前にアメリカ人学者でノーベル物理学賞を受賞した人はわずかに2人、化学賞は3人、医学賞が5人(この5人のうち3人は共同研究者)にすぎなかった。現在、ノーベル賞の多くをアメリカ人が独占しているのとは大きな違いである。
もちろん、これらの受賞者が即ユダヤ人であるというわけではないが、大量のユダヤ人学者が活躍してアメリカの学問水準が上がったことだけは間違いない。アインシュタインもアメリカに渡ったユダヤ人の一人であった。
音楽界でのユダヤ人の活躍には、さらに顕著なものがある。
第二次大戦後、ヴィルトゥオーソ(巨匠)と称された音楽家の中でユダヤ人でない人を探すほうがむずかしいくらいであろう。音楽の才能は早期に分かるものだから、これを伸ばしてやればユダヤ迫害が起きたときに国境を越えて助かりうることは、親にもよく分かる。そして才能ある若者には豊かなユダヤ人が高価な楽器を貸したり、時には与えたりすることが普通に行われていたのである。
また、あまり知られていないが、古書籍商もユダヤ人が多い職種の一つである。
前に記したが、一口に古本屋といっても、2種類ある。比較的最近刷られた本を扱う町の古書店のことを英語ではセカンドハンド・ブックセラー、文献学的・骨董的価値を持った本を専門に扱う古書店をアンティクェリアン・ブックセラーと言う。ユダヤ人の多いのは、もちろん後者である。
こうした価値の高い古書の取引は、一朝一夕に学べるものではない。その本がいつ、どこで作られたかは当然のこと、重要な書籍の場合、その本が過去、オークションに掛けられたのがいつで、どのくらいの値段で売られたかなどもすべて把握していなければ、一人前の古書籍商として通用しない。
しかし、逆に言えば、それだけのノケハウを身につけていれば、どこに行っても開業できるのが古書籍商という仕事であり、ユダヤ人に古書籍商が多いというのは、まことに当然の成りゆきなのである。しかも彼らが血縁によるグローバル化を進めていることは、すでに述べたとおりである。〈中略〉
■なぜ、日本にユダヤ財閥は来なかったのか
……前章で縷々述べたように、国際経済において長期的な勝利を収めるための条件とは、要するにユダヤ人を味方に付けるか否かという点にある。
ディズレーリの大英帝国が世界に覇を唱え、さらに現代アメリカ経済が国際経済の主人公となっているのも、結局は彼らが「ユダヤ人の知恵」を取り込むことに成功したからに他ならない。
これらの歴史的事実からわれわれが学ばねばならない教訓はあまりにも明白である。すなわち日本もユダヤ人を味方に付け、日本人がユダヤ人に学び、ユダヤの知恵をわが物にしないかぎり、日本が国際経済において生き残ることはむずかしいということである。
といっても私は「日本経済をユダヤ人が牛耳るようにすべきである」などと言っているのではない。
大事なのは、ユダヤ人の目から見ても、日本が住みよい国家になれるか否かなのである。ユダヤ人が敬遠するような経済体制を採っているかぎり、いくら経済をオープンにし、グローバル化の体裁を整えたところで、日本はとうてい国際競争の覇者にはなりえないということなのだ。つまり、ユダヤ人にとっての住みやすさが、その国の将来を知るうえでの重要な尺度なのである。
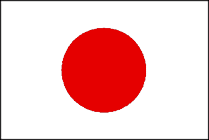
日本ほどの経済力のある国ならば、本来なら、今ごろユダヤ人の大財閥の次男や三男が移住していてもおかしくないところである。
ところが現実を見れば、ユダヤ財閥の血縁者が日本で活躍しているという話をあまり聞いたことがない。日本にまったくユダヤ人がいないわけではないが、大財閥と呼ばれるほどのユダヤ人の一族が日本に根を下ろしたということは聞かない。これはいったい、なぜなのか。
たしかに、これまでの日本は外国人が移住することに対して、いろいろな制限を行ってきたし、ことに戦前の日本においてはユダヤ人も進出しにくかったであろう、ということもよく分かる。しかし、資本のあるところ、儲けるチャンスのあるところなら、ユダヤ人は万難を排してでも進出するはずである。それなのに、戦後になっても、なぜ彼らは日本に定着しないのか。
なぜ、ユダヤ人は日本を敬遠するのか。
その答えは私の見るところ、一つしかない。それは戦後日本が私有財産を憎み、金持ちを迫害するかのような税体制を採ってきたからである。〈中略〉
現代の日本では「三代経つと財産はゼロになる」と言われている。いかに経済的に成功し、大金持ちであったとしても、その孫の代になると相続税や所得税で、ほとんどすべての財産が国庫に入ってしまうというわけであるが、この数年はもっとそれが進んで、子どもの代にはそっくり財産がなくなってしまう例も稀ではなくなった。〈中略〉
はたして、このような税制を行っている国に、ユダヤ人が住みたがるであろうか。いかに成功を収めたとしても、その財産が税として“没収”されてしまうような国にユダヤ人が定住するわけはない。〈中略〉
……経済的繁栄を求めるユダヤ人にとって、日本の課税制度はまさしく豊かなユダヤ人を狙い撃ちにしているかのごとく見えるに違いない。
ユダヤ人が日本を忌避する理由は、まさしくそこにある。成功すればするほど日本の税制は厳しくなっていくわけだから、日本に住みたがるユダヤ人などあるはずもない。いや、ユダヤ人にかぎらず、経済的成功を求めるために日本に移住したいと考える人間がいるはずはない。それどころか、日本の企業や個人の中でも、財産の海外疎開がすでに始まっている。
日本だけにしか住んだことのない日本人は、今の税制に慣れっこになっているため鈍感になっているが、世界の目から見れば、日本はまさしく「富裕な人を迫害する国」なのである。
以上、渡部昇一著『まさしく歴史は繰りかえす』(クレスト社)より
── 当館作成の関連ファイル ──
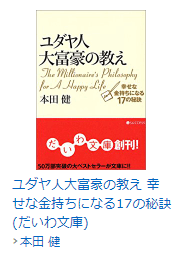



Copyright (C) THE HEXAGON. All Rights Reserved.