| ヘブライの館2|総合案内所|休憩室 |
No.a6fhc104
作成 1998.1
■Part-1
この日、私(高橋)はベラスコとボルマンとの昔話が出たついでに、ヒトラーやエヴァと別れた地下官邸最後の話を聞かせてもらった。
さて、ベルリン最後の日にベラスコはどうやってそこを去ったのか。それが次の話なのだが、話の中で私は驚異的なナチス・ドイツのいわば「地下組織連絡網」の存在を知った。そこには、ベラスコの超法規的な国境無視の手口が見えたのである。
戦後世界とはいうものの、実はいまでも敗戦とは無縁の、つまり現在もなおヒトラー・ナチズムの徹底した意志と行動が確実に存在しているらしい。まさに「和平は戦争の一時的中断に過ぎない」ようだ。
「本日は3月10日木曜日、次の日付けはまたそのときに。ハイル・ヒトラー」
ベラスコは立ったまま右手を上げ、大声でそう叫び、靴のかかとをカチッと鳴らしてみせた。
「なんとも馬鹿げた規則だった」と嘆きながら、ふたたびソファーに座り直した。ヒトラーと過ごした地下官邸内の習慣の一つを目の前で私に演じてみせた。
ベラスコは語る。
「地下官邸では、毎日睡眠薬とビタミン剤を交互に口にした。ディーゼル・オイルの強臭、騒音と振動、きかない換気装置、ひっきりなしに続く爆震、鳴り続ける電話の呼び鈴、混線する通信ラジオのがなり声、毎日少しずつガタが進んで立て付けが悪くなるドアのキシミ……24時間連続するその中で、頼るものはクスリしかない。しかし、量を過ごせば本当の病人になってしまう。敬愛するヒトラーと4月21日までその地下官邸で過ごした……」
一般に、4月30日がヒトラーとエヴァ・ブラウンの服毒自殺日と世間には公表されている。ベラスコがヒトラーの地下官邸に呼びこまれたのは3月、ドイツ第三帝国が敗戦に調印するほぼ2ヶ月前。神から死地を決められた恐怖とヒトラーとあの世に連れ立つ名誉の中にいた。爆撃で振動する前に、全身が震え続ける地下の4週間だった、とベラスコは地下官邸での体験を何回も繰り返し語った。

激戦の末、ベルリンの帝国議会のドームに
翻ったソ連の国旗(1945年4月末)
以下は、ナチス帝国崩壊寸前に、24人の大佐と高官とともにベルリンの地下官邸から脱出することに成功したベラスコの回想録である。
──────────────────────────────
ヒトラーが閣僚たちと階段の上に消えた3時間後、私は地上めがけて階段を駆け上がった。ベルリンの夜空は黒と赤に断続的に変化していた。砲撃で夜空は赤一色になる。ガレキの中を走ろうとしたら誰かが私を引っ張った。SSのワグナー大佐だった。こっちから走れ! そう叫んだ彼の横にオベルベイルもいた。
ワグナー大佐らのあとに続いてガレキの山をいくつも這ってこえた。暗闇を照らす赤い炎で死体と救助を求める人びとの姿が見えた。ベルリンの大通りは地獄だった。突然、誰かの手で車の中に引っ張りこまれた。そのメルセデスの革張りシートに身を沈めてはじめて安堵した。ワグナー大佐とオベルベイルも車内に飛びこんできた。ソビエト軍はベルリンを完全に包囲していなかった。南西部はヒトラー・ユーゲント(ナチス・ドイツの青少年団/1926年組織)や他の部隊が死闘を続けていたのだ。そのおかげでベルリン脱出行は、かないそうだった。
崩壊したビルのガレキに車はなんども阻まれた。そのつど車を降りて障害物を排除するか車で強引に飛びこえた。ベルリン郊外の空き地に車をいったん止めて、仲間と合流して脱出することにした。
しばらく待っていたそこを、まぶしいライトをつけた友軍護衛車の一団が通りかかった。先頭車だけがライトを点灯して、そのあとに無灯の車が続いていた。18台の護衛車だった。その最後尾につくことにした。
オベルベイルは眼鏡をなくしたと嘆いていた。車に引っ張りこんでくれたSS将校はシートに仰向けになって太めの腹を出してのびていた。ワグナーはケガで割れた膝を押さえていた。夜が明けてくるにつれて、われわれの車は南部の田舎道を走っているのがわかった。くしゃくしゃになった煙草が私のポケットにあった。車内の全員にすすめて一息ついた。煙草をもつ私の指先は震えたまま止まらなかった。18台の護衛車の乗員は全員が地下官邸のスタッフだった。
◆
田舎の道路を走行していたわれわれの一団に突然戦闘機が一機襲いかかってきた。英国空軍の偵察機で、爆弾を投下した。先頭車が被弾して破壊され頓挫したために、後続車は次々に追突して全車が停止した。全員が道路周辺を逃げまわったが、遮蔽物はなく被害は甚大だった。つづけて機銃掃射を見舞われたために、わずか1、2分のあいだに23人も死に、13人が重傷を負った。10台の車が走行不能になった。死亡者の遺体を道路脇に並べ、重傷者には救急用品と毛布を渡してふたたび車を走らせた。
私は生存を感謝しながら、昨日の地下官邸の場面を思いだしていた。そんなときに突然あの太腹の男、SS大佐フッカーが大声で喋りはじめた。
「ヒトラーはドイツ国民とともに死ぬ気だった。だがボルマンはヒトラーを生かして地下官邸から出した。ボルマンはヒトラーに無理やり薬を飲ませてベルリン脱出を命令した」
このおしゃべり男のフッカー大佐が、地下官邸でヒトラーの実務をこなす部署にいたのを思いだした。その点で彼の発言には信憑性があった。フッカーは車内の全員が黙りこくっていたせいかよけい雄弁になった。
「ボルマンが最後に地下官邸にきたとき、ヒトラーはまだそこに残る気だった。心の中の軍隊とともにベルリンを防衛するつもりだったし、死ぬ覚悟もあった。だが、ボルマンはそれを察知してヒトラーとエヴァを即刻地下官邸から退去させるよう命令した。2人は薬を飲まされたが、それがエヴァに致命的な結果をもたらした」
ひたすら喋りまくるフッカーの顔をワグナー大佐はにらみつけていた。ワグナー大佐はフッカーの知らない事情まで知っているらしかった。フッカーが非難したボルマンの態度に私は内心半信半疑だった。ボルマンの心変わりなど信じられなかった。
フッカーのお喋りは際限なくつづいた。
「ヒトラーの失敗は、英国軍事情報部が買収した予言者を信用したことだ」
予言者がどうやってヒトラーを信じこませたかを微細に述べた。そのことは英国軍事情報部員から私も聞いていた。だが奇抜すぎて重視しなかった。裏付けでもとっておけばよかったのにと後悔した。
だが、もしフッカーのおしゃべり通りだとすれば、私のスパイ活動歴の中で最大の失敗だったと悔やまれた。
◆
ドイツ横断に24時間かかった。
1945年4月22日の夕暮れになって、一団はババリア山脈の麓にある天然の要塞「ロタック・アム・エルヘン」にたどり着いた。SS将校ジンマーマンが豪語したとおり、なるほどこの要塞はいかにもドイツ軍の砦らしい堅固なものだと感心した。
車は要塞上部へ向かった。途中、自動小銃をもった衛兵になんどもチェックされた。厳しい哨兵(見張りの兵)の目を浴びながら、指定場所の高台の洞窟内の事務所に着いた。そこがナチス・ドイツの新しい、しかし最後の情報司令部になった。その日からおよそ一週間のあいだ、世界中に散在するSS情報員らと交信した。交信の内容は脱出指令が中心だった。膨大な数のコードネームが目の前を通過した。
われわれが指定したSS幹部と関係者の脱出ルートは二通り。一つはスイス国境の町フェルトキルヘ。他の一つはケプテン経由。後者ルートは問題があった。ケプテン・ルートにはSS情報部に協力した共産党員が1名いたのだが、その無能さがかねがね噂されていたからだった。些細なミスですべてが台無しになる厳しさを田舎の連絡員は知らない。それに敗戦の風が彼らに寝返りをもたらす可能性もあった。
その一週間後、ワグナー大佐から吉報をもらった。スペインヘの帰国命令だった。ただしその帰国は別の仕事をするためだった。ワグナー大佐は、私に帰国しだいTO諜報機関員に連絡をとり、特別な訪問者を受け入れる準備をするよう命令した。その特別な人物が誰なのかを尋ねたが答えはなかった。ただ一言、その人物がナチス政党を継承するためにも欧州から安全に脱出する必要がある、その脱出を助ける役目を君は使命として与えられた、とだけ言った。
その使命を命令する際の文書のコードネームは「ZAPATA」だとつけ加えた。私はこの作戦が充分に練られたものだと直感した。
◆
1945年4月29日、くたびれ果てた軍服姿のワグナー大佐とオベルベイルに向かって、「ハイル」と敬礼して要塞をあとにした。用意してくれたDKW車を運転してミュンヘンにある目的のガレージをめざした。道路は難民でいっぱいだった。幸い参謀本部が地元警察につくらせた道路案内地図のおかげで、難民を避けて時間を稼ぐことができた。
私の身分証明書は、ミュンヘンのダッチ・カイザー・ホテルのスペイン人シェフとなっていた。道中は怪しまれなかったが、町の給油所では困った。軍人なら即座に給油できたが、シェフでは相手にされなかった。給油を拒否されて困った私は、近くを通りかかったSSの警邏隊と思われる部隊の隊長に身分を明かして給油を可能にしてもらった。スパイの常識では非常に危険な芸当だった。スパイは味方の軍人にさえ身分を明かさないのが鉄則だったからだ。時間が惜しかったためにあえてした冒険だった。
スイス国境に近づいた。避難民の数はさらに増えていた。痩せ細った女子供までが持てるかぎりの家財道具を抱えて歩いていた。手もちのパンとバターを避難民の何人かに渡した。礼もいわずひったくっていった。
ビールが飲みたくなって、道路沿いの居酒屋に車を止めた。女主人らしい人物に注文したが、ビールは置いていないとすげなく断わられた。居酒屋商売ならこちらもまんざら知らないわけではない。女主人の背中を押して貯蔵庫の前までいって黙って立った。やむなく彼女はその中からチーズの小片を二切れ出して私の前に置いた。そのあとビールも出た。ふたたび車を走らせたが、エンジンの調子が悪くなって車は停止してしまった。瞬間的に怒りがこみ上げてきた。ビールを味わっているあいだに、あの居酒屋でガソリンを抜きとられたのだ。
時間が惜しい。車を捨て避難民同様に歩きはじめた。小さな駅があった。鉄道は動いていた。切符を買おうとして駅員に笑われた。誰も切符など買わないのだという。
そこからインスブルック行きの天蓋のない貨車に乗った。
◆
目的地フェルトキルヘまでの乗換え駅で待ち時間を利用して腹ごしらえをすることにした。駅前は傷病兵であふれていた。見つけたカフェに入って、適当な席に座った。隣席にカップルがいた。暗いカフェの中で、最初は気づかなかったが、カップルの男の方は地下官邸通路で若い士官らに愛国精神の高揚を説いていたあのSS将校ジンマーマンだった。ジンマーマンも私に見覚えがあるようだった。隣の婦人は妻のマリヤだと紹介した。
ジンマーマンはとんでもない頼みごとを私にしてくれた。ドイツとヒトラーに仕えることだけが全てだったが、それが失われた今となっては生きていくことはできない。自決するつもりだから妻マリヤの面倒をよろしく頼む、というものだった。
祖国ドイツに殉じる覚悟のジンマーマンに、私は承知したと答えた。妻の額にキスしたジンマーマンは立ち上がり表へ出て行った。マリヤも立ち上がり、テーブルの横で「神よ、彼がどこにいようと救ってやってください」と何度もつぶやいていた。ジンマーマンの姿が雑踏の中に消えるまでマリヤは立ち続けた後、テーブルの上に伏せて泣き崩れた。
ジンマーマンが自害したことを知ったのは、戦後2、3年たってからだった。
その夜、フェルトキルヘにいる我々のエージェント、カトリック神父のジョンに連絡した。私とマリヤは3日間神父宅に隠れた。神父は私とマリヤの結婚証明書をつくってくれた。夫婦者なら道中怪しまれずにすむからだった。私の名前はアンヘル・ドネイト、そして彼女はマリヤ・ピントになった。
5月1日、神父宅のラジオを聞いていると、ヒトラーが軍の司令官らと争って死亡した、と繰り返し伝えていた。
◆
我々2人は5月3日、スイスに入国した。
ここで私たちをスペイン本国へ送還してくれるよう訴えた。この後スペイン人専用の難民施設に入るまでに、いくつかの施設をたらいまわしにされた。5月7日、ドイツ軍が無条件降伏したという報道を聞いた。
難民収容所は手製の鶏小屋と変わらなかった。幅2メートル、奥行き3メートルほどの四方の地面に鉄柱を打ちこみ、金網で囲い、天井は藁をふいただけだ。木製の台にそのまま身体を休めるだけで他には何もない。便所は小屋の脇に穴を掘り、そこで数人が用を足す共同便所で、囲いも何もないために一晩中悪臭に悩まされた。
そこで難民事務局のインター・アライド・コミッションに話をつけて許可をとりつけ、ジェノバのホテルに警官監視付きでマリヤと移動した。ジェノバでバルセロナ行きの手筈を整えてから、マドリードにいる妻コンチータに出迎えるよう電報を打った。
6月下旬、バルセロナ港で出迎えたコンチータの車でマリヤと3人でマドリードの自宅にもどった。コンチータの強い勧めでマリヤは3年間私の家で暮らした。
■Part-2
ベラスコ家の居間は住まいの広さに比べて小さめだが、公園からは薫風が入ってくるし、話題には緊張感がみなぎるしで、飽きることなくくつろげる場だった。
このソファーでベラスコ夫妻とくつろぎの時間を味わったナチスの大幹部がいた。ヒトラーの片腕ボルマンとアイヒマンだ。
ボルマンは1946年1月6日に、アイヒマンは同年6月上旬に、それぞれ別々にベラスコ邸をひそかに訪ねている。両ナチス大幹部は戦勝国に指名手配され、ユダヤ人らの戦犯追跡機関からは懸賞金が掛かったお尋ね者たちだ。
以下は、ベラスコの回想録の続きである。
──────────────────────────────
元「TO諜報機関」のメンバーだったドイツ人フェリペが突然家に訪ねてきたのは、1945年12月のある晩だった。
フェリペと会うのは何年ぶりだろうか。マドリード脱出のさいの電話「MATILDA」を受けた男だ。フェリペは以前より痩せたようだが、背の高さが体格の変化を隠していた。フェリペはそのままナチスの工作員として現在も働き続けていると言った。私はうなづいた。戦後も戦前と変わらぬままSSの組織は形を変えただけで維持されていることを知っていたからだ。
フェリペは相当な活動資金をあずかっていた。ナチスが集めた寄付金は天文学的な金額だった。その資金でフェリペは組織活動の経費をまかなっていた。主体業務はナチス大幹部の国外移動を手助けすることだった。
40歳をこえたとボヤきながらフェリペは、持参した小型封筒をよこした。ワグナーSS大佐からの待ち望んでいた「仕事」かもしれない。ロタック・アム・エルヘンの要塞で大佐からスペインヘの帰国命令を受けて以来の命令だろう。小型封筒をもって書斎に入りアイロンをテーブルの上においた。いつもの順序どおりに大型封筒を用意して、肝心の小型封筒をそこに入れ、霧吹きで外側の大型封筒を濡らした。封筒の表面が濡れているあいだに糊しろの部分にアイロンを当てる。こうすれば、封筒の口は破損せず、閉じたときと寸分たがわず中身を改められる。SSスパイ時代がよみがえった。
封筒に入っていたメッセージはスペイン語で書かれていた。
「1月1日から15日のあいだ、マドリードの自宅で特別な訪問者を待て。君はその人間を知っている。この手紙を持参した男が君の自宅に連れていく。ZAPATA」
ワグナー大佐が教えてくれた「ZAPATA」のコードネームだ。私はホッとした。ナチスの重要人物がまだ生きている証明だからだ。むろんフェリペにメッセージの内容はわからない。
◆
1946年1月3日の深夜、フェリペがふたたび訪ねてきた。例のメッセージにあった「重要人物」を同伴していた。深緑のソフト帽を深くかぶり、黒色の外套の襟を立てたままだから顔がよく見えない。フェリペは、フレッチャーマン氏だと紹介した。握手した瞬間にその人物が誰かわかった。マルチン・ボルマンだ。
部屋に入るとフェリペは、ボルマンに聞こえないように私の耳元で、フレッチャーマンが誰なのか、と尋ねた。私はフレッチャーマンだと答えた。次に、彼がどんな地位の人物なのかを聞いた。そこで、ヒムラーの部下ではなかったかな、ととぼけた。フェリペは肩をすくめたあとしばらくして立ち去った。

マルチン・ボルマン
ボルマンの姿を私が最後に見たのは、例の地下官邸で4月21日だったが、口をきいたのは、ボルマンがわが家に訪ねてきたときが最初だった。目の前のボルマンは以前よりも痩せていた。二重アゴは頬の筋肉と一緒になくなっていた。前頭が部分的に禿げてギリシャ鼻には整形が施されていた。輝いていたのは眼光だけで、それも異様な明るさに見えた。
フェリペを帰してボルマンを居間のソファーに案内し、スペイン産ブランデーを勧めた。
「君は私を覚えているかね」
ボルマンはそう尋ねた。私がうなずくと同時に、
「そう私はフレッチャーマンだ、いいかね君」と念を押した。
「ならば、私はドクター・ゴメスです」
私も即座にそう答えた。ボルマンのスペイン語はひどいものだった。
「ここで長居するつもりなら、スペイン語を上達させてください」
「長居をするつもりはないが、君の忠告どおり少し勉強しよう」
ボルマンはそう答えた。
ここまでピレネー山脈をこえて陸路できたのか、それとも民間航空機できたのか、あるいはUボートでガリシア海岸沖まできて車を乗り継いできたのか、という私の問いにボルマンは答えなかった。
その代わりに、開封された白い封筒を渡してよこした。裏表とも何も書いてない。
そのメッセージの紙面にも「ZAPATA」の文字があり、なぜかヒトラーのサインもあった。文面はボルマンをバルセロナの南およそ15キロほどにあるコンドール城に連れていくよう指示していた。その古城は地中海に面した閑静な地域にあることを私は知っていた。
ボルマンは3日間わが家の居間で過ごした。
◆
1月6日、私は新車のクライスラーを用意してボルマンを乗せ、マドリードをあとにしてバルセロナに向かった。なるべ人目につかない道路を選んだために8時間の長旅になった。コンドール城には50歳すぎの漁師風の男マカリオが待っていた。
敷地総面積が数千坪ほどの城郭内には、戦前から連絡センターとして使われていたいくつかのコテージがあった。人目につかない城の塔の中に案内された。マカリオは快適ではないが一番安全な部屋だと言った。簡素な空間だったが、床にはカーペット代わりに白い砂が厚めに敷かれていた。ボルマンはマカリオに食事を出すよう命令した。私はそのままマドリードにUターンすることにした。ボルマンは身体を鍛えておくようにといい、長い旅に出るからとつけ加えた。マドリードにもどった私はその後3ヶ月間、誰からもなんの連絡もなかった。
◆
1946年5月1日、フェリペがあらわれた。受け取った封筒の中のメッセージは簡単なものだった。5月7日にガリシア海岸のビラ・ガルシアにボルマンとともに到着するようにと書いてあった。その場所は、以前にマドリードから逃亡したときに目指したイベリア半島の北西海岸にある寒村だ。Uボートが待っているのだろう。そこからどこへ向かうのだろうか。
5月3日、妻のコンチータに長期旅行になるかもしれない旨を告げ、バルセロナに向かって8時間の長距離ドライブに出た。コンドール城に到着して、ボルマンと再会した。「スペインは素晴らしかったが、去るのは辛くない」とボルマンはワインを傾けながら流暢なスペイン語で喋った。
この12週間でナチ党の再建と将来構想を固めたとボルマンは語り、その行動初日を祝って3人で乾杯した。
「ナチ党とその指導者のために、ハイル・ヒトラー!」
暖炉の炎が石壁にゆらゆらした3人の乾杯する影を映した。敗戦国ナチス・ドイツはここにはなかった。私は格別興奮して震えた。ボルマンがハイル・ヒトラーと叫んだこの乾杯は、ヒトラーの生存を意味するからだった。
◆
スペイン大横断の旅がはじまった。青い安物の上着に綿シャツ姿のボルマンと車中で交互にコニャックをまわし飲みして喉を湿らせながら固いパンをかじった。車から降りてレストランや居酒屋に立ち寄るのは危険だったからだ。人目の少ない道を選んで車を走らせたので、給油所を探すのも厄介だった。
コンドール城を出て地中海沿いにドライブした。グラナダ、セビリアを抜けてポルトガル国境に近いメリダまで走って、ホテルに一泊した。2人ともパスポートはもっていなかったが、身分証明書だけで部屋は確保できた。ホテルヘの投宿は危険だったが、長旅の疲れが危機感をいささか麻痺させたのかもしれなかった。
翌日も暑い太陽を浴びながら、目的地まであと100キロほど手前のポンフェラーダまでドライブして二泊目を過ごした。旅の最終日は最悪だった。荒れた山道の凸凹を避けて走りながら、身体中を車内のあちこちにぶつけた。最終目的地ビラ・ガルシアでは、漁師でSSのエージェント、マルティネスが夕食を用意して待っていた。
マルティネスは小さな封筒を私に手渡した。ただし開封するのは沖合いの船上でしてほしいとつけ加えた。私は疲れも重なったせいで激怒、その理由を追及した。だが命令だからとマルティネスは素っ気なかった。
私たちはどこに向かうのかを知りたくてウズウズしていた。ボルマンは自分も知らないが、仲間たちを信頼しようとだけ答えた。私は気をとり直してボルマンと一服した。スペインでの最後の煙草の味だった。漁船に乗る前に、車をマドリードにもどす手配をした。コンチータ宛に予想以上の長旅になるかもしれないと書いたメモも一緒に託した。全長27、8メートルの漁船は快調に沖合い2マイルの位置まで走り、停船投錨した。周辺に別の船舶がいないかを確かめた。
風が出て揺れが大きくなった船上でマルティネスがポケットから紙に包んだ物を私に差し出して、あなたが待ち望んでいたものだ、ただし開けるのはあとにしてほしいと言った。私はかまわず包みを開けようとしたが、ボルマンがあとで開けるようにと命令した。
何かが漁船に当たった。ドイツ海軍水兵が2人乗ったゴムボートだった。ボルマンとともにそのゴムボートに乗り移り、漁船のマルティネスらに別れの手を振った。揺れるボートの目の前に鉄のかたまりが見えた。船体の周囲が波の白い泡に包まれていた。懐かしいドイツ海軍のUボートだった。船腹には「U−313」と書かれていた。
客をハッチの中へ迎えてまもなく、Uボートは潜水して南下を開始した。3000マイル、18日間ノンストップの航海がはじまった。2人の客以外は乗務員だけだった。
1946年5月7日午前5時10分、ナチス・ドイツが無条件降伏してから1年目が過ぎていた。
■Part-3
ナチス再興を決意した男たちを乗せたUボートは、イベリア半島北西から南下した。ドイツ敗北からほぼ1年を経たその日の早暁、ベラスコとボルマンの長い航海がはじまった。

ドイツ敗北の翌年1946年5月に
ベラスコとボルマンはUボートに乗って、
イベリア半島北西から南米アルゼンチンまで
18日間ノンストップの航海をしたという
以下は、ベラスコの回想録の続きである。
──────────────────────────────
われわれは狭い個室の二段ベッドを分かちあった。Uボートの個室にひとまず腰をおろし、マルティネスから受け取った包みを開封した。船内であらためるようにとマルティネスが強くこだわったあの包みだ。なぜ船内でとこだわったのだろう。
船内で確認できたのは、Uボートの船体番号313と艦長の名前がフィという短い苗字だということだけだった。
Uボートは、どこに向かうのか。マルティネスから受け取った包みの中身が楽しみだった。ナチスがふだん使っていない封筒が包みの中から出てきた。スペイン語で書かれた便箋の文章は簡単なものだったが、まずUボートの目的港がわかった。南米のアルゼンチンだった。手紙にはこう記されていた。フレッチャーマン(ボルマン)に南米の生活様式、政治状況、それにスペイン語を教えるようにと。
包みの中に2冊のパスポートがあった。ボルマンと私のだ。スペイン東北のサンセバスチャンにあるアルゼンチン領事館発行になっていた。私のパスポートにのみ別紙が貼ってあり、このパスポーートは一時的で緊急用につき、到着国で正規のパスポートに変更するよう指示してあった。
ボルマンのパスポート名はルイス・オレガ、私はアディアン・エスパーニャ。用箋には例の「ZAPATA」のサイン。包みの中の最後の用箋には暗号文が書かれていた。私には解読不可能でボルマンも同様だった。艦長に渡したところ、それはUボートの航海指令書だという。
マルティネスが、包み紙を船内で開けるようにこだわった理由がわかった。ボートの行く先に対して私が拒否できないよう配慮したためだった。
◆
ポルトガル沖で1時間浮上した。その間に木箱が19個積みこまれた。私はカネと期待したが、なんと食料品だった。旅の長さは勉強時間をもたらしてくれた。スペイン語のレッスンがはじまり、アルゼンチンなまりのスペイン語が個室の中を飛び交った。勤勉なドイツ人「生徒」ボルマンは、アルゼンチンの地理と社会環境をむさぼるように学んだ。
私がボルマンから知りたかったのは、ヒトラーの安否。それを察してくれたのか、ボルマンは地下官邸の最後の場面を少しずつ説明してくれた。
ヒトラーを幇助して脱出が成功したからこそ、自分がこのボートに乗っていられるのだ──つまりヒトラーは第三帝国の象徴ゆえ、地下官邸では死なせてはならない人物だったのだ、とボルマンはヒトラーの生存価値をまず強調した。
ボルマンの話によれば、地下官邸のヒトラーをひとまずロタック・アム・エルヘンの要塞に移した。エヴァは地下生活中の投薬がたたって死んだ。ヒトラーとエヴァがガソリンを浴びて焼身心中したとする物語は、ボルマンの創作だった。世界中にその「事実」を信じこませた。
実際は、ボルマンが信用する部下数人を使ってロタック・アム・エルヘンの要塞からさらにドイツ領土内を横断して船でヒトラーをノルウェーに移した。ヨーロッパからの脱出準備を2人の部下が整えるまでの間、ヒトラーをノルウェーの寒村に待機させた。ヒトラーの現在の居場所は話せない。連合軍はヒトラーの「自殺」に満足したろう。ボルマンは手際よく運んだと自慢気に語った。
私が、世間ではボルマンも死んだと思いこんでいるだろうとたたみかけたところ、ボルマンは笑いながら身を乗りだして、「ボルシェヴィキの戦場で死んだと伝えてくれ」と熱い口調で言った。
一瞬私の胸には冷たい恐怖心がわいた。知りすぎた男の末路が頭に浮かんだのだ。私がそれを口に出すと、ボルマンは笑って手を横に振りながら私を「囚人」と呼んだ。囚人はむろん冗談だった。私のことを「ナチスの同志で、忠実なメンバーで、友人だ」とほめ言葉を並べた後で、「私の逃亡の秘密を話さないように」とつけ加えた。私に異存はなかった。
◆
うねりと白波に操まれながら、Uボート「U−313」はアルゼンチンのラ・ブラタ河口沖でいったん浮上した。
われわれの上陸地点はパタゴニア地域のプエルト・コイの港付近だ、とそのときはじめてフィ艦長から知らされた。上陸地点は、潜水艦と陸上との無線のやりとりで決まったようだった。陸地が見えた時点で、ベラスコは、ただちに下船させよと艦長に詰め寄ったが、無理だった。「U−313」の一挙手一投足を決める事実上の艦長は陸上にいたからだ。
陸上からの無線連絡員はロドリゲスと名乗っていた。私はその名前に覚えがなく、不安にかられた。ふだん偽名(コードネーム)を自在に使うプロスパイである私も、なぜか相手の名前にこだわった。上陸寸前の緊張感が、プロスパイの自覚まで失わせたのだろうか。
1946年5月25日早朝、ボルマンと私は海岸の岩場にかろうじて上陸した。強風でゴムボートが何回も転覆しそうになった。密室生活の中で渇望していた空気だったが、強すぎる風は悪魔だ。
無線で応答してきたロドリゲスと名乗る男は、2台の車と7人の人間を連れたローマ・カトリックの神父だった。実はこの人物は、かつて私と仕事で組んだことのあるナチスの情報員ボガミスであることがわかった。アディアン・エスパーニャが私であることを知った「神父」は、再会を懐かしんだ。
Uボート「U−313」は白波をかぶりながら、次の寄港地ブエノスアイレスに向けて去っていった。
◆
ボルマンと一緒に上陸した私は、アルゼンチンのスペイン大使館でパスポートを切り替え、空路マドリードに舞い戻った。そして、南米への第2の逃亡者を扱うようにとの指令を携えたスイスからの修道士を自宅に迎えた。
スイスからきた修道士は、クレメンスという人物を南米に脱出させたいという。私は、そのクレメンスなる人物と会ったうえで返答することにして、修道士とスイスに向かった。修道士はスイスのフライベルグから2、3キロ離れたクレメンスの潜伏先に私を案内した。
クレメンスなる人物とは会ったものの、彼が誰なのかはわからなかった。クレメンスは、自分が連合軍に追われていて、助けが欲しいとだけ言った。彼は、バチカン教皇庁が特別発行したパスポートを持っていた。このパスポートは戦後、多数の避難民のためにバチカンが発行したもので、欧州内の移動にのみ使用が許されたものだった。名前はディデールとなっていて、クレメンスではなかった。私はその理由を尋ねることもしなかった。クレメンスことディデールを連れて、スイスから空路マドリードの自宅に戻った。
マドリードのアルゼンチン大使館でクレメンス名義のパスポートを入手した私は、クレメンスを空路ブエノスアイレスヘと送りだした。マドリードのバラハス空港で別れる寸前に、クレメンスは自分の本名はアイヒマンであると打ち明けた。それは1946年6月3日のことだった。


アドルフ・アイヒマンSS中佐
■Part-4
ベラスコは、その後メキシコに渡り、アメリカとの国境近くのシゥダードフワレスという小さな町に住みついた。そして、「カルシア・ヴァルセッカ」という新聞社で、土曜特集版を担当する編集委員として働いた。むろんそれは仮の姿で、実際はナチスのエージェントとして、情報集めをおこなっていたのである。
1957年6月、南米のボルマンから会議に出てほしいとの知らせがベラスコに届いた。場所はアンデス山中の農場。ベラスコはボルマンからの突然の報に驚き、ドイツのナチス地下本部で安全を確認してから決断することにした。
当時ベラスコは、西側情報組織から徹底的にマークされていた。中南米を含む最大の秘密情報機関の頂点にいたベラスコは目立つ。おおっぴらな移動は危険この上なかった。

ベラスコは、メキシコからドイツに飛んで、地下のナチス本部で安全な旅行を保障させることにした。西側情報員にベラスコの追跡を断念させるために、ベラスコがメキシコのCIAに情報を流す代わりに追跡しない確約をとる案が検討された。CIAにはメキシコの共産主義者グループによる米軍メキシコ基地へのテロ攻撃計画の詳細を渡す。そのかわりCIAはベラスコの旅を追跡しないと約束する。この取り引きは成立した。
だが情報機関の目はCIAの他にもある。ベラスコは闘牛サーカス団の巡業を目隠しがわりにする案を考えだした。団長ベラスコは、元著名な闘牛士。息子のフェルナンドは敏捷だが素人そのもの。なにか目玉にする売り物はないか。ベラスコは恰好の華を見つけだしてくる。闘牛士志望の女性ローラだ。彼女を看板闘牛士に仕立てて、一座を組んだ。女闘牛士を呼び物にしたショーだ。
ローラをローラ・モンテスという芸名に仕立ててしまうスパイ業界人には、人間の姓名などそこいらの石ころと同じに思っている。たとえば、ギレルモ、ゴメス、レカ、ディデール、アディアン、これらは世界にたった一人しかいないベラスコのコードネーム。人間の姓名など記号の1つでしかないのである。
以下は、ベラスコの回想録の続きである。
──────────────────────────────
メキシコシティーで道具を買いそろえ、一座を整えて、アンデスに向けて出発した。エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、パナマと、細長い中米の回廊を闘牛ショーの一座は巡業をつづけた。女闘牛士一座アイデアは大当たりした。
だが、その舞台裏は緊張の連続だった。たとえば、前日にパナマ市でナチス機関と連絡を取り合ったうえで、いついつにはエクアドルに向かうようにと指示される。巡業先はナチスの秘密情報部が前日に知らせるまでわからない。文字どおり、明日の行く先も知れない旅まわりの一座なのである。
中年をすぎた私も団長兼闘牛士として闘った。ショーが終われば、明日殺す牛の仕入れに駆けずりまわった。ほとんど寝る間もなく、しかもその間に地下組織と連絡をとって先へ進むという辛い毎日に、座員はみなへきえきしたようだ。
やがてアンデスまでの悪路がトラックを拒みはじめた。トラックをあずけて全員をそこに残した私は、単身ロバにまたがって危ない渓谷をいくつもこえて進んだ。壊れそうな木製の細い橋を渡るさいはロバの背中にしがみついた。人里離れた場所だったから、ダンディである必要はない。
◆
山中の深い場所に丸太小屋があらわれて、数十人の現地人が私をとり囲んだ。エクアドル人と称する農場主と小作人のインディオだった。
「会議に出席するためにきた」と伝えた私に、農場主は会議など開いていない、という。来た道を戻りかけたとき、農場主は一杯飲んでいかないかと誘ってくれた。地酒を1、2杯飲み干して去ろうとすると、欧州人と思われる男が付近の小屋からあらわれて、私の名前を確認したあと小屋に案内した。
小屋の2階の部屋に通されるなり私はナチス式の敬礼をした。
部屋の真ん中にテーブルクロスをかけた大型テーブルがあり、その周囲に7人の男たちが座っていた。そして、ボルマンがいた。
「老けたなアンヘル」、ボルマンは懐かしそうに声をかけてきた。
ボルマンは例のUボートの一件以来、私を監視しつづけ、情報活動の経歴と実績を徹底検証したと言った。その結果はボルマンらを大いに満足させたとも言った。
だが私は冷めていた。これまで張り切りすぎた。もはや昔のような活動はできない。これからは、家族と静かに暮らしたい。私はそんな断わりの言葉をふところにしてアンデス山中にやってきていたのだ。
ボルマンと6人の男たちは、私に矢つぎばやに質問をあびせた。ラテン・アメリカ社会の地下から見た状況や、革命を引き継ぐための知識、社会の成熟度などについてだった。
喋り疲れた私は、一段落したあとで、ナチスとの決別をボルマンに告げた。ボルマンは驚き、ラテン・アメリカ全域にヒトラー・ユーゲントと同じ青年組織を完成させたこと、ナチスの復活が目前にあることなど、明るい材料を私に差しだして、ナチスからの離脱を思いとどまるよう説得を始めた。
それに対して私はただ一言「疲れてしまって情熱を失った」とだけ述べた。20年間ナチスに協力してきた私の「店じまい」宣言のつもりだった。
◆
私は、会議後の食事の席でボルマンに小声で質問をぶつけてみた。
「ヒトラーはどうしているか?」
ボルマンはそれに答えず、肩をすくめ、ただ「ヒトラーをドイツに凱旋帰国させたかった」とだけ言った。
「では死んだのか?」
この問いかけに、ボルマンは沈黙を返してよこした。
そして、これまで報道機関の話題に触れることを嫌っていたボルマンが、珍しく欧州での自分の話題の有無について私にたずねた。私は、「ボルマンの話題は最近ではめっきり減った」と答えた。ボルマンは、「それはよいことだ」と寂しそうに繰り返していた。
私はボルマンに別れを告げてアンデス山中の農場をあとにした。ロバにまたがって危ない渓谷をいくつも渡り、トラックをあずけた村に戻った私は、一座を解散してメキシコのわが家にもどった。そして、その翌朝、スペインヘの帰国を手配した。
── 当館作成の関連ファイル ──
◆「ヒトラー逃亡」説の実態 ~ヒトラーの死にまつわる数々の疑惑~
|
第4章
|



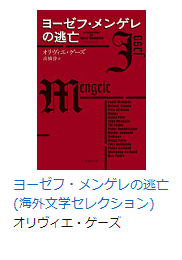
Copyright (C) THE HEXAGON. All Rights Reserved.