| ヘブライの館2|総合案内所|休憩室 |
No.a6fhd600
作成 1998.6
| 第1章 |
ユダヤ教の内面化が促進された |
|---|---|
| 第2章 |
ユダヤ神秘思想「カバラ」の発展
|
| 第3章 |
カバラの大巨人ラビ・ルリアの
「ルリア神学」誕生 |
| 第4章 |
ユダヤ教最大のメシア運動
「サバタイ・ツヴィ運動」 |
| 第5章 |
「サバタイ・ツヴィ運動」から
「ハシディズム運動」へ |
| 第6章 |
フランク派ユダヤ人の
倒錯的なメシア運動 |
| 第7章 |
本質的に「シオニズム」と
「ユダヤ思想」は別物である |
| おまけ |
ユダヤ人にとって「メシア」は
いろいろな形をとってあらわれる |
|---|
↑読みたい「章」をクリックすればスライド移動します
■■第1章:対ローマ戦争敗北でユダヤ教の内面化が促進された
●ユダヤ教徒の「メシア運動」とユダヤ神秘思想「カバラ」は、切っても切り離せない関係にある。
カバラによれば、天国に秘め置かれている“メシア(救世主)の魂”が地上に“人の子”として現れ、全ユダヤ人を救済するのは、地上の悪が絶頂に達したときであるという。
そこで問題となったのが、その時期であった。
●ユダヤ民衆は、紀元前からその時期は目前に迫っていると考え、熱心にメシアを待望したが、とりわけユダヤの地がローマ帝国から派遣された代官によって治められるようになった紀元6年以後は、ますますメシア待望熱が高まるようになった。
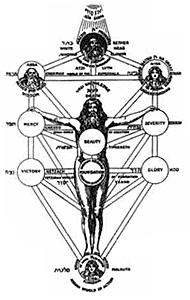
ユダヤ神秘思想「カバラ」によれば、
天国に秘め置かれている“メシアの魂”が地上に
“人の子”として現れ、全世界のユダヤ人を救済する
のは、地上の悪が絶頂に達したときであるという
●一刻も早くメシアを引き寄せ、ユダヤ解放を成し遂げなければならないという切迫した思いは、ユダヤ愛国者を「ゼロテ党(熱心党)」に結集させ、そのまま対ローマ戦争へとなだれ込ませた。
紀元66年から紀元70年にかけての「第一次ユダヤ戦争」である。
●しかし、当時のローマに立ち向かうには、ユダヤ軍はあまりに非力だった。
彼らの砦は次々と陥落し、ついにはエルサレムの「ソロモン第二神殿」まで破壊、炎上した。この破壊後に残ったわずかな神殿遺跡が、今日の「嘆きの壁」である。

ティトゥス(紀元39~81年)
父ウェスパシアヌス帝の命を受け、
エルサレムを占領し、徹底的に
破壊した(紀元70年)


(左)「ユダヤ戦争」の勝利記念として建立されたティトゥスの凱旋門。ローマに現存する最古
の凱旋門で、アーチの内側には隙間なくレリーフが施されている。右はアーチ内側にある
レリーフの1つで、ユダヤ教の象徴的存在である七枝の燭台(メノラー)が見える。
ティトゥスは「ソロモン第二神殿」の宝物を戦利品とし、反乱軍の指導者を
捕虜にしてローマに凱旋した。エルサレムは「嘆きの壁」を残し、
徹底的に破壊された。この戦争のユダヤ人犠牲者数は
60万人とも100万人ともいわれている。
●けれども、ユダヤ人のメシア待望熱は衰えることはなかった。
「第一次ユダヤ戦争」から約60年後の紀元132年、ユダヤ人は「星の子」を意味するバル・コクバを先頭に押し立てて、再びローマに反旗を翻した。
ユダヤ民衆はバル・コクバをメシアと信じた。バル・コクバがメシアと信じられた最大の理由は、ユダヤ教ラビの中でも最も偉大なラビのひとりに数えられているラビ・アキバ(アキバ・ベン・ヨセフ)が、バル・コクバを正式に「メシア」と認めたからである。


(左)ユダヤ教の律法学者ラビ・アキバ (右)バル・コクバ
ユダヤ教のラビの精神的指導者であったラビ・アキバによって、
そのカリスマ性を見いだされたバル・コクバは、ラビから「星の子」の
メシア称号を授けられた。ユダヤ教の聖職者たちは彼を全面的に支持し、
第一次ユダヤ戦争の問題点を徹底的に研究した上で、バル・コクバを
革命軍のリーダーにして再びローマ帝国への反乱に踏み切った。
●バル・コクバのもとには、日毎に民衆が結集し、その数は50万人以上に膨れ上がった。
紀元132年、バル・コクバはこの大勢力を率いて革命軍を立ち上げ、当初は日の出の勢いで戦勝していった。しかし、戦闘の長期化とともに、物量・人材で劣るユダヤ勢は各地で苦戦を強いられるようになり、ひとつ、またひとつと拠点を撃破されていった。
そして紀元135年、ローマ皇帝ハドリアヌスの命を受けて反乱軍殲滅に乗りだしていた勇将ユリウス・セウェルスとの戦闘により、バル・コクバはあえなく戦死。ラビ・アキバも処刑されて、「第二次ユダヤ戦争」(バル・コクバの乱)は悲惨な結末を迎えたのである。
※ この反乱で戦死したユダヤ人の数は58万人といわれ、多くの高官たちが死刑となり、生き残った1万人のユダヤ人捕虜は奴隷としてローマ帝国各地に売り飛ばされてしまったという。
●ちなみにハドリアヌスは、紀元130年にエルサレムをローマ風の都市に再開発して、自らの氏族名アエリウスにちなんで「アエリア・カピトリーナ」と改称し、「ソロモン第二神殿」の跡地にローマの神である「ジュピター(ゼウス)」を祭る神殿を建設した。
紀元132年にはユダヤ人の「割礼」を時代遅れの野蛮行為として禁止し、これを破った者には死罪をもって報いるとの強硬な姿勢を示した。
※ この皇帝の「反ユダヤ政策」はユダヤ人たちの大反発を招き、上述の「バル・コクバの乱」が勃発したのである。

ユダヤ教を徹底的に弾圧した
ローマのハドリアヌス皇帝
(紀元76~138年)
ハドリアヌスは治世開始の当初はユダヤ人に対して温厚な
顔を見せていた。しかし晩年になると、属州ユダヤの不安定要因は
ユダヤ教とその文化にあると考え、ユダヤ的なものの根絶を図るようになる。
彼は「ユダヤ暦」の廃止を命じ、律法の書物を神殿の丘に廃棄して埋め、多くの
ユダヤ教指導者を殺害した。また「ユダヤ州」を「シリア・パレスチナ州」
に変名し、この地から「ユダヤ」の名前を消し去ったのである…。
●「バル・コクバの乱」以降、数百年にわたって、ユダヤ人は聖地エルサレムに入ることはもちろん、廃墟を遠望することすら禁じられた。もし禁を破ってエルサレムに入る者は、死刑を覚悟しなければならなかった。
また、ローマ帝国は、神殿の表土まで削り取って捨て去り、エルサレム南門には、ユダヤ人が忌み嫌うブタの彫刻をほどこして、彼らの信仰を愚弄したのである。
●ユダヤ人が神殿跡地への入場を許されるようになったのは、ようやく4世紀に至ってからである。ただし、それが許されるのは、聖地エルサレムがローマによって破壊された記念日ただ1日であり、ユダヤ人は屈辱に泣き続けた。
「嘆きの壁」は、このときからユダヤ人の燃えるようなメシア待望と、民族的怨念を吸い込み続けて今日に至っているのである。


エルサレム旧市街の神殿の丘に位置する「嘆きの壁」
壁の全長は約60mで高さは約21m。壁の石の隙間には、
ユダヤ教徒の祈りの言葉が書かれた紙切れがぎっしり詰まっており、
夜になると夜露がたまり、壁に生えたヒソプの草を伝って滴り落ちる。
それが数々の迫害や苦難を受けて涙を流すユダヤ人のようでもある
ことから、「嘆きの壁」と呼ばれるようになったという。
●メシアニズムに導かれた紀元70年と紀元135年の両次にわたる対ローマ・ユダヤ戦争は、かくして悲惨な結末のまま幕を閉じた。
以後、ユダヤ人は、欧州、中東、アフリカの各地に離散し、それぞれの地域にユダヤ・コミューンをつくっていく。そして異教徒との宗教的交わりを断ちながら、ひたすら内面的にメシア登場の時を待つ態勢に入ったのである。
◆
●もはや偉大なカリスマ、バル・コクバが指導したような大規模な革命運動は、ユダヤ人には起こせなかった。
その間、世界帝国ローマは、民心掌握とユダヤ教弾圧のために、キリスト教を公認し(313年)、ついで国教化(392年)した。
ユダヤ教から見れば、キリスト教は、ユダヤの遺産である『トーラー(モーセの五書)』やメシア思想などを盗んだ盗法者にほかならない。加えてキリスト教は、イエスをまだ到来してもいない「メシア」とし、世界中に勢力を拡大していっている……。
一体これら世の中の動きは自分たちにとって何を意味しているのか?
なにゆえに自分たちは苦しみを味わなければならないのか?
●ユダヤ教徒たちは、各地のコミューンにこもりながら、「神」が歴史に刻み込んだこれらの謎の解明に向かった。
剣ではなく、信仰と思索が、彼らの生き延びる武器となった。
かくして、アブラハム、モーセ、ソロモン、アキバと連なる秘教の伝統の内面化が、古代から中世にかけて、強力に押し進められていくことになった。
彼らの中で、「神」の真意を探るユダヤ神秘思想「カバラ」は発展し、「神の国」を顕現させるメシア(救世主)到来が希求されていったのである。
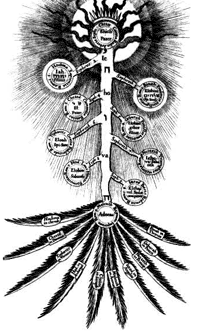
■■第2章:ユダヤ神秘思想「カバラ」の発展
●ユダヤ教の神秘思想が「カバラ」という呼称で統一されるようになったのは、歴史的には中世に至ってからのことである。そこに至るまでの間、カバラの伝統は、キリスト教が支配する世界からは、完全に隠されていた。
しかし、12世紀に至って北スペインやフランス南東部のプロヴァンス地方にカバラについての秘義を語る者が現れだすと、以後、カバラはヨーロッパ世界に急速に広まっていった。その際、特異な神秘思想を展開するカバラ奥義書が、数多く執筆・編纂されていった。
●この時期に登場したカバラ奥義書が展開したのは、主に『トーラー(モーセの五書)』のカバラ的解釈であり、『トーラー』の背後に見え限れする『原トーラー』の追求だった。
カバリストたちは、「創世記」や「出エジプト記」などの記述を特別な数字に還元したり、神秘的な操作による文字の並べ換えなどによって、表面的な意味の背後に隠された叡智を探りだすことに没頭した。
また、神的創造世界のマンダラであるセフィロト図のオカルト解釈を通じて、人類文明の過去・現在・未来の諸相を探求し、来るべきメシア(救世主)時代の年代計算に情熱を傾けていった。
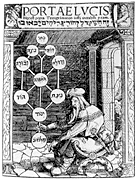
●現在、カバラには三大教典があるが、そのうちで最も古いものは『イエツィラの書』(別名『形成の書』/紀元3~6世紀に成立)で、残りの『バヒルの書』(別名『光明の書』)と『ゾハルの書』(別名『光輝の書』)はこの時期(12世紀~13世紀)に成立した。
●『ゾハルの書』の著者である、スペインのラビ・シメオンによって、カバラはユダヤ教唯一絶対の神秘思想としてまとめあげられた。彼が13年間の洞窟生活の間に、神からの啓示を受けて書いたとされる『ゾハルの書』は、『タルムード』以後のラビ文学の中でひとつの規範的テキストとなり、数世紀にわたって『旧約聖書』と『タルムード』に比肩する地位を維持することになった。『ゾハルの書』の出現によって、ユダヤ教はいわば第3の絶対的聖典を持ったことになったのである。(第1の聖典は『旧約聖書』で第2の聖典は口伝律法の『タルムード』である)。
以後、ユダヤ神秘思想はこの『ゾハルの書』に集約されたカバラ思想を中核として展開していく。
●こうしてユダヤ教が、霊的・内面的な方向で極度に洗練されていった間にも、ユダヤ人に対する過酷な迫害は続いていた。
他宗教を認めないユダヤ教の閉鎖性や、強固な選民思想は格好の非難の対象になったし、カバラに対する盲目的な恐れは、ユダヤ人を魔術師とする強固な偏見を育てていった。
キリストを売ったユダヤ人、金に汚いユダヤ人、悪魔と交渉しているユダヤ人といった、いわれのない偏見から、とくに欧州圏では、ユダヤ人はしばしば虐殺や略奪、また、異端審問の名のもとに行われる拷問の餌食となった。
そうした中で、メシア待望の気運を盛り上げていったのは、カバリストたちだった。
●カバリストは、預言者たちの黙示文学に描かれたような暗黒世界が、いよいよ全地を覆いだしてきたと主張し、虐げられたユダヤ民衆の終末意識をあおったが、同じことはヨーロッパのキリスト教団でも起こっていた。
たとえば画家たちは、好んで黙示録的情景を描き、偽キリストや最後の審判を描いた。占星術師の中には、ドイツのヨハン・シュトフラーのように「1524年にノアの大洪水の再来がある」と唱える者もいたし、実際、彼の言葉を信じて箱船を造った有力者もいた。
戦争、内乱、一揆、流星などによる恐怖は人々の終末感をいっそうあおったが、こうした恐怖心を増幅しつづけたのは、宗教的権威のおどろおどろしい託宣だった。
たとえば15世紀に現れ、キリスト教を大改革したマルティン・ルターは、あと数年でこの世は終末を迎え、「聖書は完全に実現されているだろう」と唱えた。また、彼の弟子のひとりは、ルターの思想をより過激に展開して、16世紀初頭、地上から悪の勢力を一掃するための「メシア的革命軍」を組織したのであった。

マルティン・ルター
(1483~1546年)
■■第3章:カバラの大巨人ラビ・ルリアの「ルリア神学」誕生
●かくして、キリスト教とユダヤ教とを問わず、終末観が世界を支配したこの時期、ユダヤ教に、それまでの神秘説を根底から塗り替えるカバラの大巨人が現れた。
1534年に聖地エルサレムで生まれ、7年間、徹底した隠者生活を送りながら、自在に魂を天界に飛ばす瞑想を続けてカバラの奥義に達したとされる、ラビ・ルリアである。(正確な名前はラビ・イツハク・ルリア・アシュケナジである)。
●ラビ・ルリアのカバラ=「ルリア神学」で、後世に最も大きな影響を与えたのは、この世界が、創造の始まりから混在していた「悪の要素」によって、完成を妨害されてきたとした点である。
彼は、ユダヤ人こそ、悪の要素から世界を救い、未完成の天地創造を完成させるための使命を帯びた民(選民)だと主張した。サタンはユダヤ人を徹底して迫害し、メシア(救世主)の到来を妨害して、神の創造が未完成のままに留まるよう、陰に陽に働いていると主張した。
さらに、ラビ・ルリアの主張で後のカバリストに甚大な影響を与えたものは、「預言者がメシア到来の前触れとしたような地上の暗黒は、まさに極に達しており、メシア到来の機は熟した」という主張であった。
●「ルリア神学」は彼の死後半世紀ほど経った1625年頃からユダヤ教の真の神秘主義思想を代表するものになった。この「ルリア神学」による多大な影響のもと、1665年に、世界各地のユダヤ人を巻き込んだユダヤ教最大のメシア運動が起きた。「サバタイ・ツヴィ運動」である。

セフィロトの樹
■■第4章:ユダヤ教最大のメシア運動「サバタイ・ツヴィ運動」
●1626年、トルコのスミルナにサバタイ・ツヴィというユダヤ人が生まれた。奇しくも彼が生まれた日付はエルサレム神殿が破壊された日であり、将来、メシア(救世主)が生まれると信じられていた日であった。
サバタイ・ツヴィの時代、ユダヤ社会の支配的思潮となっていたのはラビ・ルリアのカバラ、すなわち「ルリア神学」で、彼もこの時代の風潮を受けて「ルリア神学」を熱心に勉強した。ストイックな修行に明け暮れていた彼は、その堂々たる体躯から、周囲の人々を魅了するようなカリスマ的なオーラを徐々に放っていたという。

サバタイ・ツヴィ
●1648年、サバタイ・ツヴィ22歳の年に、ウクライナでユダヤ人の大量虐殺事件、「フメリニツキーの乱」が起こった。この事件は、もともとポーランド領主に対するウクライナのコサックの反乱だったが、ひとたび暴動が起こると、コサックたちの矛先は、日ごろから嫌悪していたユダヤ人へと向かった。そのさまを、ある歴史家はこう描いている。
「あらゆる物を奪い去る凶暴で大規模な殺戮が起こった。各地で残忍な虐殺が行われ、ポーランド人たちは多くの場合、自分だけでも助かりたいという愚かな考えで、ユダヤ人の隣人を裏切った」


ボフダン・フメリニツキー(1595~1657年)
1648年から1657年にかけて「フメリニツキーの乱」を起こし、
多くのユダヤ人を虐殺した。虐殺はガリチア地方(西ウクライナ)を中心に、
ベラルーシ、さらにウクライナ南東部にも及び、ユダヤ人共同体は崩壊的危機
に立たされた。彼はユダヤ年代記では「邪悪なフメル」と記されている。
●この事件で虐殺されたユダヤ人の数は、50万人を超えたという。悲報はサバタイ・ツヴィの耳にも届いた。彼は「この事件こそ、メシア出現の生みの苦しみである」と宣言し、地上の悪が絶頂に達したという信念をいっそう強めたのであった。
さらに彼は、個人的に訪れた神秘体験を通じて、「自分はメシアだ」という観念を育むようになっていった。
●のちにサバタイ・ツヴィが、彗星のごとく現れたメシアとして、各地のユダヤ人社会から絶大な支持を得るようになった背景には、ひとりの若き預言者の存在がある。カバラ学者のナタンである。
ナタンは早熟の天才として才能を発揮していたが、同時に神秘的な資質も備わっていた。彼はある日の神秘体験によって、ガザにメシアが現れるという神の啓示を受けたと確信した。そして、その啓示に従って、ガザでサバタイ・ツヴィと出会ったのであった。サバタイ・ツヴィに出会ったナタンは、彼こそ預言されていたメシアだと、ただちに直感した。と同時に、自分はメシアの到来を告げる“先駆けの預言者”エリアの再来だと確信した。
ナタンとサバタイ・ツヴィ、いずれかが欠けてもユダヤ史上空前のメシア運動は起こり得なかったという意味で、この出会いは、まさに運命的な出会いだった。1665年のことであった。
◆
●ユダヤ教の口伝伝承では、預言者はパレスチナ以外の地には現れないとされていた。それゆえ、イスラエル以外の地に現れた預言者は、すべて「ニセ預言者」と見なされてきた。ところがナタンは、まさにパレスチナのガザで預言した。これは多数の預言者が活躍した紀元前の「聖書」時代以来、かつてない衝撃的な事件だった。
しかもナタンは、その資質からいっても、学識からいっても、また、預言者に欠かせない神秘体験のレベルの深さからいっても、真正の預言者と見なしていいだけの資格を備えてると信じられた。
そこで人々は、ナタンを預言者として、またエリヤの再来として受け入れた。ということは、彼が「この人こそメシアだ」と唱えたサバタイ・ツヴィこそ、待ちに待った本物のメシアということである。
ナタンに導かれて、サバタイ・ツヴィは「自分こそメシアである」と、聖地エルサレムで公に宣言した。また、2人の兄弟をユダヤとイスラエルの王に任命し、自分は「地の王の中の王」を名乗った。
●メシアが現れたというニュースは、手紙によってすぐさまヨーロッパ、アジア、アフリカのユダヤ人コミューンに伝えられた。人々は熱狂をもってサバタイ・ツヴィを迎え入れ、それらコミューンのシナゴーグ(ユダヤ教会堂)では、「我らの主、王、師にして、イスラエルの神の油注ぎたまいし聖にして義なるサバタイ・ツヴィ」への祈りが捧げられた。世界各地のユダヤ人社会から救世主ツヴィのいるトルコに使節団が送られた。
1665年のメシア宣言から1年とたたないうちに、ユダヤ教はサバタイ・ツヴィを中心とした強固な統一を達成した。サバタイ・ツヴィは古い律法を廃したり、全世界を26人の高弟に分割して分け与えるなど、「ユダヤの王」として振舞い、エルサレムからトルコのスミルナ、そしてコンスタンティノープルと、巡幸して歩いた。
●サバタイ・ツヴィをメシアと信奉する信徒(サバタイ派ユダヤ人)は、貧富、教養の別なく、あらゆる階層に及んだ。トルコ国内だけで何十万人にも達した。
これはトルコ政府にとって、まことに危険な状態であった。そこでトルコ政府は、政情を揺るがす危険人物としてサバタイ・ツヴィを捕縛し、投獄したが、サバタイ・ツヴィは牢獄内でも有り余る貢ぎ物に囲まれながら、「ユダヤの王」として振舞い、ますますユダヤ教徒を熱狂させた。人々はサバタイ・ツヴィに会うために使節団を組んでトルコに殺到した。
サバタイ・ツヴィは彼らの前で、救済はその年、つまり1666年のうちに起こると宣言した。そのため多数のユダヤ人が、自分たちの居住国を離れ、サバタイ・ツヴィとともにパレスチナの地に戻る準備をしたのであった。
◆
●けれども、サバタイ・ツヴィをメシアとする「サバタイ・ツヴィ運動」は、すぐに予想外の方向に進むことになる。
ユダヤ人のあまりの熱狂ぶりを見過ごすことができなくなったトルコ政府は、サバタイ・ツヴィをスルタン(君主)の前に引きだし、「ユダヤ教を捨てて改宗するか、死を選ぶか」と強く迫った。
サバタイ・ツヴィはあっさりと棄教を選んだ。それまでかぶっていたユダヤ式の帽子を捨て、イスラム教信者であることを示す白いターバンをかぶって退席したのである!
●サバタイ・ツヴィはイスラム教に改宗してしまった……。
普通に考えれば、これは堕地獄に値する神と民族への最大の裏切り行為である。ところがまことに奇異なことに、サバタイ・ツヴィの改宗はそのようには受け取られなかった。むしろこの改宗によって、サバタイ・ツヴィはより神秘的なメシアヘと昇格したのである。
なぜそんな奇妙なことが起こり得たのか?
理由は、サバタイ・ツヴィの最大のブレーンであるカバラ学者ナタンの巧みな肯定的合理化にあった。ナタンは、サバタイ・ツヴィの揺れ動く精神状態をカバラ的に再解釈し、サバタイ・ツヴィの改宗は、実は悪魔の息の根を止めるための作戦なのだと論を進めたのであった。
この世を覆いつくしている闇の勢力はあまりに強大であり、外部から攻撃をしかけても容易には崩れない。そこでメシア・サバタイ・ツヴィは、“あえて”悪の王国の内部深くに侵入した。そうして、時が至るまでは、あたかも悪の一部になりきった者のように振舞いつつ、着々と救済の準備を進めているのだと説いて、サバタイ派ユダヤ人を鼓舞したのである。
●このように、ナタンは「ルリア神学」を改良させる形で、独自のカバラ神学=「ナタン神学」を形成した。
彼によれば、サバタイ・ツヴィの戦いは、かつての対ローマ戦争のバル・コクバのときのような、単純な地上界での戦闘を意味しているのではなく、メシアの戦闘領域は霊界(セフィロト界)に広がり、現界と霊界にわたって展開され、互いにシンクロしあって進められる「霊的戦い」へと変質したというわけである。
◆
●イスラムに改宗したあとも、サバタイ・ツヴィを信奉する者はあとをたたなかった。また、サバタイ・ツヴィ自身も、ひそかにユダヤ教との関係を続け、シナゴーグに姿を現したり、一部の信者を集めては深遠なカバラを伝えた。
そのため、業を煮やしたトルコ政府は、サバタイ・ツヴィをアルバニアに追放し、1676年9月、サバタイ・ツヴィはその地で亡くなった。
●けれども、「サバタイ・ツヴィ運動」がそれで消滅したわけではなかった。
世界を覆うサタンの勢力がいかに強大なものかは、歴史を通じて常に迫害の標的にされてきたユダヤ人には、骨身に染みてわかっていた。それゆえ、「悪魔」を打ち倒すためには、自ら「悪魔」のただ中に入り、その内側から、ちょうど木を腐らせるような形で倒すしかないのだという、サバタイ・ツヴィおよびナタンの教えが説得力をもった。
その結果、「サバタイ・ツヴィ運動」は表向きの改宗者を数多くつくりだした。ある者はイスラムに改宗し、またある者はカトリックに改宗していった。
■■第5章:「サバタイ・ツヴィ運動」から「ハシディズム運動」へ
●「サバタイ・ツヴィ運動」以降、ユダヤのカバラ的メシア運動は、より内的なものとなり、何人もの自称メシアを生み出しながら、「ハシディズム運動」へとつながっていった。「ハシディズム」の「ハシド」とは「敬虔者」という意味である。
●「ハシディズム」の創始者は、18世紀初頭に東ヨーロッパを放浪して生涯を終えたバアル・シェム・トーブ(本名はイスラエル・ベン・エリエゼル)である。その後、ハシディズムは、その弟子で「大説教者」と呼ばれたラビ・ドーヴ・ベールなど数々の傑出したラビを生み出しながら、「大衆による神秘的敬虔主義運動」となって、まっすぐ今日まで続いている。

「ハシディズム」の創始者
バアル・シェム・トーブ
●この「ハシディズム運動」の大きな特徴は、カバラの用語と観念を、ユダヤ人の日常生活の宗教的言語へと転換させたところにあった。
その核になる用語を「ツァディク(義人)」といい、この「ツァディク」を救済の中心とする。この霊的指導者は、共同体ごとに現れる小さなメシアであり、彼らを神秘的リーダーとして敬虔な生活を実践し、総じて神の王国実現を追求しようとしているのである。現代のユダヤ神秘思想およびメシア運動は、このハシディズムを中心に展開している。
◆
●では、一般のユダヤ教徒は最終のメシア(救世主)登場の日を、どのように思い描いているのだろうか。簡単に紹介しよう。
ユダヤに伝わる伝承では、メシアはツファット、ベツレヘム、ティベリアのいずれかから出現するとされている。そこで登場した人物は、「サバタイ・ツヴィ運動」においてサバタイ・ツヴィがナタンによって祝福を受けたように、預言者によって祝福を受けて初めて、全てのユダヤ人にメシアとして認められ、エルサレムヘと向かうことになる。
メシアの時代は、開かずの門になっているエルサレムの「黄金の門」が開き、そこからメシアが入場することで幕を開ける。地上と霊界での戦闘の末、サタン勢力を駆逐し、メシア軍は最終的な勝利を収める。そのとき、幻視者には、雲間で展開される神と悪魔の戦闘が見えるともいう。
神の勝利の後、世界に散らばったイスラエル10支族は約束の地カナンに戻り、メシアを戴く統一された国を実現することになる。このときになって、天界に保存されていたエルサレムの霊的本体は、再び地上に降りて「新イスラエル王国」の首都となり、復活した「ソロモン第3神殿」を中心に、神とメシアによる神権政治が行われる。すでに熱狂的なユダヤ教徒の一部は、この「ソロモン第3神殿」の模型まで造りあげて、その日を待ち望んでいるのである。
こうして神の創造が完成されたとき、人類の寿命は1000歳に伸び、サタンは消え、野獣はどう猛さを忘れて全地が楽園となる。人類の新たな時代が到来するのである……
これが一般のユダヤ教徒が思い描いている「メシア到来後の新世界」である。

今も封印されたままである聖地エルサレムの「黄金の門」
※ 将来のメシア(救世主)到来の日、この門が開かれるという…
●「ツァディク」と呼ばれたハシディズムの指導者は、伝統的なユダヤ教の「ラビ」に対して「レベ」という尊称を持ち、指導権は世襲され、各地にレベの「家」が成立した。
しかし、そのハシディズムも発展を遂げる過程で幾つものセクトに解体し、さらに小さな相違点が起因となって異なる宗派を生んでいった。
●ハシディズムの中心地は、主にポーランドをはじめとする東ヨーロッパにあったが、ナチズムの脅威にさらされた結果、全て破壊された。そのため、アメリカやイスラエルに新たな中心地が生まれた。これらのハシディズムのセクトは、「ルバヴィッチ・ハシディーム」「ベルツ・ハシディーム」「サトゥマル・ハシディーム」などなど、各出身の町の名前で呼ばれる。
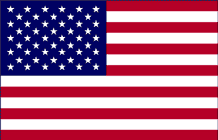
●このうちアメリカにある「ルバヴィッチ・ハシディーム」は、ハバド派ハシディズムとも呼ばれるが、同派から1990年代初頭、「メシア」が出現して、多大な反響を巻き起こした。その名をレベ・シュネルソン(メナヘム・メンデル・シュネルソン)という。彼は1951年に同派の第7代レベに就任した際、メシアは第8代レベが登場する前に現れると預言した。


アメリカのハバド派ハシディズムのレベ、
メナヘム・メンデル・シュネルソン
●シュネルソンが1994年に90歳で脳溢血で倒れると、その預言の解釈をめぐってハバド派内部で論争が起こり、二分する事態となった。すなわち、シュネルソンを正真正銘のメシアとして信奉し宣伝するグループと、シュネルソンはメシア出現の時期を示しただけであって、神のみが彼の本当の使命を明らかにすると主張するグループに分かれたのである。
ユダヤ社会では「神聖」の象徴であったシュネルソンは、自分自身をメシアとみる支持者に対して一切否定しなかった。並外れた知力と体力に恵まれていた彼は、カリスマ的存在であった。ユダヤ人はもとより、非ユダヤ人も彼にアドバイスや祝福を求めたほどで、ボブ・ディランなどの著名人も彼のもとへ“巡礼”した。
1994年のシュネルソンの死後も、彼を「メシア」とする動きはユダヤ社会に少なからぬ影響を及ぼしているという。
◆
●ところで、ハシディズムと政治の関係についてであるが、1912年に結成された宗教政党「アグダト・イスラエル」がイスラエル国家に協力的姿勢を保っているのに対し、超正統派ユダヤ教の政党「ナトレイ・カルタ」は、現在のイスラエル共和国を国家として承認することに反対している。
彼らはイスラエルが独立する際にも、断固反対した。真のイスラエル国家は、メシアとともにしか現れないからだという。
この超正統派ユダヤ教は、規模は小さいが、原理主義的傾向が極めて強いのが特徴である。彼らはメシアの出現を待望してやまず、そのために祈りと戒律を厳守した、極めて求道的な生活を日々送っているのである。
※ この超正統派ユダヤ教徒については後述する。
■■第6章:フランク派ユダヤ人の倒錯的なメシア運動
●サバタイ・ツヴィに影響されて、倒錯的なメシア運動を起こす者がいた。
1726年にポーランドで生まれたヤコブ・フランクという過激なユダヤ教指導者である。

ヤコブ・フランク
●彼は、サバタイ・ツヴィのひそみに倣って、キリスト教に「偽装改宗」した。偽装改宗は聖なる神秘だと考えたためである。
そして彼は「ルリア神学」を自分なりに解釈し直して、「悪の世界」を充実させることによって破局を招来し、「終末」を早めようというメシア運動「フランキズム」を展開したのであった。
ヤコブ・フランクの教義は著しく虚無主義的であった。この倒錯的なメシア運動は、もちろん成功することはなかった。

ユダヤ人ヤコブ・フランクは、「悪の世界」を
充実させることによって破局を招来し、「終末」を
早めようというメシア運動「フランキズム」を展開した
●ヤコブ・フランクとその一派(フランク派ユダヤ人またはフランキスト)は、1756年に正統派ユダヤ教ラビから除名された。その後、フランク派ユダヤ人たちのグループは、ユダヤ主義の世俗化を目指す「改革派ユダヤ教」に姿を変えたといわれている。
●ちなみにあの有名な初代ロスチャイルドは、フランク派ユダヤ教に深く関与していたとの説もある(19世紀を通じて、ロスチャイルド家はフランク派ユダヤ教を全面的に支持し、育成したと言われている)。


(左)ロスチャイルド財閥の創始者
マイヤー・アムシェル・ロスチャイルド
(ロスチャイルド1世/1744~1812年)
(右)獅子と一角獣が描かれているロスチャイルド家の紋章





ロスチャイルド1世には5人の息子がいたのだが、それぞれをヨーロッパ列強の首都に
派遣して次々と支店を開業させ、それぞれがロスチャイルドの支家となった。上の画像は左から、
長男アムシェル(フランクフルト本店)、次男サロモン(ウィーン支店)、三男ネイサン
(ロンドン支店)、四男カール(ナポリ支店)、五男ジェームズ(パリ支店)である。
※ フランク派によって「改革派ユダヤ教」の代表選手として選抜されたのは、ドイツの「正義者同盟(ブント)」のメンバーだったアブラハム・ガイガーで、彼は1868年11月、フランクフルトで行われた初代ロスチャイルドの五男の葬儀で、ユダヤ教ラビとして説教していたと言われている。
このアブラハム・ガイガーの活躍によって、ドイツのユダヤ人の間では1850年までに、アブラハム・ガイガーの作った「改革派ユダヤ教」が圧倒的な勢力を得るに至ったという。


(左)モーゼス・モンテフィオーレ(ロスチャイルド一族)
(右)フランス・ロスチャイルド家のエドモンド・ロスチャイルド
※ 2人は「イスラエル建国の父」として知られている
■■第7章:本質的に「シオニズム」と「ユダヤ思想」は別物である
●「シオニズム」(別名 Zion主義)とは、パレスチナにユダヤ人国家を建設しようという思想である。聖地エルサレムの「シオン(Zion)の丘」にちなんで名付けられた。
現在のイスラエル政府の「シオニズム」は、人種差別的なイデオロギーと軍事思想に基づいているといえる。
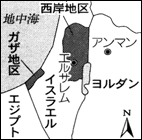

(左)イスラエル(パレスチナ地方)の地図 (右)イスラエルの国旗




「シオニズム」に抵抗する人々
●一般に「シオニズム」と「ユダヤ思想」の違いはあまり意識されることはない。
そのため、「シオニズム」と「ユダヤ思想」は同じものだと思っている人が多い。しかし本質的に、「シオニズム」と「ユダヤ思想」は別物である。
基本的にシオニズム強硬路線派は、無神論者といっていい。ユダヤ教そのものにはあまり関心のない連中である。自分たちの行動を正当化するためにユダヤ教を利用することはあっても、ユダヤ教そのものを信仰してはいない。
●『反シオニズムの正統派ユダヤ教徒』と題された本には次のように書かれている。
「正統派ユダヤ教徒の大半は、パレスチナの地にユダヤ人のための民族の郷土を設立するというシオニストの野望に反対である。これはシオニズムそのものではなく、シオニストに反対するという側面が大きい。
なぜならば、シオニストは大半が脱宗教的であり、伝統的なラビの権威よりも社会主義や民族主義といった『非ユダヤ的』なイデオロギーを優先しているからである。正統派ユダヤ教徒は、自分たちの立場を神学的な面から正当化するため、救済を早めることを禁じたラビの伝統を様々に引用し活用している。」

「イスラエル共和国」の独立宣言(1948年)
●シオニスト強硬路線派が悲願の建国を果たした「イスラエル共和国」──。
しかし、超正統派ユダヤ教徒はこの国を認めようとしない。
なぜならば、イスラエル共和国は建国において“メシア信仰”を無視し、しかも政教分離という近代国家の原則を採用した世俗国家であるためだという。超正統派ユダヤ教徒からすれば、このようなイスラエル共和国が“国家”と名乗ること自体、神に対する許しがたい冒涜(ぼうとく)に他ならないという。
この超正統派ユダヤ教徒は「聖都の守護者」を意味する「ナトレイ・カルタ」(前出)と呼ばれ、現在のイスラエル共和国はユダヤ教の本質を完全に逸脱した世俗的な寄せ集め集団に過ぎない、として徹底的に批判している。


「シオニズム」を批判する超正統派ユダヤ教徒たち

イスラエルの国旗を燃やして「シオニズム」に反対
●1985年4月4日、超正統派ユダヤ教徒グループ「ナトレイ・カルタ」は、次のような声明文を発表した。
「シオニストの大冒険は不名誉な終わりを迎えようとしている。最初はシナイ半島だった。今度はレバノンである。独立した真のユダヤ教徒であるトーラーのユダヤ人にとって、これはまったく驚くことではない。我々は両親からも教師からも、シオニズムはユダヤとユダヤ思想の敵だと教えられてきた。
シオニストの政治的策動は、一時的には成功するかもしれないが、長い目で見れば、その命運は尽きているのである。〈中略〉
シオニズムはユダヤ思想とは全く反対のものである。ユダヤ思想は数千年にわたり、シオニズムなしに存続してきた。シオニズムのいう『メディナ』は全くの作り物であり、真のユダヤ思想を歪めるものである」
「シオニスト指導者らは、今でこそホロコーストを大げさに哀しむが、当時の彼らは、『強壮な若いパイオニア』だけいればいい、『全ヨーロッパのユダヤよりパレスチナの1頭の牝牛のほうが大切だ』と言っていたのである。我々はシオニストという偽ユダヤ教徒がその正体を知られるようになること、ユダヤが真のユダヤ思想を心から信じて実践し、過去の栄光を思い、未来を誠実に信じることを望み、祈っている」

↑「シオニズム」に反対するユダヤ人たち
Zionism is Nazism(シオニズムは
ナチズムだ)と書かれたプラカードが見える
●さらに彼らは、1992年に次のような声明を発表した。
これは「シオニズム」に対する強烈な批判メッセージであった。
「敵であるシオニストと私たちの戦いは、妥協の余地のない、まさに “神学戦争”なのである」
「ユダヤ人たちが全世界に追放されたのは、神の意志によるのであって、彼らが神の律法を守らなかったためである。あらゆる苦難をへて、メシア(救世主)が到来するまでそれは続く。メシア到来によってのみそれが終わるのである。それゆえに、シオニストあるいはその関係機関が神を無視して世界中からユダヤ人たちに帰ってくるように強要するのは、ユダヤ人たちをいよいよ危険に陥れる“不敬の罪”を犯していることになる」
「もしシオニストが神を無視し続けるならば事は重大である。ここ、すなわちイスラエルは地上で最も危険な場所となろう」

イギリスは第一次世界大戦中の1917年に、ユダヤ人に対して「連合国を支援すればパレスチナの地に
ユダヤ国家建設を約束する」という「バルフォア宣言」を行なった。第一次世界大戦後、それまでパレスチナ
を支配していたオスマン・トルコ帝国の敗北にともなってパレスチナは国際連盟の委任統治の形式でイギリスの
支配下に置かれた。第二次世界大戦後にイギリスは深刻化するパレスチナ問題を国連に付託した。1947年に
国連総会はパレスチナに対するイギリスの委任統治を廃止し、パレスチナの地をアラブ国家とユダヤ国家に分割
する決議を採択した。この分割決議はユダヤ人にとって有利なもので、翌年にユダヤ人が独立宣言(建国宣言)
すると、アラブ諸国は猛反発し、すぐさま大規模な武力衝突(第一次中東戦争)が勃発した(新生ユダヤ国家
であるイスラエルは米英の支持を得てアラブ諸国を打ち破り、イスラエルの建国は既成事実となった)。
この両者の紛争は1973年の第四次中東戦争まで続き、多くのパレスチナ先住民が土地を奪われ、
イスラエルの支配地域は拡張していった。半世紀以上たった現在も450万人ものパレスチナ人が
その土地を追われたまま、ヨルダンを始め、レバノン、シリア、エジプト、湾岸諸国などで難民
生活を強いられている。100万人近いパレスチナ人がイスラエルの領内で人種差別的な
厳重な監視下の生活を強いられている。ヨルダン川西岸、ガザ地区ではそれぞれ
170万人、100万人ものパレスチナ人がイスラエル占領軍の
極限的な抑圧のもとに置かれて苦しんでいる。
●「シオニズム」について、ジャック・バーンスタインというアシュケナジー系ユダヤ人は次のように述べている。
「実はほとんどのユダヤ人というものは無神論者である。あるいは反神の宗教ともいえるヒューマニズム(人間至上主義)に従っている。だからユダヤ人とは宗教的な人々であり、イスラエル建国は聖書預言の成就であるととらえるのは神話でしかすぎない。しかもユダヤ人が単一民族であるというのはもっと神話である。アシュケナジーとスファラディの間には完全なる区別がある。これこそ最大の証拠である。
イスラエルで行われている人種差別は、イスラエルという国家を遅かれ早かれ自滅させてしまうことになるだろう……」
●サザン・バプテストの「新約聖書学」教授フランク・スタッグは、以下のような見解を述べている。
「今日のイスラエル国家は数ある国々の一つにすぎない。それは他のあらゆる政治国家と同様に“政治国家としての運命”を辿らなければならない。他のあらゆる政治国家のように判断されなければならない。
現在のイスラエルの国や国民を“神のイスラエル”とすることは、『新約聖書』の教えにおいて致命的な誤りを犯している」
●また、プレズビテリアンの「旧約聖書学」教授オーバイド・セラーも、このことを次のように結論づけている。
「現代のパレスチナにあるユダヤ国家は、聖書や聖書預言によって正当化されるものであるというシオニストたちの主張を支持するものは、『旧約聖書』にも『新約聖書』にもないということに私とともに研究している者たち全てが同意している。
さらに聖書預言という“約束”は、ユダヤ人やシオニストだけではなく全人類に適用されるべきものである! “勝利” “救い”という言葉は本当の聖書の意味としては宗教的・霊的なものであって、政治的な敵を征服するとか崩壊させるとかいう意味のものではない」
「『新約聖書』を信じるキリスト教徒であるならば、もともとそこに住んでいた人々から政治的、また軍事的力によって奪い取ってつくった現代のイスラエル共和国を、キリスト教徒の信仰の神の“イスラエル”と混同させてはならない。これら2つのイスラエルというものは完全に対立しているものなのである」
◆
●反シオニズムのユダヤ人ジャーナリストであるアルフレッド・リリアンソールも、次のような指摘をしている。(ちなみに彼の父方の祖父はアシュケナジー系ユダヤ人で、祖母はスファラディ系ユダヤ人である)。
「ユダヤ的遺産は明白であり、間違えられようがない。それは変わらずに続いてきた。一方、シオニズムは特定主義であり人種差別主義であるのに対し、ユダヤ教=ユダヤ主義は普遍主義であり人種統合主義である。
ユダヤ教はキリスト教やイスラム教と同じく一神教であり、つねに道徳的選択と人間と創造主の間の精神的結びつきを代表してきた。そこには狭量な排他主義の入る余地はほとんどなかった。それに対しシオニズムは、土地へ執着し、しかもその土地は2000年もの間ユダヤ人には属していなかったのである。
ユダヤ教は特定のどんな地理的境界とも無関係であることによって、今日まで生き延びてきた。ユダヤ人は主なる神に選ばれたが、それは特定の地を所有したり、自分たちの子どもを他人よりもえこひいきするためではなかった。彼らが選ばれたのは、ただ唯一の神しか存在しないというメッセージを広める任務のためであった」


ユダヤ系アメリカ人のアルフレッド・リリアンソール。
反シオニズムの気鋭ジャーナリストであり、中東問題の
世界的権威である(国連認定のニュースレポーターでもある)。
─ 完 ─
■■おまけ情報:ユダヤ人にとって「メシア」はいろいろな形をとってあらわれる
●ユダヤ人のラビ(ユダヤ教指導者)であるマーヴィン・トケイヤーは、著書『ユダヤ人の発想』(徳間書店)の中で次のように述べている。
参考までに紹介しておきたい。


(左)ラビ・マーヴィン・トケイヤー。1967年に
来日、「日本ユダヤ教団」のラビとなる。
(右)彼の著書『ユダヤ人の発想』
「ユダヤ人は長い歴史を通じて、いつかメシア(救世主)が来ると信じてきた。
アウシュヴィッツの囚人たちがつくった『アニ・マミン』の歌にもあるように、『私たちはメシアが来ることを信じている。しかし、到着するのが少し遅れているだけだ』という大いなる楽観と、同じほどに強い信念に支えられて生きてきた。
そして、メシアが来るということを、いたずらにただ待っていただけではない。
自分たちの手でメシアを呼び寄せなければならないという情熱に駆られてきたのである。
よりよい世界が来る期待、興奮というものを、常にユダヤ人は、血の中で感じてきた。そしてそれが、一歩でも自分を前進させようという情熱になってきたのである。やがて地上の楽園が来るという終末観が、ユダヤ教を貫いているが、これは手形の決済日がいつかやってくるようなものである。しかし、だからといって、だれか人間以外のものが手形を決済してくれるから、初めから不渡りにしておいてよいということではない。手形の決済の日には、人間は自分で手形を落とさなければならないのだ。その日のためにこそ、日々の精進と進歩というものが生きるのである。
ユダヤ人にとって、メシアはいろいろな形をとってあらわれる。
たとえば、ユダヤ人マルクスが説いた共産主義社会というものも、その一つである。ユダヤ人キッシンジャーにとっては、自分なりに考えた安定した世界秩序をつくることがメシアであるだろう。あるいは、ユダヤ人の小さなビジネスマンにとっては、自分の仕事が成功することが、メシア信仰の彼なりの表れとなる。
要するに、少しでも世の中をよくしようという思いは、それと同時に、自分を少しでもよくしよう、進歩しなければならないという意欲と連結しているのだ。ユダヤ人は、子どものころからこういうふうに教えられ、そして自分でも念じてきているのである。
ユダヤ人の頭の中に詰まっているのが、世界の進歩だけではないことに注目してほしい。要するに、一人の人間の進歩というものは、世界の進歩と同じことであると考えられているのだ。強烈な個人意識がそこには存在しているのである。
ユダヤの聖典『タルムード』には、『自分が進歩しなければ世界は進歩しない』という言葉がある。世界は一つであり、自分は一人なのだ。」
── 当館作成の関連ファイル ──

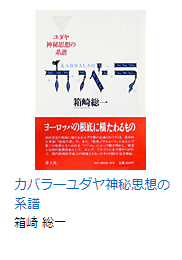


Copyright (C) THE HEXAGON. All Rights Reserved.