| ヘブライの館2|総合案内所|休憩室 |
No.a6fhb300
作成 1998.1
| 序章 |
|
|---|---|
| 第1章 |
失敗に終わったフランスでの
国際難民会議(エビアン会議) |
| 第2章 |
ユダヤ難民に冷淡だった
フランス政府 |
| 第3章 |
ユダヤ難民に冷淡だった
イギリス政府 |
| 第4章 |
ユダヤ難民に冷淡だった
アメリカ政府 |
| 第5章 |
空振りに終わってしまった
米英両国共催の「バミューダ会議」 |
| 第6章 |
なぜアウシュヴィッツは
破壊されなかったのか? |
| 追加1 |
『封印されたホロコースト』について
|
|---|---|
| 追加2 |
映画『戦場のピアニスト』の秘話
|
| 追加3 |
なぜアメリカはユダヤ人の
救済に消極的だったのか? |
| 追加4 |
ユダヤ難民に無関心だった
アメリカの政治家たち |
| 追加5 |
連合国が断固たる措置をとっていたら
ユダヤ人の犠牲者はもっと少なくて済んだ |
| 追加6 |
アメリカのブッシュ大統領は語る
「アウシュヴィッツは爆撃すべきだった」 |
↑読みたい「章」をクリックすればスライド移動します
■■序章:はじめに
●第二次世界大戦中、ドイツで公然と行われたユダヤ人迫害に関して、ヨーロッパの国々もアメリカも、長い間沈黙を守った。(アメリカはユダヤ人に対する入国査証の発給を非常に制限し、ほとんどシャットアウトの政策であった)。

1933年1月30日に誕生したヒトラー政権
●もちろん、ナチス・ドイツに対してヒューマニズムの立場で結束し、厳重に抗議すべきと説いた人たちも確かにいた。しかし、多勢に無勢で力にならず、ドイツを正面きって弾劾することも、また、ユダヤ人たちを進んで救おうとするまとまった動きも見られず、ようやく戦争が最終段階に入って誰の目にもナチスの崩壊がはっきり分かる頃になって、やおらインターナショナルな次元で救済の声があがり始めた。
でも時すでに遅く、文字通り「後の祭り」だったのである。
●以下少し長くなるが、欧米諸国(連合国)がナチス・ドイツのユダヤ人迫害政策に対してどのような対応をしてきたのかを、フランス→イギリス→アメリカの順で詳しく見ていきたい。
■■第1章:失敗に終わったフランスでの国際難民会議(エビアン会議)
●1938年7月のことであった。ナチスのユダヤ人迫害政策がいよいよ露骨になってそれを多くの人々が知り、欧米諸国が国内の世論を無視出来なくなった時、32ヶ国の代表者たちがフランスの保養地エビアンの「ローヤル・ホテル」に集まり、ユダヤ難民問題の国際会議を開くことになった。
それは既に、ナチスがユダヤ人迫害を始めてから5年半もの歳月が経っていた頃のことである。

国際難民会議(エビアン会議)の
開催地となった「ローヤル・ホテル」


国際難民会議(エビアン会議)に出席した代表者たち
※ 1938年7月に32ヶ国の代表者たちがフランスの
エビアンに集まり、ユダヤ難民問題の国際会議を開いた
●各国代表は、キリスト教的、人道主義的立場から、ユダヤの虐げられている人達を救済するためには全員一致してナチスの政策を阻止すべしとか、難民を受け入れよう……などと熱弁をふるった。が、それらは「空理空論」ばかりで、実行可能な具体策というものは1つもなかった。
それぞれが、どこかの国が問題を解決してくれるだろうと期待し、ついには異口同音に「我々はユダヤ難民に手を差し伸べるのにはやぶさかではないが、我が国の現状が、それを許さぬのは誠に遺憾とするものである……」といった意味のことを述べるにとどまった。

10日間にわたって開催された「エビアン会議」の様子
●結局、イギリスにしろ、アメリカにしろ、またフランスにしろ、難民受け入れのために移民法をほんの少しでもゆるめるどころか、反対に移民制限を厳しくしてしまったのである。
ドイツの隣国のスイスも、ユダヤの不法越境が増えたので困る、と言ってナチスに抗議した。
イギリスのチェンバレン首相が「受け入れることによって、国内の反ユダヤ主義が強まるのを恐れる」と言い訳すれば、片やナチスのリッベントロップ外相は「我々がドイツからユダヤを放逐しようと思っても、どこも受け入れてくれる所がない」と、こぼしたそうである。
※ 実際にはイギリスとオーストラリアが、わずかではあったがユダヤ難民受け入れに手を貸した。しかしそれも、国民を刺激することを恐れて、秘密裏に行わなければならなかった。ナチスにとって、こういうヨーロッパ全体の反応は予測していたことで、ユダヤ救済のラッパは鳴れども誰も動かず、ヒトラーの思うつぼだったのである。


(左)イギリスのチェンバレン首相
(右)ナチスのリッベントロップ外相
●ナチ党の理論的指導者として活躍したアルフレート・ローゼンベルクは、この「エビアン会議」を契機として、党機関紙『フェルキッシャー・ベオバハター』に論説を寄せ、「国際会議というものは伝統的に反ユダヤ主義闘争の代表の集まる場」である事を皮肉を込めて指摘した。

アルフレート・ローゼンベルク
彼は初期の頃からヒトラーの傍らにあって
思想的影響を与え、側近として重きをなした
●1938年夏に「エビアン会議」が失敗に終わって4ヶ月が経つか経たぬ中に、ドイツではまずユダヤ教会焼き打ちの狼火があがり、続く「水晶の夜」(1938年11月9日)と呼ばれる事件をきっかけに、計画的ユダヤ人迫害の序曲が始まった。
※ この「水晶の夜(クリスタル・ナハト)」と呼ばれるユダヤ人迫害事件は、ポーランド系ユダヤ人青年が在フランス・ドイツ大使館の書記官であるフォム・ラートを射殺した事がきっかけで起きた。この事件によって、当時まだ存在していたドイツ全土の400のユダヤ教会(シナゴーグ)のほとんど全てが焼かれ、7500の商店が壊された。その際に砕け散った窓ガラスが月明かりに照らされて水晶のように輝いたことから「水晶の夜」と言われているが、実際には殺害されたユダヤ人の血や遺体、壊された建造物の瓦礫などで、現場は悲惨なものだったという。
この事件で96人のユダヤ人が殺され、2万6000人のユダヤ人が逮捕され、強制収容所に連行された。この事件を機に、ヒトラーはユダヤ人の大規模な国外追放を始めた。


1938年11月9日の「水晶の夜」事件で破壊されたユダヤ人商店街
※ 砕け散った窓ガラスが月明かりに照らされて水晶のように輝いた
ことから「水晶の夜(クリスタル・ナハト)」と呼ばれている。
右の画像は翌朝、砕け散った窓ガラスを掃き集める青年。
●「エビアン会議」で西側諸国がユダヤ難民の保護に二の足を踏んだことが、ユダヤ人迫害の遂行を急ぐベルリンのヒトラーに「ゴーサイン」を送ることになった、とみる歴史家は少なくない。

ベルリンにいたヒトラーは、フランスで開催された
ユダヤ難民問題の国際会議の動きを静かに注視していた
※ 追記:
●ベルント・シラー著『ユダヤ人を救った外交官 ─ ラウル・ワレンバーグ』(明石書店)の訳者である田村光彰氏(北陸大学法学部教員)は、この「エビアン会議」の実態について次のように語っている。
「1938年7月6日、フランスの保養地エビアンで10日間にわたる国際難民会議が開催された。この会議では、わずかの例外を除いて、いかなる国もユダヤ人難民を引き受けようとはしなかった。そればかりか、その時点まで法律上受け入れの可能性のあった国々は、移民法を改正し、締め出しを図ったり、あるいは少しではあるが開いていた国境を閉じた。
ユダヤ人難民の入国を拒否する理由は、第1に福祉政策上の恐れであった。ユダヤ人は多くの法律や条例で職業から締め出され、自営業は略奪され、閉鎖させられ、人間として生存する最低限の市民権をも奪われていた。さらにドイツやオーストリアから国外『移住』をする場合には、加えてほぼ全財産が没収された。貧困と絶望が直撃した。諸外国は、入国してくる難民が福祉の受給者になることを避けようとした。第2に、世界恐慌の影響と、それによる自国内の失業者の存在である。
〈中略〉
32ヶ国の代表と39の救援組織が参加したこの国際難民会議は、見るべき成果はほとんどなかった。ユダヤ人難民を救うという本来の主旨は、〈難民の救済〉とは不釣り合いな開催場所である保養地の湯煙の中に雲散霧消してしまった。以降、難民に手を差し伸べようとする組織的で国際的な努力は、第二次世界大戦の勃発と共に、ほんの少数の例を除いて消滅していった。」


(左)『ユダヤ人を救った外交官』(明石書店)
(右)スウェーデン外交官ラウル・ワレンバーグ
■■第2章:ユダヤ難民に冷淡だったフランス政府
●ドイツが侵入して来る2年前、フランスのダラディエ首相は、移民、特にユダヤ移民を対象とした人種差別法令を発していた。
またフランスの「ユダヤ人問題委員会」のベルポワは、「戦争を望んでいるのはユダヤ人である。それが彼らの経済を助長し、世界征服へと繋がるものであるからだ」と述べ、さらには「ヒトラーは問題解決法をよくわきまえた人物である」と、当時のドイツの政策を讃えていた。
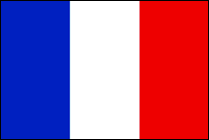
●1938年11月の「水晶の夜」事件以後、ドイツを脱出するユダヤ人が続出すると、フランスはその波が自国を揺さぶらぬようにと手を打ち始めた。
イギリスのチェンバレン首相がフランスに対して「もっとユダヤ人を受け入れるべき……」と、パリに出向いて来て勧告すると、「これまでユダヤを入れ過ぎた。もう一人たりとも入国させられない」というのが、フランス側の返答であった。
その言葉通りにフランスは、ドイツからの難民は再び送り返す方針を採ったのである。

ドイツ軍によるポーランド侵攻(1939年)
※ これで第二次世界大戦の幕が切って落とされた
●1939年9月1日にドイツ軍がポーランドに侵入すると、フランスはイギリスと共にその翌日、対独宣戦布告を発した。
ドイツと戦う自信は十分にあったフランスだったが、にもかかわらず、わずか9ヶ月であえなくドイツに降伏。そして3ヶ月を経ずして、「ユダヤ人を差別する法規」が作られ、実施されるようになった。
その第一段階として、ユダヤ人は公職から追放され、学校、病院、裁判所といった公的機関からも締め出され、そして翌年からは自由業も禁止され、ユダヤ人の大半は失業を余儀なくされた。学生の場合は、1941年6月に作られた法規によって大学への道を封じられ、子供連は公園で遊ぶことを禁じられた。
●フランスには、1870年に成立した「クレミュー法令」というのがあって、それによってユダヤ人に対する中傷も禁じられていたのだが、ヴィシー政府は「クレミュー法令」の無効を宣言した。この法令は、ある種の人間の集団に対してジャーナリズムが人種的、宗教的反感を煽り立てることを禁じたものであったが、ヴィシー政権下ではその無効宣言によって、反ユダヤ主義運動が合法化された。
ヴィシー政府そのものはナチス・ドイツに屈服した後で成立したから、あたかもナチスの圧力によって「ユダヤ人迫害」に手を染めたかのように一般には信じられてきたが、実際には、無効宣言は「自発的」に発せられたのであって、ナチスは全く関係していなかったのであった。
◆
●ヴィシー政府のラヴァル首相は、ドイツをバックにした反ユダヤ主義を利用して、フランスの再建を図った。
彼は「永遠に同化しないユダヤ民族は、フランスの中に別の国家を築いて我々を滅ぼそうとしていたのである」などと言い、1941年春にはユダヤ人の財産没収を宣言した。
●ユダヤ人の財産没収のことをアーリアニザション(アーリアン族所有化)と称し、そして得意になったラヴァル首相は、ドイツのSS将校たちとの会合において、「反ユダヤ主義のアクションという点では、我々フランスのほうが諸君ナチス・ドイツよりも先輩である」と、ぶったという。
しかし、この「アーリアニザション」たるや、体のよい掠奪みたいなものであった。例えば、没収した物品についての控えもろくに付けていなかった場合が多く、没収財産の大方は行方不明となったり、それに携わった公人の懐に入ってしまった事実も少なくなかった、と言われている。

ピエール・ラヴァル首相
彼はヒトラーに熱心に協力し、
ドイツでの強制労働につかせるために
フランス国内のユダヤ人を積極的に移送した。
戦後、米軍に逮捕され、裁判に立たされた彼は、
傍聴者のみならず陪審員からも口汚くののしられた。
1945年10月15日の死刑執行の日、彼は毒を
飲んだが、医師たちがすぐに吐かせた。その後、
吐き気をもよおし、水を求めながら銃殺隊の前
まで引きずられていったが、威厳をもって
死に臨んだと伝えられている。
●1942年7月16日には、フランスにおいて最大規模の「ユダヤ人狩り」(ユダヤ人の一斉検挙)が2日間にわたって行われた。
この事件は通称「ヴェル・ディヴ事件」と呼ばれ、ヴィシー政府がフランス警察を動かして作戦を実行し、パリで9000人にも及ぶ警察官と憲兵が動員され、多くの国民がそれに協力したのである。
警察庁の記録によれば、パリと郊外で一斉検挙されたユダヤ人は1万3152人で、その約3分の1(4115人)は子供だった。

●このとき検挙されたユダヤ人の多くは、パリ市内の「ヴェル・ディヴ(冬季競輪場)」に数日間監禁され、その後、アウシュヴィッツをはじめとする東欧各地の強制収容所へと送られた。
終戦までに生き延びたのは100人に満たない大人のみで、子供は生き残らなかったと言われている。

「ヴェル・ディヴ(冬季競輪場)」に閉じ込められたユダヤ人たち
※ 水や食料やトイレが不足して、屋根も無く劣悪な環境だったという
●この「ヴェル・ディヴ事件」は戦後のフランスではタブー視され続けてきたが、1995年7月16日の「追悼式典」に出席したシラク大統領が、初めて「フランス国家の犯した誤り」と認めた。
フランス人の大半はこの事件のことを知らなかったので、大統領の演説を聞いた国民の多くは困惑し、大きな衝撃を受けたと言われている。
※ この時のシラク大統領の演説は、自ら総裁を務める「共和国連合」を中心とする右派にも波紋を拡げる内容ではあったが、世論調査の結果、国民の多数が大統領の演説を支持したことが分かったという。

事件から53年目にあたる1995年の
「追悼式典」で演説するフランスのシラク大統領
※ 戦後ずっとフランス政府は「ヴェル・ディヴ事件」の
責任を一切認めていなかった。1995年になってようやく
シラク大統領がこの事件は「フランスのフランス人によって
犯された犯罪」であることを明言し、正式に謝罪した。
●フランスのユダヤ問題に詳しいあるジャーナリストはこう述べている。
「第二次世界大戦中、ナチス占領下で激しい抵抗を繰り返した『レジスタンスの国』を自負するフランスだが、その一方で、皮肉にも自国政府による大規模なユダヤ人迫害が行われていたのだ。
このことは長年、公式には認められていなかったが、1993年に『ユダヤ人迫害の日』が設けられ、1995年には大統領就任直後のシラク大統領が演説で、ホロコーストにおけるフランス国家の責任を承認し、フランス人には“時効のない負債”があると述べたのである。これは多くのフランス人にとって衝撃的な話だった」
●このジャーナリストはさらに続けてこう述べている。
「この話で問題なのは、フランスのユダヤ人迫害がナチス占領下で強制的に行われたわけではないという点にある。
当時、フランスはユダヤ人のフランス国籍を剥奪したり、たとえ市民権を持っていたとしても上級職には就けないようにしていた。また、ユダヤ人には黄色い星章を付けさせて区別。フランスで第二次世界大戦中に行われたユダヤ人の迫害の象徴である『ドランシー収容所』の初期の警備と管理は、フランスの公務員と憲兵が中心だったのだ。
このようにナチスだけではなく、フランス政府も能動的にユダヤ人の迫害を行っていたのである。
また、フランスでは1942年の一斉検挙事件以外でも多数のユダヤ人が逮捕・連行されており、終戦までの間にフランスからアウシュヴィッツその他の強制収容所に送られたユダヤ人の総数は約7万6000人(国内の収容所での死亡者や処刑された人々を加えると約8万人)にのぼると言われているのだ」

↑「ドランシー収容所」に連行されるユダヤ人たち(1941年8月)
パリ北東部にあった「ドランシー収容所」はユダヤ人移送のための収容所で、
ポーランドの強制収容所へ移送するまで仮に収容しておく「通過収容所」だった。
1941年8月の設立から1944年8月の解放までの間に約7万人のユダヤ人が
「ドランシー収容所」からアウシュヴィッツなどの強制収容所へ移送された。
●ところで、鋭い知性の持ち主だったフランスの著名な哲学者ジャン=ポール・サルトルは、大戦中に自国フランスで起きていた惨劇について次のように嘆いていた。
参考までに紹介しておきたい。
「およそ、フランス人で、ドイツ軍の占領と対ナチス抵抗運動の経験があるぐらいの年配の人間だったら誰でもそうなのだが、私はユダヤ人に対する組織的迫害計画を、単なるヒトラーの狂暴性のおそるべき結果として片付けることはできなかった。
このような反ユダヤ政策がフランスにおいて可能だったのは、多くのフランス人が何も言わずにのんびりと『共犯者』となっているからであって、さもなければとてもありえないことだと、毎日毎日、嫌というほど思い知らされたものだった。
それに、1942年のユダヤ人一斉検挙(ヴェル・ディヴ事件)を行ったのは、ほかならぬわがフランス警察であることや、真正フランスのフランス人たるラヴァル首相が、ユダヤ人追放に関する命令書に『子供を含む』と書き込んだ事実を忘れることはできないのである。」
(サルトル編『アラブとイスラエル』サイマル出版会)

ジャン=ポール・サルトル
(1905~1980年)
フランスの哲学者、作家、劇作家、
評論家。1964年に「ノーベル文学賞」に
選ばれたが、「いかなる人間でも生きながら
神格化されるには値しない」と言って、
ノーベル賞受賞を辞退した。
※ 追記:
●上で紹介したフランスの歴史の暗部(恥部)ともいえる「ヴェル・ディヴ事件」は、現在何本か映画化されているので、興味のある方はご覧下さい↓



左から『パリの灯は遠く』、『黄色い星の子供たち』、『サラの鍵』
■■第3章:ユダヤ難民に冷淡だったイギリス政府
●第一次世界大戦の結果イギリスは、パレスチナ占領の実績がものを言って国際連盟からその地の委任統治権を得ると同時に、ユダヤの国家作りも課題として負わされた。イギリスがこのような提案を呑んでユダヤのために一肌脱ぐ気になったのも、国内事情からもあるいは外交政策としても、ユダヤに関する難題が山積していたからである。
特に第一次世界大戦前にロシアからおびただしい数のユダヤ人がドーバー海峡を渡ってやって来て住み着いた上に、1930年代に入ってからもヨーロッパ大陸からユダヤの波が押し寄せ、国内にユダヤ・ストレスが顕著になったからでもあった。
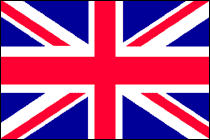
●時の首相ネヴィル・チェンバレンは、先述したように、フランスに対してユダヤ難民をもっと受け入れるようにとヒューマニスティックな呼び掛けをしたが、自国や統治領のパレスチナには、ユダヤ人を受け入れることを種々の理由で渋っていたのであった。そのようなイギリスの政策によって、どれだけのユダヤ人が助かるべき命を失ったか知れないと言われている。


(左)ネヴィル・チェンバレン首相 (右)ヒトラーと握手するチェンバレン
●イギリスはフランスとともにドイツに対して宣戦布告をし、ここに第二次世界大戦という大掛かりな舞台の幕が切って落とされたのであるが、その日、パレスチナのテル・アビブの海岸では、「タイガーヒル号事件」が発生した。
ポーランドをはじめチェコ、ルーマニア、ブルガリアなどの国々からユダヤ難民1400人を乗せてきた「タイガーヒル号」が、イギリス海軍の巡視艇からいきなり銃撃を浴びせられ、多数のユダヤ人が殺されてしまったのである。
これは記録に残っている限りでは、第二次世界大戦が始まってから最初のイギリスの発砲であり、ナチス・ドイツ以外の手にかかって殺された最初のユダヤ人だった。
この惨劇はあたかも、後にユダヤ難民のパレスチナ不法入国を食い止めるべくやっきになったイギリス人の、その政策の前途多難を暗示したようなものであった。
●パレスチナではシオニズムに対するアラブの抵抗が強まり、これは日を追うにしたがって抜き差しならない政治運動に移行していった。パレスチナへ流れ込んだユダヤ人の大半はポーランド、ルーマニア、バルト海沿岸のリトアニアとラトビア、それにギリシアなどからであったが、ユダヤ人の増加を嫌ったパレスチナのアラブ人が1936年4月にストに入り、それが大規模な暴動を引き起こしたことから、次第にパレスチナ問題は国際問題と化した。
イギリスのパレスチナ政策は、アラブを刺激しないという方針で進められるようになり、ユダヤ人のパレスチナ入国を厳しく制限するようになった。
これに失望したシオニスト・ユダヤ人たちは、イギリスの“植民地政策”と手を切って非合法活動に入り、コントロールを逃れてユダヤのパレスチナ移住のために懸命になった。のちにイスラエル首相となったメナヘム・ベギンも、当時はそのグループのリーダーとして活躍し、イギリスのパレスチナ移民局を爆破したりして勇名を馳せた人であった。


(左)のちにイスラエル首相となったメナヘム・ベギン。
(右)メナヘム・ベギン率いるユダヤ人テロ組織「イルグン」が、
多くのイギリス人将校を狙って爆破した「キング・デービッド・ホテル」。
このことでイギリス政府はシオニストのベギンをお尋ね者にした。
●西はジブラルタルから東はスエズ運河まで地中海を掌握していたイギリスは、ユダヤ人のパレスチナ不法入国に対して、特に神経質になっており、それらの海に面している国々のユダヤ救済活動にまでいちいちくちばしを入れるようになった。
ユダヤ人がヨーロッパから密航するのを防ぐために艦隊を動員し、黒海や地中海の監視を厳しくしたのである。
ドイツ、オーストリア、チェコのユダヤ人たちは、この知らせを聞いてパニック状態に陥ったという。
●ブルガリア政府は1939年12月、イギリス政府から警告を受け、ユダヤ難民を乗せたブルガリア船に対しては厳重に取り締まること、もし見付けた場合は直ちに元の所に帰港させること、などを要求された。
ルーマニアでは、1940年1月、在ブカレストのイギリス大使館がルーマニア政府に圧力を掛け、ルーマニアの船がユダヤ人を乗せてドナウ河を黒海に向けて下ることを禁じ、同じく2月、ユーゴスラビア政府にも、他の国々と同じように圧力をかけて、「ユーゴスラビアの国旗を掲げた船に乗るユダヤ人を厳しくコントロールすること」、「必要な行先国のビザを所有しているか否かを調べる」、「パレスチナ行きの許可証を持っているかどうか?」などに始まって、パスポートに果たしてユダヤ人であることを示す「J」の印が押されているか? ということまで完全にチェックするよう、約束させたのであった。ユーゴスラビア政府はイギリスの要求のお蔭で、船会社の切符の売れ行きがガタ落ちになったとこぼしたそうである。


(左)パレスチナへ向かう途中、ロードス島についたユダヤ難民を乗せた船(1939年)。
(右)パレスチナ沖に到着したユダヤ難民の船。地中海を36日間旅してきて、
ここ1週間近く水も食料もない状態だったが、イギリス当局は全員を
不法移民として拘留キャンプへ送った(1939年)。
●イギリス政府のコントロールはやがて大西洋にまで及び、中米のパナマ政府は、ユダヤ難民の不法輸送に従事している多くのパナマ船をキャンセルするように強く要求され、また、リベリア政府は、リベリア入国の偽造ビザの取り締まりを強化するように警告された。
それだけではなく、イギリス外務省はユダヤ難民が通過するであろう国々に対しても通過ビザの発行停止を呼び掛け、不法移民を乗せた船舶を取りおさえること、入・出港を不可能にするような処置を取ることなどの要求をした。
しかし、国際法で定められた公海の航行の自由という原則があり、イギリス人は、これを如何に合法的に制限するか、ユダヤ難民の流れをどうすれば堰き止められるか……などについて、大いに研究を重ねたようである。
●イギリスの監視下に置かれた国はヨーロッパと近東を併せて12ヶ国及び中南米諸国であったが、特に始終接触したのはユダヤ人の退路にあった国々、すなわちルーマニア、ブルガリア、トルコ、ユーゴスラビア、ギリシアなどであった。

イスラエルのハイファ港に到着したユダヤ難民たち
イギリスはユダヤ人のパレスチナ入国を厳しく制限したため、
多くのユダヤ難民がボートピープルとして海上をさ迷った。
イギリス当局に不法移民として逮捕され、ハイファ
近くの収容所に収容された者もいた。
●イギリスの厳しい対策のために第二次世界大戦中に、ボートピープルとして海上をさ迷ったユダヤ人たちの悲惨な話は、いったいどれほどあったか見当もつかないほどだと言われている。
●数あるエピソードの中でも「ストルマ号事件」は、ユダヤ人のイギリスに対する恨みと憤りをひときわ買った事件であった。
1941年12月、769人のユダヤ難民を乗せ、ルーマニアを出港した「ストルマ号」が、イギリスによって上陸を禁止されて2ヶ月以上も海上をさ迷ったあげく、最後には沈没してしまったのである。
ユダヤ人たちにとって、この「ストルマ号事件」は、イギリス人の本性を如実に示す例として、いつまでも忘れることの出来ない事件と言われている。ユダヤ人のある者たちはこの復讐を誓って、1944年11月、当時カイロに来ていたイギリスの植民地担当大臣モイン卿を暗殺した。
●「ストルマ号」沈没の知らせが入った時、イギリス上院のディヴィス卿は「イギリス政府はヒトラーの政策を助けているのか?」と、極めつけた。これに対してクランボーン卿は、イギリス政府の名において次のように応えたとのことである。
「この問題は、今日取り挙げない方が賢明というものでしょう……」
◆
●1942年12月、イギリス議会(下院)で、リバプール選出のシドニー・シルバーマン議員が、アンソニー・イーデン外相に対し、「ドイツが全てのユダヤ人を東ヨーロッパへ追放し、彼らの殺害を計画している」という説の真偽を質問した。
それに対し、イーデン外相はこう答えている。
「その通りであります。占領下のヨーロッパで、ドイツの支配の下に置かれているユダヤ人が、野蛮で非人道的な扱いを受けているということに関し、最近、信頼すべき報告が政府に届いていることを、議会の場でご報告申し上げねばならないのは、たいへん遺憾なことであります」

アンソニー・イーデン外相
●このようにイギリス政府は、ヒトラー政権下のユダヤ人の悲惨な状況を、明確に把握していたのである。しかし、イギリス政府はユダヤ難民に対して冷淡・無関心な姿勢を改めることはなかった。
■■第4章:ユダヤ難民に冷淡だったアメリカ政府
●1930年代末、ユダヤ人の追放、処刑、殺害といったニュースがナチス占領下のポーランドから伝わってきた時、アメリカはそれでも難民受け入れの意志は見せなかった。ルーズベルト大統領はユダヤ人の収容地として、ドミニカ共和国を候補地として考えていたようである。
スペインは40万人のユダヤ人に対して、行先国のビザを所有する者に限って通過を許可したが、そのような時もアメリカは知らぬ顔を通した。
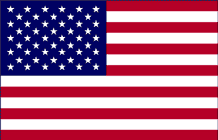
●1930年代のアメリカでは、ユダヤ人が政府の職に多く就きすぎていると考える者が24%、ヨーロッパでユダヤ人が迫害を受けているのは彼ら自身の責任であると思う者が35%で、ドイツから多数のユダヤ人がアメリカに亡命してきたら受け入れるべきかという問いに対しては、回答者の77%が否定的だった。
また、大西洋横断無着陸単独飛行に世界で初めて成功したチャールズ・リンドバーグは、第二次世界大戦へのアメリカの参戦に反対し、「ユダヤ人とイギリスとルーズベルトがアメリカを参戦させようとしている!」と主張した。彼はその後も親ナチス的な言葉を口にし、大戦中、反ユダヤ主義を公然と支持したことで知られている。

第32代アメリカ大統領
フランクリン・ルーズベルト
●ナチスに追われたユダヤ人の波が押し寄せ始めた時、アメリカは1939年6月の「スミス法」で外国人受け入れの取り締まりを強化し、続いて1941年の11月には「ラッセル法」を制定してビザ発行を制限した。
それゆえ、ヨーロッパのアメリカの出先機関は事実上、その面の機能を停止したも同然であった。
ナチスは初めの頃はユダヤ人が自由に国外に逃亡するのを黙認していたが、それを禁ずるために引いたデッドラインは1941年8月で、実施し始めたのはその年の10月下旬だから、それまでにアメリカがもっとユダヤ人を受け入れていれば、ユダヤ人殺戮の犠牲にならずに済んだ人もかなりいたであろうと言われている。逆にアメリカは、それらの人々にとって最も貴重な時期に、2つの法令を以てユダヤ人の足を二重に縛ったわけである。
●それまでにも、イギリスからユダヤ人の受け入れの催促を受けた時、「戦争が済んだ後、それらのユダヤ人たちが再びイギリスに戻る、という保証がない限り受け入れられない」と言い、その後1940年になって現実に受け入れたのは、わずか3万6000人あまりに過ぎなかったのである。そして、その後からも1日に20~30人のみの審査をするといった悠長さであった。
1942年に、ソ連領域内のユダヤ人母子1万人を、ソ連から他国に移動させるのを手伝う用意があると、アメリカ政府が声明を出したが、これとてアメリカは自国に引き取るというのではなく、具体的には「ソ連からペルシアに集結した難民1万人を、メキシコに送る輸送料を受け持つ」というものであった。
既に、その年の8月に在スイスのアメリカ大使館からの報告で、「ナチスが、ヨーロッパにおいて大量のユダヤ人を殺害する計画を企てている」と、聞かされた時もアメリカ政府筋は、「ユダヤ人の被害妄想的プロパガンダ」としか受け取らなかったのである。
◆
●なお、ルーズベルト大統領夫人のエリノア・ルーズベルトが、ユダヤ人たちをアメリカ、もしくはアフリカに受け入れるべきであると世論に訴えたこともあったが、その気のないアメリカ国務省は船舶不足を理由に、夫人の提案を退けてしまった。そして、「ナチスのスパイが潜入していることも考えねばならない……」と付け加え、さらに「いずれにせよ、我々はユダヤ問題に関わり合う立場ではない」と、一切の救援を拒否する態度を明らかにしたのであった。
また、国際的に活躍していたアメリカのランドール女史が「アメリカは、移民法を現行のままでも最少限50万のユダヤ人を救うことが出来るはずである。私たちは末長く、兄弟を裏切った者と呼ばれたいのですか?」と訴えたが、これも空しく響いただけであった。
アメリカ政府としては、ユダヤ人の虐殺の情報管理を秘密にして、一般市民には出来るだけそれらの情報が洩れないように努めたのであった。市民たちから集会やデモなどによって突き上げられるのを恐れたためである。
●1943年、シュテフェン・ワイスという事業家が、スイスにプールにしてある私財を投じて、およそ7万人のユダヤ人をナチスに賄賂を使って救出することを考え、着々と準備していたが、アメリカ国務省がこのプランのためには動こうとせず、その上、イギリス政府も7万のユダヤ人を救った後のことを憂慮して、協力することを拒んだのであった。
シュテフェン・ワイスとその仲間達は、このときの状況について「これはイギリス的冷酷と二枚舌の悪魔的な結合であり、これでは死刑宣告と同じだ」と言って、嘆いたという。
●第二次世界大戦中のアメリカ政府によるユダヤ人救済政策の手ぬるさを厳しく批判した歴史家ダヴィッド・ウェイマンは、著書『招かれざる民 ─ アメリカとヨーロッパ・ユダヤ人の虐殺』の中で次のような指摘をしている。
「ドイツとオーストリアにいたおよそ70万のユダヤ人のうち、その半数が第二次大戦開始前までに外国へ移住、逃亡した。そのうちアメリカが10万人、パレスチナが10万人弱、イギリスは5万人、そしてその他の諸国が5万人弱のユダヤ人を受けいれた。残る30万ほどのドイツとオーストリアのユダヤ人の多数が、ナチスによる絶滅計画の犠牲になることになる。
そして第二次世界大戦の開始によって、ドイツの支配下に入ったポーランドへ向けて、各地からユダヤ人の強制輸送が始まる1941年10月には、ナチス第三帝国支配下の地域からのユダヤ人の移住は禁止され、海外への逃亡の道は全く閉ざされることになるのである。」
◆
●リトアニア生まれのユダヤ人であるソリー・ガノールは、少年時代にナチスの迫害にあい、「ダッハウ収容所」に収容されたが、アメリカの日系人部隊によって救出されたという。
彼はこの時の体験を、著書『日本人に救われたユダヤ人の手記』(講談社)にまとめているが、彼はナチスが迫ってくる頃、全く偶然、杉原千畝氏に出会い、杉原夫婦を自宅に招いたという。そして、杉原千畝氏から早期の脱出をアドバイスされるが、決断が遅れ機を逃してしまい、このことはまさに一生悔やまれたという。


(左)リトアニア生まれのユダヤ人ソリー・ガノール
(右)彼の著書『日本人に救われたユダヤ人の手記』(講談社)
●この本には、当時のアメリカ外交官について、次のような記述がある。
「リトアニアの臨時の首都カウナスは長年にわたり、ユダヤ人がよそからの干渉をほとんど受けることなく暮らすことのできる、ヨーロッパで数少ない場所のひとつで、ユダヤ人は強固なコミュニティを築き上げていた。私が11歳のとき、第二次世界大戦が始まり、一転して恐怖に満ちた日々となった。カウナスは、ナチの手を逃れ、避難場所を提供してくれる国を必死に探し求める人々であふれかえる、ふきだまり地点と化した。彼らの多くが断られ、あちらの政府こちらの当局から追い返された。アメリカ、イギリスの政府もそうであった。」
「ダッハウ収容所で5歳年長のベルトルトと一緒に過ごすことが多くなった。ベルトルトの一家は、私の家族と同じように、もう少しでアメリカに渡るところだった。ポーランド駐在のアメリカ領事は最初、問題はないといっていた。ところが、ベルトルトの母親がユダヤ人で、父がポーランド社会党のメンバーであるのを発見すると、『わが国にアカはいらん。それにユダヤ人が洪水みたいにやってきては困るんでね』と手のひらをかえした。これをきいて、日ごろ温厚なベルトルトの父親が領事に飛びかかり、なぐりたおしてしまったという。
『これでアメリカ移住はおじゃんさ。あげくの果てに、お袋と弟はアウシュヴィッツに送られ、おやじはワルシャワ蜂起のときに殺されたよ……』
ユダヤ人を差別したこのアメリカ外交官と、カウナスの、あの日本人領事代理(杉原千畝氏)はなんと違っていたことか!」
◆
●アメリカを代表する歴史家の一人、ボストン大学のヒレル・レビン教授(ユダヤ学研究所所長)も、次のように語っている。
「いくら日本政府に何らかの損得勘定があったにせよ、日本側の対応は当時のアメリカ政府の非協力的な対応に比べれば文字通り、天と地ほどの差がある。もしアメリカ政府がもっと積極的にユダヤ人救済に手を差し伸べていたら、さらに何百万という命が助かっていたはずだからだ。
だがアメリカは、杉原がユダヤ人に対するビザの大量発給に注いだのと同じくらいの努力を、ビザを発給しない方向に使ったのだ。
当時から多くのユダヤ系移民がいたアメリカでは、ユダヤ人勢力が社会にも相当な影響力があったはずである。にもかかわらず、なぜアメリカはユダヤ人を救済しようとしなかったのか? この問題はかなりのミステリーと言わざるを得ない」

ボストン大学のユダヤ人
ヒレル・レビン教授
※ 追記:
●第二次世界大戦中、アメリカはユダヤ人に対する入国査証の発給を非常に制限し、ほとんどシャットアウトの政策であった。
明治学院大学法学部教授の丸山直起氏は、著書『太平洋戦争と上海のユダヤ難民』(法政大学出版局)の中で、次のように述べている。
※ 各イメージ画像とキャプションは当館が独自に追加

『太平洋戦争と上海のユダヤ難民』
丸山直起著(法政大学出版局)
「アメリカのルーズベルト大統領はユダヤ難民の境遇に同情し、亡命者あるいは難民としてアメリカに入国した多くの優秀なユダヤ人の能力を高く評価し、彼らを通じてドイツ国内の悲惨な状況を把握していた。しかし、移民法を改正してユダヤ難民のために門戸を全面的に開放することまでは考えなかった。
1939年5月、ユダヤ難民を乗せドイツからキューバに到着したものの、アメリカを目前にヨーロッパに送り返された『セント・ルイス号』難民の悲劇ほど、ユダヤ難民に対するアメリカの冷淡さを象徴する事件はなかった。
また、1942年以降、ユダヤ人虐殺の悲報がホワイトハウスに届けられたにもかかわらず、ルーズベルト大統領は積極的な行動に出ようとはしなかった。


ユダヤ難民を満載した客船「セント・ルイス号」(1939年)
ユダヤ難民937名を乗せた「セント・ルイス号」は1939年5月、
ハンブルクを出航したが、当初の目的地キューバで上陸できず、アメリカ
からも入国を拒否されて空しくヨーロッパへ戻った(乗客の大半は後に殺された)。
他にも「オルディナ号」「クワンツア号」「フランダース号」などの難民阻止事件があった。
1943年10月6日、ワシントンでナチスのユダヤ人虐殺を糾弾する正統派ユダヤ教徒による集会と行進が挙行された際、ユダヤ教のラビ代表とルーズベルト大統領との会見の調整が試みられたが、ルーズベルトは、こうした会談は国務長官が行うべきであると判断し、ホワイトハウスを訪れたラビ代表に対して、その到着前に外出し会見を回避する道を選んだのであった。〈中略〉

ワシントンで抗議デモを行う正統派ユダヤ教徒たち(1943年)
※ ヒトラーの迫害でたくさんのユダヤ人が犠牲になるなか、
アメリカは救出に何の手も打たなかった。1943年10月6日、
400名を越える正統派ラビがワシントンで抗議デモを行った。
一行はホワイトハウスに到着し、ルーズベルト大統領に
直訴しようとしたが、大統領は会うのを拒否した。
正統派のユダヤ教団体は、ヨーロッパのユダヤ人を脱出させるため、パスポートやビザなどを偽造したが、アメリカのユダヤ人社会の指導者たちはこうした不正な方法に反対し、自国の移民政策に反してまで気の毒な難民に支援の手を差し伸べる気はなかった。
とりわけ、ポーランドで救援を待ち望む聖なるユダヤ教学者を救うことこそ、何ものにも優先すべきとする正統派ユダヤ教団体と、アメリカ国内世論の動向に神経質なスティーブン・ワイズら米国ユダヤ人社会の指導者たちの対立は深刻であった。
例えば、1940年8月初めにアメリカの主要ユダヤ人団体が参加した会議で、正統派のラビ(ユダヤ教指導者)たちは、リトアニアから3500人のラビ、学生たちを入国させるための特別ビザを発給できるよう国務省に圧力をかけて欲しいと要請したが、スティーブン・ワイズらは、これほど多数のユダヤ人を定住させることは容易ではないとして、アメリカ政府に圧力をかけることに反対したのである。
アメリカのシオニスト運動指導者たちは、ホロコーストの間もパレスチナに将来のユダヤ人国家を建設する計画に精力を傾けており、ヨーロッパのユダヤ人の救済は二の次であった。」
以上、丸山直起著『太平洋戦争と上海のユダヤ難民』(法政大学出版局)より

スティーブン・ワイズ博士
彼はアメリカのユダヤ指導者階級の
中心人物のみならず、全世界のユダヤ人の
指導者ともいうべき人だった。ルーズベルト大統領の
ブレーンの中でも随一であり、大統領ある所には、
必ず影のように彼がついていたと評され、その
政策を左右する実力を持っていた。
このワイズ博士ら米国ユダヤ人社会の
指導者たちと、正統派ユダヤ教団体
の対立は深刻であったという。
※ さらに追記:
●アメリカの孤立主義の指導的代表者だったハミルトン・フィッシュ(元下院議員)は、著書『日米・開戦の悲劇 ─ 誰が第二次大戦を招いたのか』(PHP文庫)の中で、「ルーズベルトはユダヤ難民に無関心だった」と告発している。
少し長くなるが参考までに紹介しておきたい↓


(左)ハミルトン・フィッシュ (右)彼の著書
『日米・開戦の悲劇』(PHP文庫)
… ハミルトン・フィッシュの略歴 …
ハーバード大学を卒業し、第一次世界大戦に
従軍の後、1919年、米国下院議員に選出され、
1945年まで12回にわたり選出される(共和党員)。
アメリカの孤立主義の指導的代表者であり、ルーズベルト
大統領の外交政策を鋭く批判した。1991年没。
「1942年の初めに、私はヒトラーの非人道的な人種差別政策と、ドイツ、ポーランドにおける、何百万人にものぼるユダヤ人の虐殺を非難する決議案を議会に提出した。
これに対して、国務省はよくわからない理由から、虐殺について何も知らないと主張して、全世界の国々にユダヤ人に対する残虐な虐殺に反対するよう呼びかけようという私の提案の採択を妨害したのだった。その時には、ヨーロッパ中の国が、すでにヨーロッパのユダヤ人に対する残忍な虐殺を知っていたのだ。
しかるに、ルーズベルトの国務省は、説明のつかぬ、わけのわからぬ理由で私の提案に反対したのだった。」
「ユダヤ人のベン・ヘクトは、その自伝の中で、次のように述べている。
『ルーズベルト大統領が、ユダヤ人の虐殺を防ぐ人道主義のために、指一本上げなかったこと、ユダヤ人の置かれた境遇に対して消極的なコメントを繰り返したこと、史上最悪の大虐殺に対し無関心だったことは──』理解し難い。
ベン・ヘクトは、続けて、『ルーズベルトの首席秘書官でユダヤ系のデビット・ニイルズから、大統領はドイツのユダヤ人殺戮を非難するような演説や声明を発表したりしないだろう、ということを知らされた』とも書いている。
我々は、ベン・ヘクトの勇気のみならず、彼のこの問題に対する先見性を高く評価しなければならない。
彼は『次の事件』と題された、一幕物の劇を完成しようとしていた。
それは、ルーズベルト大統領が歴史の証言台の前に立たされ、お前はユダヤ人を救うために何をしたのかを述べさせられるのである。そしてナチの火葬場から蘇った12人のユダヤ人が、事件を裁く陪審員を務めるのだ。
ベン・ヘクトはビバリーヒルズ・ホテルで、この原稿を書き終えた時、ちょうど、ルーズベルトの死が発表されたのを、ラジオで聞いたのだった。
私は、ベン・ヘクトを心から尊敬する。
彼は、『ルーズベルト大統領は世界中の人々と、中立国であろうとなかろうと、すべての国に対し、ナチス政権(ヒトラー)にその絶滅政策を止めるよう要求する、人道的なアピールを行うべきであり、さもなくば全世界が道徳的汚名に苦しむことになる』と主張するだけの、先見の明と勇気を持ち合わせていたのである。
もしホワイトハウスから、そのような声明がはっきりと発表されていたならば、ヒトラーの誇大妄想を止められたかもしれないし、少なくとも、ヒトラーの残虐さについて、おそらく全く知らないドイツ、ポーランド国民に、真相を教えることができたであろう。
〈中略〉
1943年の初めには、世界中のすべての国と政府が、ヒトラーのユダヤ人撲滅政策を知っていた。
ルーズベルト大統領と国務省は、恐るべき虐殺行為を容赦なく世界の耳目に曝(さら)すべきであったのだ。そして、すべての連合国と中立国に対し、国際法と人道にもとる、無防備の人種的、宗教的少数派を絶滅させようとする恥ずべき政策を止めさせるために、ヒトラーとナチス・ドイツに公的に影響力を行使するよう要請すべきであった。」
以上、ハミルトン・フィッシュ著『日米・開戦の悲劇』(PHP文庫)より
■■第5章:空振りに終わってしまった米英両国共催の「バミューダ会議」
●1942年1月、ロンドンの聖ジェームス宮で、ヨーロッパ17ヶ国の亡命政府の会議が催された時、ルクセンブルク代表を除いて、ユダヤ人虐殺をテーマに取り挙げた者はいなかった。また、その時の共同声明の中にも、ユダヤ人に対するナチスの犯罪を断罪する言葉は全く見られなかった。
連合国側の態度に憤慨した在ロンドンのポーランド亡命政府は『デイリー・テレグラフ』紙に声明文を載せ、ポーランドでユダヤ人がいかなる試練を受けているかを詳細に訴えた。一般の人々が真のユダヤ人迫害の凄惨な事実を知らされたのは、これが初めてだったと言われている。
●イギリスやアメリカでぼつぼつ市民大会が催されるようになったが、ナチスのユダヤ人迫害に対する批判が世論の形をとって起こったのは1942年も終りに近い頃、つまり、ナチスがユダヤ人迫害を開始してから10年目を迎えようという頃であった。
その時でさえイギリス政府は乗り気ではなく、(第3章で触れたように)アンソニー・イーデン外相はその年の12月の半ばに至って、ようやく下院でポーランドや東ヨーロッパで行われているユダヤ人迫害についての報告をした。「ヒトラー政権はどう見てもユダヤ民族を、ヨーロッパから駆逐するというかつての宣言を実行しているとしか考えられない」と。
でも、それでもなお、具体的にユダヤ人救済にはどうすればいいかという討議や、ナチスの残虐行為に対して制裁とか威嚇を検討するといったようなことは起こらなかった。

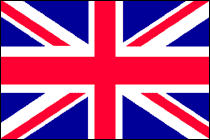
イギリスの外務大臣アンソニー・イーデン
●「この期に及んでイギリス政府は何故、ユダヤ人救済の手を打たないのか?」
と、腹を立てた劇作家ジョージ・バーナード・ショーをはじめ、ハロルド・ニコルソンなど、作家や政治家たちが署名して抗議をしたのであったが、それに対してさえもまったく反響はなかったのである。

ジョージ・バーナード・ショー
イギリス近代演劇の確立者。
1950年に94歳で亡くなるまで53本
もの戯曲を残した。1925年に
「ノーベル文学賞」を受賞。
●ようやくイギリスが、ともに難民受け入れの政策を検討しようとアメリカ政府に提案したときも、応答を得られるまでに2ヶ月かかったのである。
そういったのんきさに業を煮やしたイギリスのカンタベリー司教は上院に、「事は急を要するのである。イギリスは直ちに入国査証制度を検討し、改正すべきである」と訴え、やっとのことでイギリスとアメリカがバミューダ島(北大西洋に位置するイギリスの海外領土)で「難民対策会議」を共催したのであった。
1943年4月のことである。
●しかし、この時もイギリス政府のスポークスマン、クランボーン卿は「ユダヤ人問題ばかりに重点を置くのは誤りである」といなしており、アメリカのコーデル・ハル国務長官も「我が国はユダヤ難民に対して、特別の処置を取ることは出来ない」と、まず釘を刺したのである。

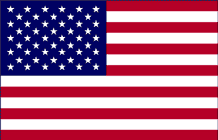
アメリカの国務長官コーデル・ハル
有名な『ハル・ノート』を日本に突き付けて、
日本政府を挑発した男。1945年に
「ノーベル平和賞」を受賞。
●この「バミューダ会議」では相変らず実行不能な空論ばかりが飛び出し、
傍聴していたイギリス自由党のエマニエル・セラーは「人間の福祉と理想を裏切る地上最低の会議」と非難した。
実際にユダヤ人の迫害が日々進行している緊急の時に、出席した28ヶ国は、英・米両国を含めて一国としてユダヤ人受け入れを了承しないばかりでなく、それを避けるために汲々としていたことを、当時の議事録は物語っている。
●この「バミューダ会議」について、アーロン&ロフタス著『汚れた三位一体〈バチカン・ナチス・ソ連情報部〉』には次のような指摘が書かれている。
「1943年4月、イギリスとアメリカの高官レベル会議(バミューダ会議)で、ナチス・ドイツのユダヤ人迫害政策に対しては、何もすべきではないことが正式に決まり、大量救出のためのあらゆる計画が放棄された。イギリス外務省とアメリカ国務省は、ナチス第三帝国がユダヤ人迫害を中止して、強制収容所を空っぽにし、(数百万でないにせよ)数十万人のユダヤ人の生き残りが西側に流れ込むことを心配したのである。
1943年も終わり頃、イギリス外務省は、ドイツヘの対応があまりに強化されれば、現実にこの事態が起こりかねないとの懸念をアメリカ国務省に明示した。1943年春に開かれたバミューダ会議の秘密報告書は、ユダヤ人の入国を望む国が1つもなかった事を明らかにしている。アメリカ、イギリス、カナダに大量疎開させるより、ヒトラーに任せておく方が得策、と彼らはみたのだ。ユダヤ人は戦争行為の消耗品だったのである。」
◆
※ 追記:
●ドイツのボン大学で日本現代政治史を研究し、論文「ナチズムの時代における日本帝国のユダヤ政策」で哲学博士号を取得したハインツ・E・マウル(元ドイツ連邦軍空軍将校)は、著書『日本はなぜユダヤ人を迫害しなかったのか』(芙蓉書房出版)の中で、この「バミューダ会議」の実態について次のように書いている。


(左)ハインツ・E・マウル(元ドイツ連邦軍空軍将校)
(右)彼の著書『日本はなぜユダヤ人を迫害
しなかったのか』(芙蓉書房出版)
「1942年6月、アメリカは突如入国規制を強化する。背景には市民の反ユダヤ感情、反移民感情があった。
ユダヤ人を救うことは政治目標の達成をさまたげ、戦争完遂に有害だと考えられたのだ。それに、アメリカのユダヤ人には政府の後ろ盾が欠けていた。この措置をロング国務次官が提唱したことは興味深い。ロング国務次官は東欧のユダヤ人に強い偏見をもっていた。」
「1943年4月19日、米英両国は『バミューダ会議』を開催した。
目的は戦争難民問題の解決であったが、現実には欧州のユダヤ人を助けようとするあらゆる努力を阻止することにあった。アメリカが外務省員のほかには、この問題に無知な二級政治家を代表として送ったことは、アメリカの姿勢を反映しており、ロング国務次官はこの会議で大きな役割を演じたのだった。」
■■第6章:なぜアウシュヴィッツは破壊されなかったのか?
●ナチス・ドイツによるユダヤ人迫害はとどまるところを知らなかったが、これを阻止するため、アウシュヴィッツ爆撃に踏み切ってその近辺のユダヤ人殺害のルートを破壊することにより、その殺害システムに打撃を与えようとの計画があった。
そのためにスパイがワルシャワに送り込まれ、その筋の戸棚の奥深くに保管してあったアウシュヴィッツの詳細なレイアウトを示した図面を盗み出すことにも成功し、一方、アメリカ空軍の撮影した写真により、技術的にも戦略的にも爆撃によるユダヤ人救済の十分な可能性の見通しが立ったのである。
しかし、そのプランは「アウシュヴィッツは軍事施設ではない」という理由で、実行されなかったのであった。

アウシュヴィッツ収容所
「アウシュヴィッツ」はドイツ名であり、ポーランド名は「オシフィエンチム」。
現在のポーランド領オシフィエンチム市郊外に位置する。「アウシュヴィッツ収容所」は
「第一収容所」、「第二収容所(ビルケナウ)」(1941年建設)、「第三収容所(モノヴィッツ)」
(1942年建設)に区分され、それ以外に38の「外郭収容所」や「付属収容所」があった。
「第一収容所」はポーランド軍兵営の建物を再利用したもので、SS長官ヒムラーの指令
により1940年4月に開設され、最初の囚人はポーランド人政治犯だった。
●戦後、『アウシュヴィッツで私は14歳だった』という本を書いたアナ・ノヴァクは、1982年4月17日の『ル・ヌーベル・オブセルバトゥール』誌のインタビューに応えて、重大な証言を行っている。
彼女の言葉によれば、アウシュヴィッツ爆撃をやらなかった連合軍はその代わりに、アウシュヴィッツで強制労働させられていた囚人たちを、機銃掃射したのだそうだ。地をはうようにしてやって来た戦闘機の群れに狙われたユダヤ人たちは、連合軍からも殺されたわけである。
「私たちユダヤ人は、強制収容施設を爆撃してくれることを、毎日どんなに待っていたか知れません。ところが、首を長くして待っていた結果がこれでした。それは、アウシュヴィッツ収容所に対して抱いていた絶望感よりも、もっともっと大きな絶望感を私たちに与えました。戦後、そのことについては誰も語りたがらないのです。連合軍は、何故あんなことをやったのでしょうか? きっと、これに答えられる人は一人もいないでしょう」
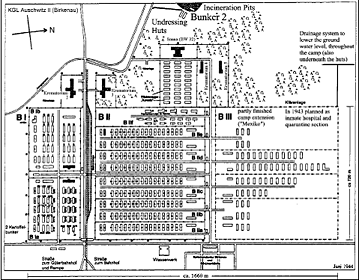
アウシュヴィッツの「第二収容所(ビルケナウ)」の全体図
「第二収容所(ビルケナウ)」の総面積は東京ドーム37個分で、この広大な
敷地に300以上の囚人棟(レンガ造りのバラック)が並んでいた。またこの敷地
にはアウシュヴィッツの象徴でもある「強制収容所内まで延びる鉄道引き込み線」や
病院(人体実験の施設でもあったとされる)、防疫施設、プールなどもあった。
●戦時中、連合軍はアウシュヴィッツの「第三収容所(モノヴィッツ)」の石油精製所は爆撃したようだが、囚人を逃がすことを目的にはしていなかった。

アウシュヴィッツの「第三収容所(モノヴィッツ)」
この収容所は被収容者を労働力とする「強制労働収容所」であり、
収容所内の工場は「I・G・ファルベン社」が操業を行っていた。
その他にも「クルップ社」「ジーメンス社」「ウニオン社」
といった大企業の工場も置かれていた。
●結局、連合軍は、アウシュヴィッツの管理施設はおろか、アウシュヴィッツへ続く鉄道線路を空爆することすらしなかったのだ。
ユダヤ人を運ぶ移送列車の鉄道線路を、「普通」に破壊するだけでもアウシュヴィッツの機能は混乱(麻痺)し、多くのユダヤ人が救われたというのに……。アウシュヴィッツに対して何もしなかった。

ユダヤ人の強制収容所への移送は、鉄道を使用して大々的に実施された。
「第二収容所(ビルケナウ)」には鉄道線路が真っ直ぐ「死の門」と呼ばれる
正面ゲートをくぐって敷地内にまで引き込まれており、大勢のユダヤ人が
極めて粗末な貨車に詰め込まれてヨーロッパ各地から移送されてきた。
この貨車には換気用の窓もなく、水のバケツと排便用バケツが1個
ずつ置いてあるのみだった。喉の渇きと急速に悪化する衛生環境
の中で、到着を待たずに命を落とした人は少なくなかった。
※ 大勢の人間を家畜同然の扱いで詰め込んでいた貨車は
まさに「移動式収容所」と呼べる代物であった。
●なぜ、連合軍はアウシュヴィッツを無傷のまま「放置」したのだろうか?
この謎について、次のように説明する人がいる。
「戦時中、連合軍は、ヨーロッパ文明のただ中で、これほどの野蛮が進行しているとは信じられなかったし、信じたくもなかったのだ。『ガス室』のおぞましい実態は、戦後、明らかにされた。もし、戦時中に『ガス室』の存在を知っていたら、直ちに爆撃していただろう」
●なるほど、このような説明は、一見もっともらしく聞こえる。
しかし、このような説明は鵜呑みにすることはできない。
なぜならば、戦時中、連合軍の飛行機は、アウシュヴィッツや周辺地域にポーランド語・ドイツ語の「宣伝用パンフレット」を多数ばらまいていたのであるが、そのパンフレットには、「収容所内の人々が『ガス』で殺されている」と書かれていたのである。しかも、連合国ラジオ局によってもヨーロッパに放送されてもいたのだ。
つまり、連合軍は「ガス室」の存在を知らなかったどころか、むしろ積極的に「ガス室」の存在を宣伝していたのである。しかも驚くことに、イギリスはアメリカの参戦前から「ガス室をつかった虐殺」という対ナチ・プロパガンダ作戦を展開していたのである。

アンネ・フランク
オランダにいたアンネは『日記』の中で、
「イギリスから送られてくるラジオ放送によると、
ユダヤ人はみんな毒ガスで殺されているそうです」
と書いている(日付は1942年10月9日)。
●特に、「イギリス治安調整局(BSC)」という組織は、戦時中、協力関係にある新聞やコラムニストと通じて、「いかにナチスが占領地で残虐であったか」というような内容のニュースを無数に配信し、キリスト教徒のアメリカ人の同情を得るために、「ナチスが教会や修道院を破壊している」といった内容のニュースも多数流し続けた。
しかしこうしたニュースの中には、全く事実にもとづかず、はじめからイギリスの情報機関によって捏造されたものも多く含まれていた。この「対ナチ・プロパガンダ作戦」には、ハリウッドの映画製作者、作家、技術者たちも大勢参加し、立て続けに反ナチスの「プロパガンダ映画」が作られたのであった。
※ この英米の「対ナチ・プロパガンダ作戦」の実態については、別のファイルで詳しく触れたい。
●いずれにせよ、西側連合国はアウシュヴィッツの囚人を解放するチャンスはいくらでもあったのに、恐ろしいほど完全に黙殺したのである。いや、上のユダヤ人女性の証言が正しければ、彼らは黙殺したどころか、囚人たちに機銃を浴びせたことになる……。
●半生を、ナチの逃亡者と戦犯の追及に費やしたサイモン・ヴィーゼンタールはこう語る。
「大戦中、死の収容所の存在は早い段階で西側諸国に知られていた。だが、まるで問題にされなかった。
1942年7月2日のNYタイムズ紙の記事は『100万のユダヤ人虐殺される』だった。
アメリカ政府に嘆願書を送った。ナチスによるユダヤ人の移送を止め、アウシュヴィッツの施設を破壊してくれと。しかし、集中攻撃はなかった。繰り返し爆撃が行われたのは郊外の工場だった。連合国にとって、ユダヤ人の救済は優先度の低い問題だったのである」

サイモン・ヴィーゼンタール
●ところで、「三菱化成生命科学研究所」の室長である米本昌平氏は、1989年に著わした本『遺伝管理社会 ─ ナチスと近未来』(弘文堂)の中で、次のように述べている。
参考までに紹介しておきたい。
「……実は、アウシュヴィッツが今日見学できるのは不思議なことなのである。この点で、M・ギンベルトは『アウシュヴィッツと連合軍』(1981年)という重要な本を書いている。ここでM・ギンベルトは、すでに1944年の後半は、ドイツの制空権の一部は連合軍の手中にあったのに、爆撃されたのは軍事施設に限られ、アウシュヴィッツ収容所には一発も落とされなかった謎を問題にしている。
確かにこれは奇怪なことである。連合軍がドイツの軍事施設ばかりか大都市までをも徹底的に破壊したのに、人類が作った最大の悪魔的施設、アウシュヴィッツがなお無傷のまま残り、しかも最近までこの不思議さに誰も気づかなかったとは……」


アメリカ軍が戦時中にアウシュヴィッツを上空から撮影した写真(1944年)
※ 戦時中、連合軍はアウシュヴィッツの囚人を解放する
チャンスはいくらでもあったのに、完全に黙殺した
●また、同志社大学の名誉教授である望田幸男氏も、著書『ナチス追及』(講談社)の中で、(さらりとではあるが)次のように指摘している。
「(上の写真は)1944年8月25日に撮影されたアウシュヴィッツの航空写真。貨車に乗せられた囚人たちが写っている。なぜこの写真を撮ったときに、連合軍は貨車のレールを爆破してしまわなかったのだろう?」
●ZDF(ドイツ公共放送局)の現代史局長であるグイド・クノップ(歴史学博士)もこう問いかけている。
「1944年に、アメリカ軍の偵察機は上空9100mからアウシュヴィッツ・ビルケナウの写真を撮影しており、火葬場をはっきり確認することができた。それなのにアウシュヴィッツが攻撃を受けることはなかった。爆弾を落とさず、写真を撮ったのである。
政府の圧制に強制されたわけでもなかった人々が、何も抵抗を企てなかったのはなぜか? 連合国はユダヤ人虐殺の開始について、非常に早い段階から情報を得ていた。彼らがドレスデンのフラウエン教会をそうしたように、アウシュヴィッツを爆撃し、虐殺機構を破壊しなかったのはなぜか?」

グイド・クノップ博士
●1993年春、アメリカのワシントンDCに総工費1億6800万ドルの「ホロコースト記念博物館」が落成した。その落成式典で、ノーベル平和賞受賞者のユダヤ人作家エリ・ヴィーゼルが演説を行ったが、その演説の締めくくりは次のような内容であった。


(左)1993年春、アメリカのワシントンDCに開設された「ホロコースト記念博物館」(落成式典の様子)
(右)博物館にあるエジスキー・タワー。ユダヤ家族のポートレート約6000枚で構成されている。
「なぜなのか? なぜ連合国側は強制収容所の機能を知りながら、爆撃を控えたのか? なぜユダヤ人の絶望的なナチス抵抗闘争を支援しなかったのか? 神は沈黙されるが、なぜ人間すら沈黙したまま、600万人のユダヤ人、世界のユダヤ総人口の3分の1が『歴史のブラックホール』に消えていくに任せたのか? 答えはない。この博物館は〈答え〉ではない。この博物館は〈疑問符〉なのだ……」
※ 英米はドイツと同じくキリスト教国である。だから、ユダヤ人に対する非人道的行為をあえて黙認したのだ、とエリ・ヴィーゼルは指摘している。
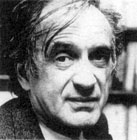
エリ・ヴィーゼル
ルーマニア出身のユダヤ人作家。
自らの強制収容所体験を経て反差別・
平和運動に尽力し、1986年に
「ノーベル平和賞」受賞。
●さて最後に繰り返しになるが、大戦中、連合国が本気でユダヤ人を救済しようと考えていたならば、迷うことなく直ちに「アウシュヴィッツ収容所」の破壊(妨害)工作に着手していたはずである。
しかし連合国は、アウシュヴィッツに対して何もしなかった。
多数の死者を出す収容所施設への大々的な爆撃までいかなくとも、ヨーロッパ各地から収容所まで続く鉄道線路を「普通」に破壊するだけでもアウシュヴィッツの機能は混乱(麻痺)し、多くのユダヤ人が救われたというのに……。
あの戦争中、連合国がアウシュヴィッツを無傷のまま「放置」した罪は大きいと思う。

数々の悲劇を生み出した「アウシュヴィッツ収容所」
※ 大戦中にこの収容所は連合軍の空襲に遭うことなく、最後まで
機能を発揮し続けた。もしこの「死の施設」が少しでも破壊されて
いたならユダヤ人の犠牲者はもっと少なくなっていただろう。
─ 完 ─
■■追加情報:『封印されたホロコースト』について
●『封印されたホロコースト ─ ルーズベルト、チャーチルはどこまで知っていたか』(大月書店)という本がある。

『封印されたホロコースト』
リチャード・ブライトマン著(大月書店)
●この本を書いたアメリカン大学のリチャード・ブライトマン教授は、次のような指摘をしている。
「大西洋の両側で、対外政策担当者たち(イギリス外務省とアメリカ国務省)は、ひどい失敗をやらかした。ホロコーストを少しでも止めるような西側の行動はなかった。
ナチス体制は外圧にはどちらかといえば鈍感だったが、ドイツ国民、ナチス衛星諸国、ドイツの加盟者たちは、そんなに鈍感ではなかった。最終解決の加担者に西側が確実に警告を発していたら、目に見える成果がもっと早くあがっていたはずだ。
もし1944年の夏と秋にアウシュヴィッツを爆撃していたら、それはヨーロッパのユダヤ人の殺戮に対する強い関心を、英米のそれまでのあらゆる声明や行動にまさる説得力をもって表明することになったのは確かだろう。しかし、西側政府が時間を──おおざっぱに言って1941年秋から『戦争難民委員会』の設置までの期間を──空費してしまったことのほうが、アウシュヴィッツ爆撃提案の拒否よりも、もっと基本的な誤りだったと思われる。」

この本を書いたアメリカン大学の
リチャード・ブライトマン教授
●さらにブライトマン教授は次のように述べている。
「ホロコーストの極めて重要な準備段階についてさえ、西側の文書の一部はいまだに公衆の目に触れていない。ハインリヒ・ヒムラーに関するイギリス陸軍省ファイルの中では、1つの文書がいまだに秘密扱いにされて抜き去られたままになっている。それは、なんと1994年までリストには“保留”と記載されていた。1943年から1945年まで帝国保安本部長官だったエルンスト・カルテンブルンナーに関する文書は、フォルダーごと非公開にされたままである。
アメリカでもこれに類したバカげた事例には事欠かない。
報道によれば、『NSA(国家安全保障局)』にはまだ非公開とされている第二次世界大戦時代の英米の文書十万ページ分があるという。戦略事務局関連文書と特定して私がFOIA(情報公開法)に基づいて出した請求や要請の一部は、4年以上もCIAの横槍で宙に浮いたままになっている。
遠い過去となった事柄についての重要情報を、歴史記録と公衆の目から隠している政府は、自国と世界に奉仕しているとはいえない。」
◆
●この本の巻末「解説」ページを担当した東京大学の石田勇治教授は、次のように書いている。
「西側連合国がナチス・ドイツのユダヤ人迫害・大量虐殺に対してどのような態度をとったかという問いは、戦後ながらく議論の対象にならなかった。1960年代初頭、アイヒマン裁判に関連して公開された一部の資料が、アウシュヴィッツに関する正確な情報をイギリスが得ていたのではないかとの疑念を惹起して注目を集めたことがあったが、本格的な研究は現れなかった。
1980年代に入って、イギリスの歴史家マーチン・ギルバートとアメリカの歴史家デイビット・バイマンがこの問題をそれぞれ別々に論じたが、本書は彼らの研究成果の延長上に書かれている。 」
「ホロコーストは戦後長らく学術的な研究テーマとはならなかった。イスラエルでホロコースト研究が本格化するのはアイヒマン裁判後のことだし、ナチ犯罪者の司法訴追を続けた戦後のドイツでも、ホロコーストの実証研究は1970年代後半まで数名の学者によって細々と続けられていたにすぎない。
それから20年あまり、ホロコースト研究は質的にも量的にも著しい発展を遂げた。とくに1980年代は、人権意識の鋭い、若い世代の歴史家たちの手で実証研究が進み、それまで忘れさられていた犠牲者集団にも解明の光があてられるようになった。
また冷戦終結後の欧米各国ですすむ歴史の見直しと新史料の発掘は、大戦下ヨーロッパの随所にホロコーストの受益者と『共犯関係』が存在した事実を明るみに出した。
今やホロコースト問題は、加害者と被害者、ドイツ人とユダヤ人だけの問題では済まなくなっているのである。」
■■追加情報 2:映画『戦場のピアニスト』の秘話
●2002年のカンヌ映画祭においてパルムドールに輝いた映画『戦場のピアニスト』──。
この映画は、ポーランドの名ピアニストであるウワディスワフ・シュピルマンが自らの体験を描いた回顧録を、ユダヤ人映画監督のロマン・ポランスキーが、幼い頃に直接体験したナチスの恐怖を原点に制作した作品である。


(左)映画『戦場のピアニスト』(2002年制作)
(右)ユダヤ人映画監督のロマン・ポランスキー
彼はフランス生まれのユダヤ人で、大戦中、両親が収容所に
入れられ、自らもユダヤ人狩りの対象とされて逃亡生活を送った。
1962年に『水の中のナイフ』で監督デビュー。1968年に結婚した
女優のシャロン・テートはチャールズ・マンソン・ファミリーにより惨殺。
1977年には自宅で13歳の少女モデルをレイプしたかどで逮捕され、
裁判で有罪の判決(実刑で50年以上)を受ける。彼は逮捕・収監を
避けるため「映画撮影」と偽ってアメリカを出国し、ヨーロッパに
渡り、そのまま逃亡犯となった(逃亡犯としての罪は未だに適応
されるため、以後アメリカへ一度も入国していない)。
●この映画の中で印象的だったのは、作品の前半(主人公シュピルマン家の夕食の場面)で、主人公の父親が口にしたセリフである。
簡単に紹介しておきたい↓
★主人公(シュピルマン家)の夕食の場面にて=(開始28分後のシーン)
◆弟(ヘンリク):「(兄貴は)寄生虫どもを相手にピアノ演奏か」
◆主人公:「寄生虫?」
◆母親:「2人ともやめて」
◆弟:「奴らはカスだ」
◆主人公:「なぜ?」
◆弟:「周りで起きていることに無関心だ」
◆父親:「アメリカが悪い」
◆主人公:「どうして?」
◆父親:「アメリカはユダヤ系が多い。だが何もしてくれない。大勢が飢えて死んでるのに」
◆父親:「ユダヤ系銀行家は、政府に宣戦布告を進言すべきだ」
 |
 |
 |
 |
●ところで余談になるが、この物語の主人公であるウワディスワフ・シュピルマンの息子、クリストファー・スピルマン(1951年生まれ)はアメリカのエール大学大学院で歴史学の博士号を取得した後、日本人女性(歴史学者)と結婚し、1998年に夫婦で福岡に移住して、現在、九州産業大学の教授を務めている。
彼が英語(翻訳本)ではなく日本語で直接執筆した『シュピルマンの時計』(小学館)は亡き父親への尽きぬ思いをつづったエッセイである。興味のある方は一読を。
※ ちなみに父親は「シュピルマン」で通っているが、本人はスピルマンの表記を使用している。念のため。



(左)ユダヤ人ピアニストのウワディスワフ・シュピルマン
(中)彼の息子であるクリストファー・スピルマン教授
(元ハーバード大学ライシャワー日本研究所の研究員)
(右)彼の著書『シュピルマンの時計』(小学館)
●長年、日本の歴史文化に深い関心を抱き続けているスピルマン教授は、子供の時に黒澤明監督の映画を見て、日本に興味を持ったという。彼の専門分野は近代日本政治思想史(特に第一次世界大戦から第二次世界大戦までの右翼思想の研究)だが、ナチス・ドイツと日本の違いについて次のように述べている。
参考までに紹介しておきたい。
「ナチス・ドイツと日本の軍国主義を比べると、日本ではこれといったイデオロギーもなく、大衆を魅惑する指導者もいませんでした。ナチスは大衆運動です。政権獲得時に100万人のナチ党員がいました。一方、日本の右翼は一種の集団主義を唱えながら、個人主義者が多かった。
日本の軍国主義は、第一次世界大戦以前の欧州の軍国主義に類似しています。これに対し、ナチスは全く新しい政治的現象です。
過去の歴史を客観的に、冷静に見る必要があります。日本の右翼思想は軍国主義に利用され、あるいは軍国主義そのものになってしまった。右翼思想とその問題点を研究することで、過去の過ちを繰り返す可能性が少なくなると思います」
●さらにスピルマン教授は先の世界大戦についてこう言及している。
「1937~38年頃、英仏両国がドイツに強硬策を取っていれば、ヒトラーはつぶせたと思います。でも、当時の政治家の多くは、第一次世界大戦の経験から戦争を避けたかった。第一次世界大戦時のイギリスのアスキス首相の長男も戦死している。だから、ナチス・ドイツが領土拡張に乗り出した時、イギリスのチェンバレン首相は戦争回避のため宥和政策を取りました。
あの時代、欧米諸国がユダヤ難民を助けなかったのは、無関心から。どうでもいいと思っていた。自分の息子が戦死したら嫌だという感情。アメリカ世論は孤立主義的で反戦的でした。
第二次世界大戦後も、どこかで戦争が起きています。虐殺はアフリカで頻繁に起き、カンボジアや旧ユーゴスラビアでもありました。世界大戦が教訓になっていません」
●ちなみにスピルマン教授によれば、父親は「ナチス」と「ドイツ」を分けて考えていたという。父親からは「1つの民族に、悪い人間もいれば、良い人間もいる。個人として判断しろ」と教えられたという。
また戦時中のことをほとんど話さなかった父親は晩年、「なぜ俺はあの時、一緒に死ななかったのか」という罪悪感を口にしたという。(スピルマン教授は日本の元特攻隊員からも、似たような心境を聞いたことがあると述べている)。
■■追加情報 3:なぜアメリカはユダヤ人の救済に消極的だったのか?
●なぜアメリカはユダヤ人の救済に消極的だったのか?
イギリスを代表する歴史家の一人、ポール・ジョンソンは著書『ユダヤ人の歴史〈下巻〉』(徳間書店)の中で次のように書いている。
参考までに紹介しておきたい。

『ユダヤ人の歴史〈下巻〉』
ポール・ジョンソン著(徳間書店)
「ユダヤ人難民を多数受け入れる能力があったのは、米国である。
ところが実際には、戦争中たった2万1000人しかユダヤ人移民を入国させていない。これは法律で定められた移民割り当て枠の10%にあたる数でしかなかった。その理由は一般大衆の反感である。米国在郷軍人会から外国戦争退役軍人協会に至るまで、愛国的団体はみな移民の全面的禁止を求めていた。
米国史上、第二次世界大戦中ほど反ユダヤ感情が高まった時期はない。世論調査によれば、1938年から1945年にかけて、人口の35~40%が、反ユダヤ的立法を支持していた。1942年の調査によれば、米国にとって、ユダヤ人は日本人とドイツ人に次ぐ大きな脅威とみなされていた。
1942年から1944年にわたる期間に、ニューヨークのワシントン・ハイツ地区で全てのシナゴーグ(ユダヤ教会堂)が冒涜されたが、この背景には広汎な反ユダヤ感情があった。
〈中略〉
具体的な行動を取るうえで大きな障害となったのは、ルーズベルト大統領その人である。彼には多少反ユダヤ的傾向があり、しかも状況について正確な報告を受けていなかった。この問題がカサブランカ会議で持ち出された時、大統領は、『ドイツ人がユダヤ人に対し抱いている不満は、理解できるように思う。彼らは人口のごく一部しか占めていないにもかかわらず、ドイツの法律家、医者、教師、大学教授の50%以上がユダヤ人なのだから』と語った。
ルーズベルトは国内の政治情勢のみ考慮していたように思われる。(米国内の)ユダヤ人の90%が大統領を支持しており、これ以上ユダヤ人のために行動する必要を感じなかった。組織的殺戮についての事実が明らかになった後でも、大統領は14ヶ月の間、何も行動を取ろうとしない。
1943年4月、遅まきながらこの問題に関する米英会議がバミューダで開かれたが、大統領は一切興味を示さなかった。そして会談の結果、具体的な措置は何も取りえないことだけが確認されたのである。
それどころか、『難民受け入れの可能性に関しては、ヒトラーへのいかなる働きかけもなされるべきではない』との警告が発せられたのだ。」
■■追加情報 4:ユダヤ難民に無関心だったアメリカの政治家たち
●なぜアメリカはユダヤ人の救済に消極的だったのか?
『ナチからの脱出』(並木書房)の著者ブライアン・リッグは次のように書いている。参考までに紹介しておきたい。
「アメリカの役人たちは、絶望的な状況に追い込まれたヨーロッパのユダヤ人たちが必死になって救いを求めても、耳を貸そうとしなかった。1938年の『エビアン会議』でドイツがユダヤ人の出国を認めるといった時も、アメリカの役人たちは応じなかった。
アメリカ政府部内で働くユダヤ人も、ヒトラーの迫害に苦しむ者に対して、充分なことをしなかった。歴史家のデイビッド・ワイマンによると、ルーズベルトに近いユダヤ人の大半は、『救出を促す行動などほとんどとっていない』のである。
ルーズベルトは大統領権限で移民当局にビザを発給させることもできたが、そのための必要な措置をとらなかった。さらに、外交手段や軍事手段を使ってユダヤ人殺害を阻止し少なくとも遅滞させることもできたが、歴史家ワイマンは『在欧ユダヤ人社会の計画的殲滅という歴史的重大事態に無関心であったことは、大統領としては重大な失敗」と断じた。」
「ナチ官僚はヨーロッパ列強の無関心を横目にしながら、ユダヤ人の迫害をした。悲しいかなアメリカも、ヨーロッパと同じであった。『エビアン会議』時に見られた熱のない国際社会の反応、そしてまた1938年の『水晶の夜事件』後の現象である外交圧力の欠如は、この無関心ぶりを如実に物語る。
歴史家のヘンリー・ファインゴールドは、『連合軍側の無関心、無行動のおかげで、ナチ政権は世界が反ユダヤの嫌悪感を共有している、と主張できた』と書いた。もっとも、1939年時点で国際社会が圧力を加えていたらナチ政府がユダヤ人迫害計画を変えたかどうか。その答えは推測の域を出ない。だが、ひとつだけ明言できることがある。それはアメリカが1938年または1939年から移民政策を変えていたら、それだけでも1941年末までに数十万の命が救われていただろう。」
「アメリカ人が移民制限を望んだ背景には、反ユダヤ主義があったと見られる。
ルーズベルトの報道官スチーブン・アーリーは、1941年7月29日付大統領あて報告で、次のように書いている。
『完全に無視されていますが、きわめて深刻な問題があります。それはしつこい反ユダヤ感情が中枢部に静かに広がっているということであります。あちこちに到るところに感知されます。ワシントンだけでなく地方でも、市井の人々が親ユダヤ的態度に反発し、憤慨するようになっています。謎のユダヤ難民が多数流入しているとか、ほとんどの者が莫大な金を携帯し、直ちに商売を始めているとか、宗教上の不寛容のゆえにどこかの分野で優位に立つと他の人々を排除し始めるといったことが、まことしやかに信じられています……ここで宗教的憎悪が爆発しないことを祈るのみであります。しかし私には、ワシントンがこの反ユダヤ感情の増殖を認識し、留意しつつ臨機に手を打って沈静化に努めるべきと思考されます』」
「戦後、トルーマン大統領は、『ユダヤ人はきわめて利己的だと分かった。ユダヤ人は自分たちが特別の扱いを受けている限り、他の人がどうなっても構わない。エストニア人、ラトビア人、フィンランド人、ポーランド人、ユーゴスラビア人、ギリシア人だって、殺され、あるいはDP(離散民)キャンプで虐待されているのだ。一方、彼らが物理的な、あるいは経済、政治的力を持っていると、ヒトラーもスターリンも、負け犬に対する残虐行為をやるための理屈をつけない』と述べている。イスラエルの熱烈な支持者にしてこの言である。
ヒトラーのもとで苦しみ殺されていくユダヤ人に、アメリカの政治家は何の救助行動もとらなかったが、トルーマンの発言からその理由がわかる。」
■■追加情報 5:連合国が断固たる措置をとっていたらユダヤ人の犠牲者はもっと少なくて済んだ
●現在、ハンガリーのコシュート・ラヨシュ大学で、近代ヨーロッパ史を担当しているプレプク・アニコー教授は、著書『ロシア、中・東欧ユダヤ民族史』(彩流社)の最後のページで、ホロコーストについて次のように述べている。
参考までに紹介しておきたい。

『ロシア、中・東欧ユダヤ民族史』
プレプク・アニコー著(彩流社)
「ホロコーストは狂気の一時的な勝利であった……しかし、ナチス・ドイツと戦った連合国にも重大な責任がある。
犠牲者数の多さは明らかに、反ファシズム連合諸国の断固たる措置があれば減じられたであろう。ナチスが一時的に大量殺戮を巧妙に隠蔽していたとしても、連合国政府は1944年夏に脱走したアウシュヴィッツ収容者の証言から、強制収容所における残虐行為を明確に把握できたはずである。
しかしながら、イギリスはこうした事実にもかかわらず、パレスチナの国境開放に積極的でなく、大戦当初からユダヤ人難民の乗った船舶の入港を終始妨害し続けた。
アメリカの姿勢も実質的に変わりはなかった。1940年、アメリカ議会は『アラスカ開放計画』に反対し、翌1941年には移民割当数をさらに引き下げ、2万人のドイツ系ユダヤ人児童が割当を超える入国を拒否された。
1943年には英米政府が難民に『門戸開放』を行うべく交渉したが、しかしバミューダ島の秘密会議では協定の調印に失敗した。
連合国軍は強制収容所の位置に関する正確な情報を得ていたものの、戦争の終結に専念していて、アウシュヴィッツ収容所やそれと連結する交通網を爆破するという案を棚上げしていた。このため大戦末期には、死者の数に比べて救出し得るユダヤ人の割合は、既に微々たるものになっていた。
〈中略〉
大戦後、中・東欧の大半の国々で権力の座に就いた新政府は、こうしたユダヤ人迫害を批判していたが、ユダヤ人に対する違法行為の解消や、反ユダヤ主義の原因の解明や、迫害に加担した非ユダヤ人の責任を明確化すべく、真剣に取り組んだ国はほんのわずかであった。
生き残ったヨーロッパ・ユダヤ人にとって、戦後は多くの点で新時代の始まりであった。しかしながら、その後の半世紀の歴史を返り見れば、これまで我々が考察してきた諸問題を20世紀の後半も受け継いでおり、21世紀も引き継ぐであろうことは明らかである。」
■■追加情報 6:アメリカのブッシュ大統領は語る「アウシュヴィッツは爆撃すべきだった」
※↓注目すべきニュース記事である。参考までに載せておきたい。
【エルサレム共同】 2008年1月、中東歴訪中のジョージ・ブッシュ大統領が、エルサレムのホロコースト記念館「ヤド・バシェム」を訪れた際、ナチス・ドイツによる虐殺が行われたポーランドのアウシュヴィッツ強制収容所を「爆撃すべきだった」と語っていたことが分かった。
案内役を務めた館長によると、大統領は目に時折涙を浮かべながら見学。
第二次世界大戦中のアウシュヴィッツ収容所の空撮写真の前に立った際、随行していたライス国務長官に、虐殺の進行を防ぐため「我々はここを爆撃すべきだった」と述べたという。
大戦中、アメリカなど連合国は同収容所で虐殺が行われている事実を把握していたが、ナチスへの軍事作戦を優先。収容所の建物やそこに通じる鉄道線路などは爆撃せず、戦後、判断の是非が論議になった。
AP通信によると、イスラエルのホロコースト研究者は、「爆撃すべきだった」という見解を示したアメリカ大統領はブッシュ氏が初めてだと語った。大統領は記念館で「ホロコーストの歴史は、悪と遭遇した時には抵抗しなければならないということを教えている」と述べた。
(共同通信 2008/01/12)
https://news.infoseek.co.jp/article/080111jijiX282


第43代アメリカ大統領ジョージ・ブッシュ
※ エルサレムにあるホロコースト記念館を訪れた際、
虐殺の進行を防ぐため「我々はアウシュヴィッツ収容所を
爆撃すべきだった」との異例の見解を示したという
── 当館作成の関連ファイル ──
◆ソ連・東欧諸国でのユダヤ人虐殺 ~知られざる第二次世界大戦の悲劇~


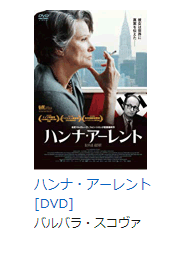

Copyright (C) THE HEXAGON. All Rights Reserved.